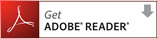伊達政宗の挑戦、蒲生氏郷の理想
第7回 第1部 2019年11月16日(土)
※オンライン講座はありません。
関東進出の布石として会津に侵攻した若き伊達政宗と、その牽制のため豊臣秀吉に送り込まれた蒲生氏郷。豊臣政権による奥羽仕置を軸に、戦国武将たちの目論見や統治から会津という土地を見直す。

いま求められる“旅マタギ”
第7回 第2部 2019年11月16日(土)
※オンライン講座はありません。
郷里を離れ、諸国を行脚した秋田の“旅マタギ”。害獣駆除を担うことで市場経済に順応した彼らは、人と自然が共生する上でのキーマンだった。狩猟の民の生き方を通して、現代の都市と地方の関係を問う。

北の関ヶ原合戦と上杉家の思惑
第6回 第1部 2019年9月28日(土)
※オンライン講座はありません。
1600年(慶長5年)、上杉景勝の上洛を巡り徳川家康が出陣。景勝の重臣直江兼続と、家康方の最上義光・伊達政宗が山形で戦った「北の関ヶ原合戦(慶長出羽合戦)」の実態を全国的視野で捉え直す。

芹沢銈介が残した東北の美
第6回 第2部 2019年9月28日(土)
※オンライン講座はありません。
民藝運動の中で柳宗悦と東北を巡り、各地の手仕事の保存や収集に努め、その美を「型絵染」の作品にも取り入れた染色工芸家・芹沢銈介(けいすけ)(1895-1984)。彼の目と旅を通して、東北の民藝に迫る。

十三湊から解き明かす北の中世史
第5回 第1部 2019年7月6日(土)
※オンライン講座はありません。
中世の日本海交易における要衝だった十三湊(とさみなと)。発掘調査から浮かび上がってきた巨大港湾都市の姿と、日本国の北の辺境北奥羽・北海道を支配した豪族安藤氏の実像を解明する。

東北で紡がれた手しごとの物語
第5回 第2部 2019年7月6日(土)
※オンライン講座はありません。
温かさのために糸を重ねた刺し子、山人の食を支えた曲げわっぱなど、風土や暮らしの知恵から生まれた工芸品。作り手300人余りを訪ねた店主が、その美に込められた技と心を語る。

多賀城が物語る古代東北の姿
第4回 第1部 2019年5月12日(日)
※オンライン講座はありません。
律令国家による東北経営の拠点として724年(神亀元年)に築かれた東北最大規模の城柵・多賀城。奥州藤原氏の時代へと連なる東北古代史の300年を、多賀城発掘研究から読み解く。

幻想世界“イーハトーブ”の新検証
第4回 第2部 2019年5月12日(日)
※オンライン講座はありません。
宮沢賢治の心象風景を表したといわれる摩訶不思議なドリームランド“イーハトーブ”。時に異界ともつながる幻想世界の実像を、現代のエンターテインメントとの関係を軸に紐解く。

PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerダウンロードへ