
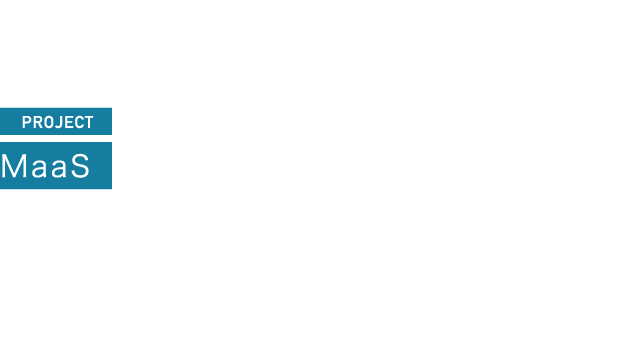
PROJECT 1
Ringo Pass

PROJECT 1
Ringo Pass
篠田 恵
MEGUMI SHINODA
- MaaS・Suica推進本部
- MaaS事業部門
- MaaSサービス開発グループ
- 2013年入社(総合職)
「Ringo Pass」が最も大切にしている、ユーザーの利便性。そのユーザーとの接点を担っているのが篠田である。アプリのUI(ユーザーインターフェース)の開発と、実証実験に参加しているユーザーへのインタビューおよびその結果をプロジェクトチーム全体にフィードバックする役割を務めている。また、実験参加企業の開拓でも重要な役割を果たしてきた。

自分たちの足で集めた実証実験のモニター。
篠田が「Ringo Pass」プロジェクトに加わったのは、実証実験に向けて作業が本格化した2018年の4月だった。
「プロジェクトに加わって最初に担当したのは、2人目のお子さんの誕生にともなって1ヶ月間の育児休暇に入った先輩社員の業務のフォローでした。いきなりの話で戸惑いましたが、おかげでRingo
Passのアプリやサーバーの仕様を理解することができました。その後、実装の管理に携わるとともに、実証実験にユーザーとして参加していただけるモニター企業の開拓を始めました」
2018年9月に開始するRingo Passの実証実験への参加者は、篠田を中心とするプロジェクトのメンバーが個別に企業を訪問して集めた。ターゲットは、都内移動を頻繁に行う営業職が多い会社。
「タクシーはまだ賛同を得やすかったのですが、シェアサイクルは馴染みが薄いこともあってかなり苦戦しました。結果的には“使ってみたら便利だった”との声を多くいただきました」
Ringo Passで利用できるドコモ・バイクシェアは、都内に多くのサイクルポートを置いている。Ringo
Passアプリの地図画面に近くにあるポートが表示され、自転車にSuicaをタッチすれば鍵が開いて走れる状態になる。実験開始の1ヶ月後からユーザーインタビューを開始して得たのが「使いやすい」との声だった。
「一方で具体的な要望もいくつかあり、予約機能を実装する優先順位を上げることにしました。開発チームの中ではそれほどニーズが高くないだろうと考えて実装を後に予定していたのですが。ユーザーの生の声を聞くのはやはり重要です」

ユーザーの希望を理解しRingo Passを正しい道に導く。
シェアサイクルより数ヶ月後から実証実験を始めたタクシーの場合は、Ringo
Passアプリの地図に近くを走っているタクシーが表示され、乗車後に車内のQRコードをアプリで読み取れば決済予約の状態になる。到着後はタクシーメーターの料金を確認し、レシートを受け取って降りるだけだ。
「タクシーのユーザーインタビューはまだ始めていませんが、どのような意見が聞けるか楽しみですね。またモニター企業の開拓も、開発が少し落ち着いたら再開する予定です。ユーザーインタビューで集まった意見は、モニターの開拓にも活かせるはずです」
会社がモニター参加を決めても、社内で実際の参加者を集めなければならない。そのサポートや、参加者向けの説明会なども篠田は担っている。UIを主とした開発担当でありながら、営業的な仕事も担っているのである。
「インタビューだけでなくさまざまな場面でユーザーと接することができるのは、開発を進める上でのメリットになっています。今後、Ringo
Passとつながるモビリティパートナーが増え、サービスの拡充も進んでいくはずですが、ユーザーが何を求めているのかをよく理解し、Ringo
Passを正しい道に導いていくのが私の重要な役割だと考えています。」
Ringo Passをユーザーに歓迎されるアプリに磨き上げ、本サービスに持っていくのが今の一番の目標です。そして移動の快適が実現できたら、駅周辺やその先の目的地までの情報提供や、エンターテイメントコンテンツの提供など、移動中の楽しさも届けられるようになれば、と思っています。Ringo Passを軸に未来を考えても、色々な夢が広がりますね。モバイルSuicaやJR東日本アプリなど、社内にはさまざまなモバイル関係のリソースがあり、いずれはそれらが融合して、お客さまとJR東日本を結ぶ新たなサービスへ進化していくのだろうと予想しています。

大学ではマーケティングを学んでいたが、何かにつけ自分がやりたいと思ったことを実現するには技術知識が必要だと考え、「IT」職種で入社した。東京支社での機械設備のメンテナンスや工事の他、JR東日本情報システムへの出向などで、機器やシステムの知識を蓄積してきた。今回のプロジェクトで自身にとっての最初の山場は、2018年8月のアプリのリリース。自分たちで一から作り上げたサービスを世に出す緊張感には特別なものがあったという。


















