

INTERVIEW 5
世界高速鉄道会議の開催
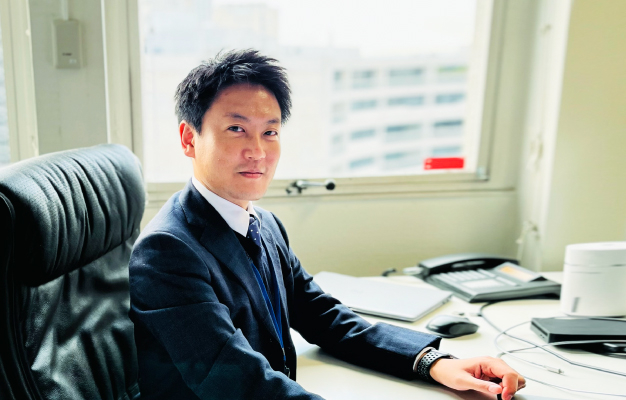
世界高速鉄道
会議の開催
髙階 建太
KENTA TAKASHINA
- 国際鉄道連合出向
- 旅客局
- 2006年入社(総合職)
新型コロナウイルス後、経営環境が大きく変化する世界各国の鉄道に関する国際協力を推進し、モビリティと持続可能な開発に関連する現在及び将来の課題解消を目指す国際鉄道連合(UIC)。1922年に設立され、現在は90ヵ国の200団体が加盟する国際機関となっている。JR東日本のパリ事務所に所属する髙階は、UICの旅客局に上級顧問として出向し、高速鉄道の推進・普及・連携に向けた活動や提言を行っている。2023年3月には5年ぶりとなる世界高速鉄道会議をモロッコで開催し、高速鉄道に特化した世界最大規模の国際会議・展示会を成功させた。社会が大きく変化し、高速鉄道が多様化するなか、髙階は世界各国の関係者とともに鉄道の未来を考え続けている。

「地球にとって適切な速度」をテーマに、世界高速鉄道会議を開催。
UICの旅客局へ出向し、2年半。髙階は、高速鉄道の発展のために、大学機関との連携や仕様の標準化、統計データの収集・分析など、さまざまな業務を進めてきた。UICの旅客局に駐在している日本人は赴任当初髙階ひとりであり、個性的な同僚に、出向した当初はカルチャーショックを受けた。
「仕事の進め方ひとつとっても、 “当たり前”とされる文化や価値観が日本とは全く異なります。異文化理解を深めながら、同僚と円滑にコミュニケーションを取りつつ、互いの意見を汲み取り、形にできるよう柔軟性をもって対応する必要があると強く感じました」
髙階がUICで担った重要なプロジェクトが、第11回UIC世界高速鉄道会議の開催だ。世界高速鉄道会議は、1992年から数年おきに開催されてきたが、コロナ禍のために、今回5年ぶりに開催されることとなった。髙階は、パラレルセッション(世界24ヵ国、約160名の高速鉄道関係者によるプレゼンテーション発表)の責任者を務めるとともに、全体スケジュールの管理から各国からの来賓の情報集約など、運営に関わる多様な役割を担った。また、日本の新幹線技術やJR東日本のプレゼンス向上のために、自らプレゼンテーションも行った。
国際鉄道組織の代表者や政府関係者、鉄道会社の幹部などが参加する世界高速鉄道会議は、世界各地の高速鉄道の発展や鉄道会社の事業戦略に大きな影響力を持っている。
「今回の会議のテーマは、『地球にとって適切な速度』としました。高速鉄道は最高速度が時速330kmを超えると建設初期投資・メンテナンスコストなどが高くなり、環境基準などの課題が顕著化します。そうしたなか、地域の需要や許容できるコストによって、最適な高速鉄道の形態は異なってくるという認識を共有するとともに、速度にこだわらずに高速鉄道を導入する柔軟性も必要であることを会議のなかで確認しました」
会議直前に新型コロナウイルス感染者が急増していた中国からの発表者が入国規制を受けたり、トルコ南部の地震の影響でトルコからの発表者が欠席したりするハプニングもあったが、最終的に柔軟に対応しパラレルセッションには、世界24ヵ国から約160人の発表者が出席。会議には48ヵ国からの1,500人が参加した。コロナ禍の影響力を受けながら目標としていた参加者数を達成し、世界高速鉄道会議は無事に終了した。

高速鉄道の発展に貢献しながら、JR東日本の新規事業の種を探す。
大学では機械工学を学び、歯車の振動低減や音の静寂性を研究していた髙階。鉄道車両の快適性や静寂性の技術に興味を抱き、JR東日本に入社した。運行の最前線で車掌や運転士、車両メンテナンス業務などを経験し、その後本社で研究開発戦略や新幹線高速化の推進に携わった。研究開発戦略に関しては、30年後を見据え、「安全」「サービス」「オペレーション」「環境」などについての中長期ビジョンの策定に関わった。
「研究開発戦略に携わるなかで強く興味を惹かれたのが、IoT、AI、自動運転などの最新技術です。技術や導入が進むヨーロッパで最新技術事情を学びたいという想いが大きくなり、パリ事務所への異動を希望しました。パリ事務所で進められている活動は大きく『インバウンド』『標準化』『国際ビジネスの開拓』の3つの分野にわけられますが、私が携わっているのは『国際ビジネスの開拓』です。UICでの業務と平行して最新技術や海外市場のリサーチを行い、新たな国際ビジネスを創出していくための活動を行っています」
現在は、モロッコでの世界高速鉄道会議を終えたばかり。次回の開催は中国で2025年。準備を始めるまでには猶予があるため、最近は技術や市場のリサーチ活動に力を入れている。これまでに築いたネットワークを活かし、海外の鉄道事業関係者とも積極的に会い、情報収集を進めている。
「IoTやロボット等の最新技術を迅速に導入し、ものごとを柔軟に考える海外の鉄道事業者や企業などの姿を目の当たりにして驚くこともあります。JR東日本が、新幹線やSuicaに続く新しい価値を世の中に生み出していくには、外国を含め様々な会社や研究機関と柔軟に連携や協調をしながらタスクフォースを組み、スピードを持って取り組んでいくことが今後ますます必要になってくると私は感じています」
遠くない未来に自動運転社会が到来し、鉄道を取り巻く環境が大きく変わるとも言われている。そうした未来を見据え、髙階はJR東日本や鉄道ビジネスの進むべき道を模索し続けている。
新幹線のような電気で動く高速鉄道だけでなく、リニアモーターカーやハイパーループなども誕生し、高速鉄道は今後、多様化しながら発展していくはずです。さまざまな方式で高速鉄道が進化していくなかで、それぞれがどのようなビジネススキームで成り立ち、また、どのような地域や環境下での導入に適しているのかなどの定義付けを今後行っていきたいと思っています。また、現在はアフリカや東南アジアでも高速鉄道の導入計画が進んでいますが、大きなハードルとなっているのが建設コストです。300km以上の距離に高速鉄道を建設するとなると、何十兆円という予算が必要になり、そのような莫大なコストが導入計画の妨げになってしまうことが多々あります。一方で、時速200km程度で走る“準高速鉄道”なら、コストを大きく抑えて建設できます。そうした情報の認知を広げ、より多くの国や地域に準高速鉄道を導入してもらいたいと考えています。

車両メンテナンス業務や運行業務、支社での車両保全計画などに携わり、戦略的な思考の重要性を感じたことから社内留学制度にて国内大学院に入学、イノベーションマネジメント研究科技術経営戦略学専攻で1年間学ぶ。その後の研究開発戦略や国際機関との調査業務などを担当した後に、パリ事務所へ。今後は、技術者として、AIやIoT、ロボットなどの最新技術を活かしたメンテナンスのコストダウンや生産性の向上を実現したいとも考えており、将来は鉄道のリソースを活用した国際ビジネスや新規事業やスタートアップに挑戦したいという目標もある。















