
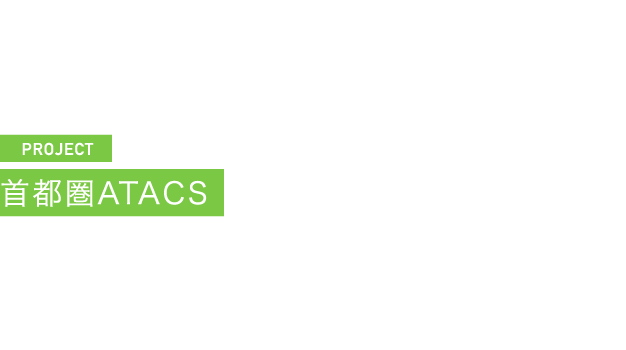
INTERVIEW 3
無線式列車制御システム「ATACS」
埼京線導入プロジェクト

無線式列車制御
システム「ATACS」
埼京線導入
プロジェクト
大上 真平
SHIMPEI OKAMI
- 東京電気システム
- 開発工事事務所
- ATACS埼京
- 2010年入社(総合職)
首都圏で初めて導入されるATACSは、安全性・安定性の向上、地上設備のスリム化、踏切警報時間の最適化などを実現する次世代の列車制御システムである。社内外から注目されるプロジェクトで、大上が課せられたミッションは精度の高い確実な設計を行うこと。世界初のATACS導入となった仙石線の踏切制御機能の導入工事を経験した大上は、その実績が買われて首都圏ATACSプロジェクトに抜擢。しかし、そこには仙石線とは異なる課題が待ち受けていた。夜のわずかな時間の中での工事が強いられ、より緻密な工程管理が問われる。また関係各所との密接な連携を取るという役割も担いながら、大上は果敢に工事に挑んだ。

次世代の列車制御システムATACS工事に関わる喜び。
その朝、大上はJR大宮駅でホームから走り出す埼京線の始発電車を祈るような気持ちで見守っていた。首都圏ATACS初導入の朝、同プロジェクトに携わった設計担当者は前日から自らが携わった工区の駅に詰めて、その瞬間を迎えていた。大上も自身が担当した大宮駅ホームで、記念すべき始発電車を見送ったのだ。
「首都圏ATACSは池袋駅から大宮駅に導入されましたが、私が担当したのは北戸田~大宮駅間。プロジェクトに参加して約2年半、待ちに待った瞬間でした。始発電車の出発を見届けてから数十分後、上下列車の運行が無事確認できたという連絡が入った時は心の底からホッとしたと同時に、じわじわと達成感がこみ上げてきました」
そう大上は2017年11月の出来事を振り返る。また、この日は大上のみならずJR東日本にとっても記念すべき日だったといっても過言でもない。従来、列車制御システムの多くはレールに電流を流して列車が在線する位置を検知し(軌道回路)、信号機によって後続列車の運転士に対して走行可能な区間と速度を指示する方式である。この方式では、列車は信号機で区切られた1区間に1列車しか運転できないという制約や、線路の周りに軌道回路や信号機などの多くの地上設備を設ける必要があり、メンテナンス業務の負担や災害時などの設備破損リスクといった課題も抱えていた。
「その点、ATACSは無線設備を使って車上・地上間で双方向に情報通信を行うことにより列車を制御する全く新しいシステムです。軌道回路を無線と車上装置に置き換えることで地上設備は最小限に抑えられ、故障リスクの低減とメンテナンスの簡略化ができます。また、指令員による速度制限の設定や車上データベースを基に、車上で速度パターンの演算と速度照査を連続的に行い、ブレーキを出力します。そのためにヒューマンエラーによる速度超過などを防ぎ、安全性・安定性も向上するシステムなのです」
しかも車上装置が列車の速度と性能を基に踏切までの到達時間を演算し、踏切の警報開始を指示。これによって適切な警報時間が実現したのだ。これまでも無線通信を用いた列車制御システムは存在したが、踏切制御機能までも含めたシステムとしては、ATACSが世界で初めてのシステムだった。
JR東日本が誇る技術の粋を集めた列車制御システムとして、内外から大きな注目を集めていたプロジェクトである。大きな責任を果たした喜びと安堵感が、大上の胸を満たしたのは当然のことだろう。

世界最先端の仕事をやり遂げたことが自信につながる。
大上が首都圏ATACSのプロジェクトに抜擢されたのには理由がある。それは入社3年目から携わった仙石線のATACS踏切工事での経験である。仙石線のATACS導入は世界初のシステムとして注目されたプロジェクトだった。
「入社後は東北工事事務所で小規模な工事を数多く経験。電気部門の大きなプロジェクトではありませんでしたがプロジェクトの進め方や工事の基礎を身につけることができました。その後、当時、プロジェクトが進んでいた仙石線のATACSを担当する部署に異動になり、踏切制御機能の導入工事を担当。そこで設計業務や工事監督業務を任されスキルを磨くことができました。」
ATACSの技術に触れた大上が、首都圏ATACSのプロジェクトに抜擢されたのは当然の経緯といえるだろう。しかし、同じATACSの導入でも仙石線と埼京線では状況がかなり異なる。まず首都圏に住む人々の通勤や通学を担う埼京線は終電から始発までの時間はわずか数時間しかない。その間に滞りなく工事を進めなければならず、緻密な工程管理が求められる現場になったことはいうまでもない。
またATACSは首都圏では初めての導入のため、ATACSに精通した技術者は、JR・パートナー会社共に少ない。当然、前例がなく既存の知識や経験だけでは進められないことが多いため、工事監督や実際に施工する協力会社のスタッフなど関係者一同が毎月一回以上集まり、安全上の課題や技術的な課題を検討しながら工事を進めていった。特に約1年もの期間をかけて行った夜間の実車走行試験については、毎回多くの関係者による入念な準備のもと、進められた。加えて導入後にメンテナンスを担当する東京支社・大宮支社ともメンテナンスの課題などを議論し、ATACS設備のメンテナンスマニュアルを作成することも大上の重要な任務だった。
「これだけ多くの方々と意見交換や調整をしながら工事を進めたのは初めての経験。その他にも、設計者として工事契約書業務や図面の作成、社内外の関係者との調整を滞りなく進められたこと、幅広い仕事をやり遂げたということは大きな自信につながりました」
こうしてようやく首都圏ATACSは完成を迎え、首都圏の基幹交通網である埼京線の安全性・安定性に大きく寄与している。
入社後早い時期から最先端の技術であるATACSに関われたのは技術者として幸運でした。仙石線と埼京線のプロジェクトを合わせると約7年もATACSに携わった計算になります。今後はATACSに関わる知識や技術をさらに磨き、設備のシステムチェンジに貢献することが私の役割になると考えています。できるなら次の線区のATACSの導入工事にもかかわって、これまでの経験で身につけた技術や経験を活かしていきたいですね。同時に後輩たちにATACSの知識や技術を伝えていくのも私に役割になります。ATACSプロジェクトでは、先輩はまだキャリアの浅かった私に責任ある仕事を任せて成長を促してくれました。その育成方法を引き継いで後輩にATACSの技術を継承していきたいですね。

東北工事事務所でキャリアをスタート。3年目からは仙石線ATACSを担当する部署に異動。その後、東京電気システム開発工事事務所に異動して埼京線ATACS導入工事担当になる。現在は、埼京線ATACSによる踏切制御機能導入工事に携わる。休日は主に神宮球場にてプロ野球を観戦して鋭気を養うなど「ON」と「OFF」を上手に切り替えて仕事に向き合う。


















