
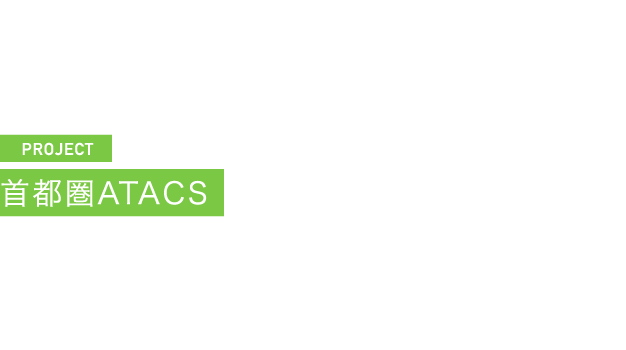
INTERVIEW 1
無線式列車制御システム「ATACS」
山手線・京浜東北線導入プロジェクト

無線式列車制御
システム
「ATACS」
山手線・京浜東北線
導入プロジェクト
宮林 直樹
NAOKI MIYABAYASHI
- 鉄道事業本部
- モビリティ・サービス部門
- 次世代輸送システム推進センター
- (ATACS)
- マネージャー
- 1998年入社(総合職)
JR東日本の先進技術を集約し、導入が進められている首都圏ATACS。2017年にATACSの運用を開始した埼京線に続き、現在は山手線・京浜東北線(大宮〜東神奈川)への導入プロジェクトが進められている。首都圏の“大動脈”とも言える2路線への導入を担うプロジェクトチームにおいて、全体をマネジメントするのが宮林の役割となる。各設備の主担当の意見調整を行うとともに、社内の関連部門や国土交通省、総務省、機器製作メーカーとの折衝などを担い、プロジェクトを推進している。

国鉄時代からの想いが結実した、仙石線へのATACS導入。
「99.9%ではダメ。100%の安全性を求められるのが列車制御システムの難しさであり、おもしろさです」と語る宮林。学生時代にはプログラミングや情報セキュリティを学び、列車制御システムに携わりたいという想いを抱いてJR東日本に入社した。入社後にまず任されたのは、新幹線の安全性を確保するための地上設備の設計。東北新幹線の八戸延伸工事プロジェクトでは、設計・工事監督・施工のすべてを担当し、貴重な経験を積んだ。
「パートナー会社に出向し、施工も担当させてもらいました。そのおかげで、設計から施工までの全体を俯瞰できる広い視野を得られましたね。そのときの経験が今も活きています」
一方、JR東日本が国鉄から開発を引き継いだATACSは、2000年代に入ってようやく実用化の目処が立つ。2008年には、仙石線(あおば通〜東塩釜)へのATACS導入プロジェクトに宮林も参画することとなった。「当時はATACSの導入に懐疑的な見方もありました。実現は難しいだろうという意見が多いなかで、逆風を感じながらプロジェクトを進めました」と笑う宮林は、仙石線への導入は険しい道のりだったと振り返る。しかし、関係者の強い熱意のもとで粘り強くプロジェクトは推進され、2011年の使用開始にまで漕ぎ着ける。だが、3月に予定されていたATACSへの切り替えは、東日本大震災と台風の影響で2度も延期に。2011年10月10日が、ATACSの使用開始日となった。切り替えを見届けた宮林は、大きな喜びと安堵を感じたという。
「実は、震災や台風でも、スリム化されていたATACSの地上設備にはほとんど被害がありませんでした。また、通常は多少のトラブルがあるシステムの切り替えも非常にスムーズに行うことができました。そうした点からも、ATACSのすごさを改めて感じましたね」

新たなモデルへ進化する山手線・京浜東北線のATACS。
列車運行の柔軟性と安全性を高め、地上設備をスリム化するATACS。その真価は、運行ダイヤが過密で、地上設備用のスペースが限られている首都圏でこそ発揮される。仙石線での使用開始を経てJR東日本は、埼京線(池袋〜大宮)へのATACS導入を決定する。そして、仙石線より大幅に運行密度の高い埼京線においても導入に成功。2017年11月に使用開始となった。
そして、2018年。埼京線よりもさらに高密度線区である山手線・京浜東北線(大宮〜東神奈川)へのATACS導入プロジェクトが発足。リーダーを任されたのが宮林だ。山手線・京浜東北線は日々膨大な数のお客さまが利用し、万が一トラブルが起きれば社会的に大きな影響が生じてしまう。宮林が背負う責任は大きい。
「もちろんプレッシャーはあります。でも、山手線・京浜東北線を任せてもらえることに大きなやりがいを感じています。多くの方にサポートいただきながら、この重要プロジェクトを進めていけるのは幸せなことです」
山手線・京浜東北線に導入されるのは、フルモデルチェンジされた新たなATACS。運行密度が極めて高く、お互いの線路を走行することもある山手線・京浜東北線に対応するために、多機能かつ高性能な新モデルへと進化を遂げることとなった。仙石線では安全性を維持しながら列車間の距離を200mまで詰められる仕様になっていたのを、埼京線では100mまで短縮し、山手線・京浜東北線ではさらに50mにまで縮める。また、ATACSの導入に合わせてATO(自動列車運転装置)の高性能化も進めることで省エネ運転などを可能にし、効率的な運行を実現していく。
山手線・京浜東北線でのATACSの使用開始は、2028年〜2031年ごろを予定している。「プロジェクトはまだ始まったばかり」と話す宮林の目は、鉄道の未来へと向いている。
JR東日本では2021年に次世代輸送システム推進センターを設立し、信号・運転・車両の各部門から人員が集い、三位一体となって新システムの開発から運用までを進められる体制を構築しました。ATACS導入プロジェクトも、このセンターのメンバーをはじめとした多くの方のサポートを受けて進めており、必ず成功させることができるはずです。ATACSは列車の安全・安定運行を支えるものですが、それを実現することによって、さらには自動運転(ドライバレス運転)へとつながっていくはずです。JR東日本が実現しようとしているのは、通常の自動運転とは大きく異なる“賢い自動運転”。決められたパターンに沿って動くのではなく、列車自身がそのときどきの状況に合わせて判断し、利便性や効率性に優れた運行を行う自動運転です。

山形新幹線や東北新幹線の延伸工事、本社での列車制御システムの仕様検討・制定、信号設備の維持管理など、入社以来多様な業務に携わる。2008年からは仙石線のATACS導入プロジェクトにおいて導入工事・多賀城高架化工事を担当。その後、品川信号技術センターの副所長を務めたあと、ATACSの技術を活用した地方交通線向け無線式列車制御システムを小海線へ導入。山手線・京浜東北線へのATACS導入プロジェクトが2018年に発足するとともにリーダーに。小学生のころから野球に親しみ、現在は電気システムインテグレーションオフィスの野球部に所属。JR東日本グループの懇親野球大会で優勝したことも。


















