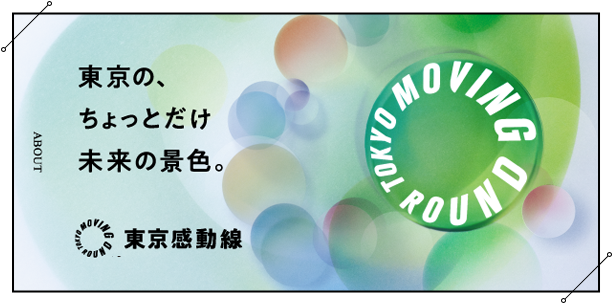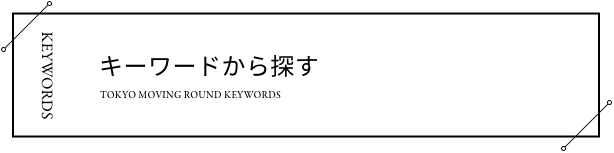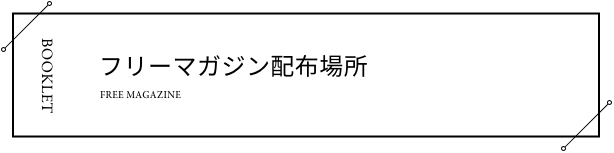- カテゴリ
- まち
古地図が教えてくれる
江戸から令和への移り変わり
高層ビルが立ち並び、先進的な印象の田町・浜松町エリア。
このエリアを古地図で見てみると、増上寺を中心に寺社や大名屋敷が立ち並び、その合間に町人地が点在する、さまざまな身分階級の人々が暮らす街だったことがわかる。
このエリアは約400年前、徳川家が江戸に入府した際に、江戸城周辺の城下町としてかたちづくられた。
しかし、明暦の大火(1657年)により、江戸城周辺の大部分が焼失。
浜松町・田町の郊外のエリアに都市は拡大され、大名屋敷が多く立ち並ぶようになる。
さらに、町人が大名や家臣たちの生活を支える飲食店や服屋などを営み、都市機能は充実していった。
【最初の上の写真】
「安政改正御江戸大絵図」/国立国会図書館ウェブサイトより転載
【写真1】
『浜の御苑之記』/資料提供:国立国会図書館蔵
江戸時代の浜離宮恩賜庭園を描く土岐頼旨の作品。潮入の池を中心に、鷹の御茶屋などが描かれている。将軍が風情を楽しむほか、賓客をもてなす場でもあった。
【写真2】
浜離宮恩賜庭園
「浜離宮恩賜庭園」。江戸時代から残る潮入の池に現代のビルが映り込んでいる。
古地図と現在の地図を見比べたときに、その違いがよくわかるのは海岸線。
現在、山手線が走る東側は江戸時代には海が広がっていた。
山手線の線路わきに佇む本芝公園を含む一帯もかつては海に面しており、雑魚場と呼ばれる魚市場があった。
古典落語『芝浜』の舞台でもあり、漁師たちはここで漁業を行っていた。
【写真3】
『東海道名所風景』「東海道名所之内 芝増上寺」/国立国会図書館ウェブサイトより転載
正面から増上寺を眺めた錦絵。増上寺は徳川家の菩提寺で浄土宗の大本山。江戸期には3000人もの僧侶が修学に励む。当時は大門の前に堀が通っていた。
【写真4】
増上寺大門
ビジネス街に佇む「増上寺 大門」。奥には江戸初期から残る三解脱門が望める。かつての堀は、現在は埋め立てられている。
しかし、1853年の黒船来航を契機に海岸線の防備が必要になり、台場をつくるなど整備がはじまる。
明治時代に入ると堤防がつくられ、海の上を鉄道が走っていたという。
大正時代以降、埋め立てが進み、戦後の高度経済成長期に更に拡大、現在の海岸線をかたちづくった。
雑魚場は昭和45年に埋め立て工事が行われ、本芝公園に姿を変えた。
公園としては珍しい細長いかたちは雑魚場であったことの名残だ。
舟を模した石碑が残され、都会の一角の憩いの場として親しまれている。
【写真5】
薩摩鹿児島藩島津家第2遺跡 豚の下あご骨/港区立郷土歴史館
薩摩鹿児島藩島津家第2遺跡から出土した豚のあご骨。
食肉が公に行われていない当時に薩摩藩では豚肉を食べていたことがわかる。
【写真6】
芝さつまの道
薩摩藩屋敷があった芝さつまの道。
当時、徳川家の菩提寺であった増上寺は江戸の入り口として、徳川家の権力を示すランドマークの役割を担っていた。
現在、敷地面積は縮小されているが、現在の増上寺の入り口である三解脱門は当時の姿を残し、国内外から多くの人が訪れる観光地。
また、現在「芝さつまの道」と名のつく通りは、当時の有力藩である薩摩藩藩主が住む「居屋敷」があった場所だ。
高層ビルが立ち並ぶいまも、このエリアは時の重なりと歴史の息吹を感じられる地である。
『お話しをうかがったのは』
港区立郷土歴史館 学芸員 石田七奈子さん
【写真7】
『東海道名所圖會』6巻/国立国会図書館ウェブサイトより転載
埋め立て前のこの地域は「芝浦」と呼ばれる海岸地帯だった。当時の漁業の様子が描かれる。
【写真8】
本芝公園
雑魚場跡である「本芝公園」。モリなどの漁業道具が彫り込まれた舟の彫刻がある。
趣ある建築物の中で歴史を学べる
スクラッチタイルで覆われた重厚感のある建物。港区の歴史的資料を収蔵・展示する「港区立郷土歴史館」を中心に、2018年(平成30年)に開館した「ゆかしの杜」は、がん在宅緩和ケア支援センターや子育て関連施設などもあり、地域の人に親しまれる複合施設だ。
もとは1938年(昭和13年)に建設された「旧公衆衛生院」の建物で、東京大学建築学科教授、内田祥三(よしかず)氏設計の「内田ゴシック」と呼ばれる外観が特徴的だ。
建物内部にも建設当初の遊び心あるデザインが残されている。建物見学は無料で気軽に参加できる。ぜひ訪れて歴史的魅力に触れたい。
【写真9】
港区立郷土歴史館