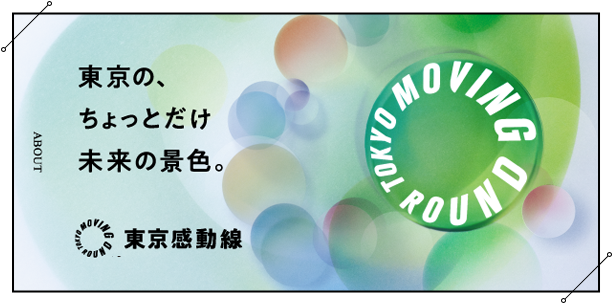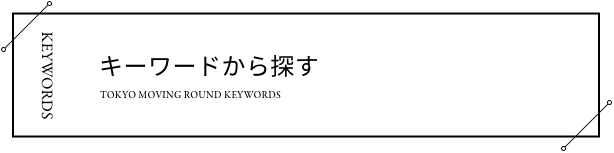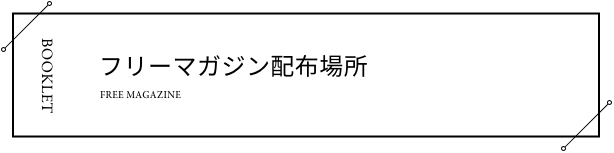- カテゴリ
- 交流・体験
毎月第二日曜日25:00〜26:00 ONAIR
真っ暗闇の中で、心と対話する時間を。
日曜の深夜。全てのしがらみから離れて本当に「独り」になっている特別な時間。人は誰もが不安や悩みを持っているはず。この番組は、自分の心と対話することの大切さを伝え、明日への活力を求める人への応援メッセージを発信するラジオ番組です。
志村:いや〜、夜中のラジオですけど、はい、今日はもう真っ暗なので、星も見えてないような暗闇ですね。
間:はい。
志村:あのう、間さんと初めてお会いしたのは去年の夏でした。
間:はい、そうですね〜。
志村:このアトレ竹芝がオープンして、もうコロナ禍でしたけれどもね、あれから1年もうそろそろ経つと思うんですけど、コロナ禍で今私達はオープンをし、耐え忍んで頑張ってきているお仲間だと思ってるんですが。
間:そうですね、本当に私、覚えていらっしゃるかわかりませんけれども、このテナントの皆さんで会ったときに、あー本当に竹芝村っていうようなそんな感覚をすごく感じたんですね。昔のやっぱりその村って、今のこの周りも村の多分景色だと思うんですけど、とっても懐かしさやいいことってたくさんありますよね、みんなで協力し合ったり、田植えもそうでしょうし、屋根のふき替えもそうでしょうし、なんかそういう感覚を僕はすごく感じたんですね、このアトレ竹芝から。ですから何とかみんなで協力し合って村をもり立てたいなって、そんな感覚がすごくあって。あのとき出展者の懇親会のときにちょっと私一言お喋りをさせていただいて、その後に季世恵さん寄ってきていただいて、すごく親しく声をかけていただいたじゃないですか。あれを僕はすごく覚えてますね〜。
志村:あー私も鮮明に覚えています、あのときのご挨拶が本当に素晴らしくて・・
間:いえいえ。
志村:私たちも・・・なんでしょう、ここはちょっと違うかもしれませんけど、昔でしたら長屋でね、醤油貸して〜とか、塩貸して〜とかって言ってお隣さん同士で助け合うような暮らしがあったと思うんですけど、でもそれがこの場で実現するんだなっていうふうに本当に感じた瞬間だったんです。で。私達は常に目が見えない人や聞こえない人たちが大勢いますので、助け合いって本当にもうないとやっていけない、そういうふうな職場でもありますけど、でもそれがあのう、助け合いっていうのは、弱い人が助けるだけじゃなくって、お互い様なんだなってことが大事だなと思ってるんですね。それが本当にこの竹芝からアトレの村から、この竹芝のエリアとか浜松町とかに広がっていて、それが世の中に、あ、そういうことだったよね〜昔ってってなんないかなって願いがあったんです。でもそれは間さんがおっしゃってくださったときに本当に嬉しくて・・・でそれを実現していらっしゃって、実は私本当に感動したことがあって、そのコロナで私達も緊急事態宣言で仕事ができなかったときに、エントランスで若いスタッフたちがどうしたらいいんだろうっていうふうにミーティングしてたそうなんですね。そのときに狭間さんが、美味しい美味しいお店のお菓子を差し入れてくださった・・・涙が出るくらい嬉しかったっていうふうに申してました。
間:あーそうですか・・私はあのう、ちょうど仕事を終えて帰るときだったんですね。で、ガラス越しに皆さんが丸く椅子に座って、皆さん真剣な顔でこうなにかを考えていらした、そんなお話してた、そんな風景だったんですね。なにかその風景を見たときに、急にドンと感情が出てきたわけですね。なにかわからないけれども、この皆さんになにか食べていただきたいっていう・・・そういう感覚だったんですね。ですから勝手にあんなことを、まあちょっと召し上がってくださいというようなことで持っていったことがありましたね〜。
志村:いや嬉しかったです〜。で、ちゃんとスタッフたちが私の分も・・・(笑)
間:ありましたか?大丈夫でしたか?(笑)
志村:もちろんです!もう十分でした・・・!それでもう嬉しくて、それが勇気に繋がるんですね〜。なんでしょう、もう駄目かもしれないと思うときのその温かさとか思いやりっていうのは、人に強い気持ちや勇気を与えてくださるんだなってことを本当に感じた瞬間だったんですけど、でも本当は飲食業界の方って私本当に大変なことだと思うんですけど、ご自身だけじゃなくて周りの人のことも見てくださっている、それを感じたときに、間さんの話をこの暗闇で伺いたいなと思ったんです。もうフレンチの世界では本当に有名で、私達からすると雲の上の方なんですけど。
間:とんでもないです。
志村:いやでも本当に飲食業界のこととか、そして今何を目指していらっしゃるんだろうとか、そういうことをお伺いできると、例えば今日今このラジオを深夜に聞いてくださっている方の中にも同じようなお気持ちでどうしようと思ったり、または飲食店をどうやっていったらいいんだろうとかってきっと思っている方もおられるかもしれない。
間:そうですね・・・。
志村:はい、そのことも伺いたいなと思ってたんです。
間:はい、ぜひ色々とお話をさせていただきます。
志村:お願いします。今はどんなことをお考えになっていらっしゃいますか?
間:そうですね、やはりこのコロナになって、楽しかったことももちろんありがたいなって本当に思ったこともありましたし、あぁ、悲しいなと思ったこともありました。やっぱりこのコロナの感染の中で飲食業がその感染のちょっと原因になっているような、そんな報道があった時期がありましたよね。
志村:そうでしたね。
間:あれをやっぱり聞いたときにはすごく、うーん・・・まぁ悲しいというか、残念な気持ちになりましたね・・・でもそれと同時に今度は応援してくださる方がいたりですね、本当に「間さん頑張ってね」なんて言って来てくださる昔から応援してくださるお客様だったり、そういう人たちのやっぱり「頑張ってね」だとか「応援してるよ」っていう言葉に、もう本当に一言一言に救われた・・という1年でもありましたし、また自分に何かできることが少しでもあれば今度は役に立ちたいと強く思った1年でもありましたね。
志村:あーそうですか・・・具体的には何かなさいましたか?
間:オリンピックに向けて、日本はもう飲食の世界もみんな一生懸命やってきましたよね?それは例えば、牛肉を作るために牛を育てている、そういう生産者もいますけれども、子牛から大人に成長するまでにやっぱり時間がかかりますよね。外国からオリンピックの観客の皆さんがいらっしゃって、それに向けて美味しい牛肉作ろう!育ててあげよう!って頑張ってた人たちが急に延期になって、その牛肉、牛たちはどこへ行くんだろう。本当に行き場を失った高級食材たちや、いろんな大切に育てられた食材、いろんなものが本当に宙に浮いてしまったんですね。
志村:はーそうでしたよね・・・。
間:それを私が知り合いの人から聞いたときに、やはり誰かが何かを動かし始めないといけないなと思ったんです。そこで、生産者、それからお客様にまず喜んでいただくこと、そうして動かすことで私達飲食店がもう少しよくなるような、そういう施策ができないかということで、「三方よし」と、昔から近江商人が言っていた、三方よしって言葉がありますよね?
志村:ありますね、三方よし。
間:あれを私は自分の会社に「これからは三方よしでやるぞ」ということを言いまして、芝浦の精肉業者さん、豊洲の水産業者さん、色々なところに応援している、まあ、僕はアワビを養殖している業者さんも応援してるんですね。そこはやはり障害者の方々が一生懸命アワビを育てているんです。水槽を洗ったり、餌をあげたり、その業者さんを私は3年ぐらい前からずっと応援しているんですけども、その人たちももちろん、とにかく誰かが料理にしてお客様に届けないと回っていかないわけですよね。
志村:うーん、そう思います本当に。
間:それなので、本当に破格値で高級食材を全部入れた破格のコースを作りましてね、もちろん私達の利益は薄いですけれども、まあちゃんと利益も頂戴して、そういうことをやりました。そうしましたら、コロナ禍で飲食店の取り組みっていうようなことで取り上げてくださるメディアもニュースもあって、皆さんの知るところになって、お陰様で随分たくさんのお客様に来ていただくことができて、お肉屋さんも魚屋さんも、いろんな業者さんにも喜んでいただきました。
志村:わぁ・・・お客様も喜ばれてましたよね〜。私Facebookでのシェアをさせていただいたんですけど、
間:いつもありがとうございます。
志村:とんでもございません!で、友人が本当に美味しかった!っていうふうに・・・!
間:よかったです〜。
志村:ね〜、久しぶりだったそうです、やはり家の中で暮らしていてもどうしても自分も疲れてきてしまう?それで今日は何を作ったらいいんだろうっていうふうに、毎日朝昼晩ご飯を自分で作ることはなかった。せめて朝と夜だけだったんだけど昼も、子供たちも家にいるし、旦那さんもいるし、なんかもう毎日・・・
間:大変ですよね〜。
志村:はい、でもそのときにその高級の本当に美味しいお料理をいただいたときに・・・肩こりが楽になったぐらいな深呼吸ができたって言ってました(笑)
間:あ〜そうですか・・・・!
志村:はい。
間:いや、まさに今、季世恵さんがおっしゃった、それがレストランの本来の役目なんですね。
志村:あーそっかー・・・!
間:レストランって語源がレストゥールというフランス語で、それは回復させるとか修復させるっていう意味があるそうなんです。いわゆる車のレストアと一緒ですよね。ですから美味しいものを食べて、皆さんと会話を楽しんで、いろいろな体の疲れだったり、あるいは少し気落ちしてたことが明るくなったり前向きになったり、僕はそれが一番レストランの大切な役割だと思ってるんですね。でもそれが今のお話のように少しでも果たせたのならば、私は嬉しいですね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
志村:レストランって、人を幸せにするけれども、心も元気にするし、私実は最近家族でTERAKOYAさんにお邪魔しました(笑)
間:ありがとうございました(笑)
志村:間さんのレストラン、小金井の方にあるとっても素敵な邸宅の、お庭が広くてそこがレストランになってるんですが、母が重い病にかかっていまして、食事が中々取れないんですね。でも新しいちょっと強い治療を始めなきゃいけないときに、その前日にスタートする前に母を連れてと思いまして、家族と、そして嫁いだ娘の家族とでお邪魔したんですけど、もう食が細くなって食べることが、こう何でしょうね、今日これ食べれたよかった〜って思っていた私達だったんですけど、コースをペロリと完食しました(笑)その喜びが、美味しい〜!っていうふうに言った笑顔と、いただくときのその噛み締めてる喜びの顔が本当にいいんですよね〜。あぁ本当にそれは体の回復と心の回復と幸せいただいたなと思います。本当にレストゥールでした・・・。
間:本当に良かったです・・・私もあのう、召し上がれているかな?って、返ってくるお皿をひと皿ひと皿見てましたけども、綺麗に召し上がられてたので、あ〜良かった〜と思いました・・・。
志村:本当にびっくりしました。でも綺麗に本当に一つ一つのお料理がどれも凝っていらして、器もですけどなんてこんなに宝石のように綺麗に飾られていて、お味も素晴らしくて、で、間のお料理は看板料理はないんだっておっしゃっていましたよね?
間:そうですね、スペシャリテをあえて持たないというふうにはまあ言っておりますけど、やっぱりそれは、いつまででも勉強をしていかなければいけないなと思ってるんですね。これがうちの看板料理、って作ってしまうとそこで成長が止まるような気がいたしまして、ですからあえて自分のスペシャリテを作らずですね、そのときの自分の考えること、美味しいと思うこと、新しいテクニック、まあこういったことがそのときの看板料理になればいいなというふうに思っております。
志村:は〜そうでしたか・・・。創作料理ですよね。
間:そうですね。
志村:はい。なのに、だから本当に斬新で新しくて見た目も綺麗なんだけれども、でも、新しいのに懐かしいんです・・・お味が。あれは何故だったんだろう〜って・・・。
間:料理はやっぱり、急には・・何て言うんですかね、何もないところから急に出てくるものではなくて、やはり伝統もありますし、僕は新しい料理を考えるけれども伝統を否定するというわけではなくて、それこそ初代の祖父の作ってきたものもとても大切にしていますし、新しい方がいいんだ、ということは全然考えてないんですね。ですから、やっぱり食って保守的なものじゃないですか。こう・・・よくイタリアのマンマの味とか、日本でおふくろの味って言いますよね、やっぱり安心できる味、懐かしい味、こういったことを大切にした上で、そして構想、構成していく、作っていくっていうことが大切なのかなと思ってるんですね。最初から最後まで新しいものばかりだとお客様は多分疲れてしまうと思うんです。
志村:あーそうですね〜。
間:でも逆に、伝統的なクラシックなものばかりだと、今度は知的好奇心を満たすことはできない。やっぱり食べて、え?これ何?どうやって作るの?すごいね!って思ってもらうような料理もしっかりコースの中に入れて、できればその一つのコースが、まあ一幕のオペラやですね、劇のような、そういう感覚で召し上がっていただけたら僕は嬉しいなと思ってるんですね。
志村:あーそうでしたか〜・・・!人は本当に食べ物で元気になるんだなってことを改めて知りまして、命は食べ物で生かされてるんだなってことをものすごく感じました。間:いや本当にそうですよね。まあ、もう言い古されたことかもしれませんけれども、有名なブリア=サヴァランの言葉で「君は何を食べてきたか言ってみたまえ。君がどんな人だか言い当てよう」みたいなそんな名言が確かあったと思うんですが、やっぱり人は食べるものでできている。そして、どんなものを好んでどんなものを食べてきたか、それによってその人の人格ですとか、意思というものにもいろんな影響があるんじゃないでしょうかね〜。
志村:あーでも、そうですね、何を食べて・・確かにそうですね、大勢と食べたりとかすることも・・でもところで間さんは、小さい頃は、多分きっとおじいちゃまからもうお父様からも英才教育だったと思うんですけども、どんなものを召し上がっていらっしゃったんですか?
間:いや〜、特別にそんなにすごいものを食べてきたわけではないんですけれども、祖父も父もお酒も好きでしたし、お酒のアテみたいな珍味みたいなものがやっぱり食卓に並ぶんですね。普通ですと子供の食べるもんじゃないって言ってくれないと思うんですけど、祖父も父も少しずつ、いろんなものを食べさせてくれました。
志村:あーそうですか〜。
間:ですからそれこそ、このわたとかね、ああいう物とか、塩辛とか、あまりちっちゃい子が食べないようなものでも、味わって食べなさい、たくさん食べるものじゃないけどもちょっと食べてみてごらんっていう、そういう感覚でしたね。ですので私はすごくそれがよかったなと思っているのは、その味覚の幅というんですかね、あぁこんなものもあって大人は美味しいと思ってるんだとか、あーなるほどこれも美味しいねとか、例えば絵を書くときに、私は料理人になってからですけども、例えば絵を書くときに、12色のクレヨンで書くのか36色のクレヨンで書くのか、やっぱり表現力って違うと思うんですね。でもそれをやっぱり子供のときにいろんなものを食べることで、私は味覚の幅というんですかね、いろんな美味しいものも美味しくないものも、いろんなものをやっぱり口にすることで表現の幅というか、味覚の幅というものをお陰様で訓練してもらったかなぁって今になると思います。
志村:それがきっと今の間さんの明日を作っていらっしゃるわけですね〜。
間:そうですね。
志村:そうですよね〜。今ほら、核家族で、どうしてもお子さんの好きなものを中心に食卓に並べることって多いと思うんですけど、たまにはね、おじいちゃんやおばあちゃんのお料理を召し上がったりすることも大事ですよね〜、お漬物があるとか〜。
間:すごく大切だと思いますね〜。
志村:そうですよね〜
間:う〜ん。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
間:私あのう、味覚の1週間というフランスで始まった、子供たちに味覚の大切さを教えるという味覚の授業というのがあるんですが、日本に入ってきた1年目からもう何年になりますかね〜10年は超えてると思うんです。毎年毎年ボランティアで小学校に行きましてね、2クラスの子供達に2時間教えるんです。で、みんなその今の子供たちってのはながら食いをしてしまったりして、味わうってことに真剣に向き合ってない、そういう環境で物を食べている子が多いんですね。ですから、ちょっとお塩を舐めて、これが塩味だよ、よく考えてよく味わってね、これが砂糖だよ、甘いんだよ、味わってねと、こういうふうにやってくんですね。そうするとやっぱりその授業の後に味わって食べる癖がつくというふうに、まあその後子供たちから手紙をたくさんもらうんですけど、そういうことが書いてありましたね〜。
志村:へ〜・・・大事ですね、そこに集中するってことですものね〜。
間:はい。あるその中の一つなんですけれども、まず鼻をつまんで、果汁のグミを口に入れるんですね。そこから噛んで、じゃあいっせーのーせでみんなつまんだ鼻を離してくださいって言うんです。そうするとその口の中の鼻腔を通じて香りがフワッと上がってきますよね。それでその香りの大切さとか、そこを発見するんですね。
志村:うわ〜すごい面白そう〜〜。
間:ですから私今こうして暗闇の中でお話してますけど、今度は目で見ずに、視覚に頼らずに何かを食べて味覚を味わってみたら、これはこれですごく味覚が鋭敏になったり考えたり、脳が活性するのかなーなんて思ってます(笑)
志村:あ〜いいですね〜。暗闇の中でドリンクを飲むとか、または何かをいただくとかってときに、口に入るってわかんないんです、何が何だか。
間:そうですよね・・・!色も見えないし。
志村:そうなんです。まず手で触って、指先でまず何かが感じるわけですよね。で、そこから口に入れると、あれ?トマトだと思ってたけどブドウだったとか、そこから何かちょっと違ったイメージが湧いてくるんですけど、でも濃く感じるんですね、お味がすごく豊かに。
間:なるほど・・・そうでしょうね〜。視覚情報が全くないわけですからね〜、本当に舌の上でゆっくり味わって、香りを嗅いで、そしてこれは何だろう?どんな味だろう?うーん・・・研ぎ澄まされますね〜これはまた。
志村:本当そうですね〜、シャンパンをグラスに注ぐ音とか、そのときのシュワシュワシュワーの音とかがですね、またすごく音楽のように聞こえてくるんですね〜。あーこんな音が本当はするんだったんだとか・・・
間:確かにね〜。
志村:はい。で、口にグラスをつけようと思ってもちょっとまごついたりとか、そんなこともしながら、その唇に当たったときのグラスの冷たさとか、全てがご馳走に変わっていくんだなーと思うんですけど、そんなことを間さんとご一緒にできたら楽しいですね〜。
間:楽しいですね〜。いやもうぜひやりましょう!
志村:あ〜ありがとうございます。あのう本当に近くに、去年からおやりになっている「SUD」というレストランも幸せなことに近くにあり、基本的にお友達ともお邪魔してるんですけど、あの時間も私にとってはもう、エステに行ってる以上の気持ちよさだと思うんですけど。
間:ありがとうございます〜(笑)
志村:はい〜。
間:もうそう言っていただけるのが、レストラン冥利に尽きますね。
志村:いや〜そうですか〜。でもそれを、今だからこそ感じれるかなと思ったりするんですね。お家でもそういうふうなお時間が取れたらいいなって思ったりしていて、なにか今日ヒントをいただけたらと思うんですけども、例えばお家でお母さんやお父さんがご飯を作るときに、どういう気持ちでお食事を作ると、あ〜あって思わなくても済むのか?なにか秘訣はありますか?
間:私は言葉を添えるのもいいかなと思いますね。「今日はね、こういうところが美味しいと思ってこれ作ってみたんだよ」とかね、「実はちょっと隠し味に何か入れたんだけれども、何だか当ててごらん?」とかね。
志村:あ〜なるほど〜!
間:なにかその、料理に集中できるような、楽しんで食べられるような、そういう一言を添えるだけで、「はいご飯できたよ」「早くさっさと食べなさい」なんて言うんじゃなくて、「今日はあなたが好きだからこれとこれを作ってみたんだ」とか、なんかそんな一言を添えることで、最初の一口目の入り口の部分がだいぶ変わってくるのかな〜なんて、ちょっと思いますね〜。
志村:あ〜大切ですね〜。よく、ついつい母親って急かしてしまったりしがちですね、私も含めて。そうするときに、美味しい?ってこちらで聞くときに、先に言ってよって本当は思ってるんですよね、美味しいって言って欲しいみたいな。
間:あーなるほど(笑)
志村:だけれども、こちらの方から工夫した点とかを言うことができれば、その待つ気持ちよりも先に何か呼びかけがあって、感覚のドアが開きますものね〜。
間:そうですね〜。
志村:あ〜大事ですね〜(笑)
間:やっぱりコミュニケーションって、本当にキャッチボールってよく言うじゃないですか?ですからやっぱり作り手の方からも1つボールを、受け取りやすいボールをポンと投げてあげるっていうのも、すごく重要なことかなと思います。
志村:あーそう思います、レストランでもそうですよね、今日のこれはっていうふうにご説明いただいてフォークとナイフを取る訳ですものね〜。
間:やっぱり説明をすることで、例えば何々さんが一生懸命作ったお米ですとか、何々さんが本当に丹精込めて3年かけて作った何々です。なんていう一言で、同じものでもやっぱり価値が変わってきますし、より味わおうっていう意識がお客様の中にも生まれると思うんですね。家庭でもやっぱりそういうことがあってもいいのかなーなんてちょっと思いましたね。
志村:は〜絶対そうですね〜。
間:だってお母さんもね、お父さんが作るときもありますし、一生懸命美味しく食べてもらおうと思って作ってるわけじゃないですか。そしたらその気持ちをやっぱり一言添えるっていうのは、いいことじゃないかなと思いますね。
志村:そうですね〜。待ってるだけじゃ駄目ですね。
間:そうですね(笑)
志村:はい、一番大事だと思いました、これは本当に学びです、私にも・・・大切にします・・・!あのう、間さんがこれから目指したいこと、例えば今コロナの最中だけれども、なにか思いはありますか?
間:そうですね〜、やっぱりこのコロナはすごく僕は学ばせてもらったなと思いました。そして、コロナって自分と、それから社会との繋がりっていうんですかね、関わりというか、そういうことの大切さや距離感やいろんなことを考えさせられる、そういう時期でしたよね。
志村:うーんそうでしたね。
間:例えば自分の行動一つで感染が広がってしまうかもしれないとか、色々なそうした自分と社会との繋がりっていうものをすごく考えさせられました。その中で、じゃあ料理屋はどうすればいいんだろう?とか、自分自身が持っているもので何かお役に立てることはないかな?とか、そういうことをやっぱりすごく深く深く感じた、考えた1年でしたね。ですから自分ができることを、そして、なんていうんですかね、自分がボランティアでやり続けるということではなくて、みんなも喜んで、社会も良くなって、でもちゃんと自分もちょっとは良くなるような、僕はそんなデザインをなるべくしたいなって思ったんですね。レストランって、皆さんに支持されないと生き残れない商売なんですね。当たり前ですけど。あぁ、TERAKOYAに行ってみようか、あそこなんかいいよねって思ってもらえないと、来ていただけないじゃないですか、レストランって。
志村:そうですね。
間:飲食店ってたくさんありますし、でもその中で一つ選んで、じゃあ今度行ってみようか、やっぱりそこには何かしらの共感であったり親近感であったり、そういうものを感じていただけたら嬉しいなぁと思うんですね。それはやっぱり、ずーっとやり続けてきた自分たちのその行動であったりとか、姿勢なんじゃないかなって本当に考えることがこの1年は多かったですね。
志村:そうですね〜。あのう、私思うんですけど、大切な人と大切な時間を過ごすって、やっぱりレストランが大きな役割になってると思うんですね。といいますのは、私はターミナルケアをずっとしていたのでよくそれを聞いてるんですけれども、例えばある患者さんが若かった頃に、旦那さんと行ったレストランにもう1回行きたいっていうふうにおっしゃるんですね。それでそこにはもう旦那さんはいらっしゃらないんだけれども、私と一緒にお邪魔したんです。で、そこで思い出を本当に幸せに、頰をピンクにして語っていただきながら、もうその方はお食事は細くて召し上がってないんだけれども、でもコースを召し上がっていて、それがね幸せそうなんですよ〜。
間:う〜ん・・・・!
志村:で、そのあとに今度は私以外の人も連れて行って、で、同じ話をずっとするんですって。で、亡くなられているんですけど、そのおばあちゃんが話された思い出を私も含めてみんなが聞いていて、それを繋ぎ合わせるとまた違ったストーリーが出来上がっていくんですね。で、今は、ことあるごとにおばあちゃんのお誕生日のときにそのレストランに集まるんです皆さんが・・・!
間:へ〜〜〜いいですね〜〜〜。
志村:でもそれ実は多いんですよ〜。それはきっと、やっぱり一番思い出って食べることと重なってるんだなと私は思ってるんですね。で、私はなぜ母を連れてTERAKOYAさんに行こうと思ったかっていうと、やがて母は、まあ自分が来るかもしれないときに、私達家族はその場でそれをずっと語り続けていきたいなと思ったんです。それは本当に日本中に、世界中にあると思うんですけれども、でもそういう場が私は飲食店だと思ってるんですね。
間:嬉しいです。まさに・・・!
志村:本当にみんなの思い出なんです。それは結婚式かもしれないし、初めてのデートかもしれないし、思い出が増えていく場なんだなっていうふうに思ってます。でそれが、そういうふうな間さんとまたダイアログがなにかの思い出が作れるとすると、これは本当に私にとって最高の幸せなんですけれども、そういうふうな場を、今コロナで命が本当に大事だって知った私達は忘れてはいけないし、忘れられないと思うんですね。そして行けなかった大好きなレストランやそのお店、カフェに行きたいと思って我慢している私達、皆さん、それをまた行けるぞってときには新しい思い出が増えていくんだろうなと思ってるんです。
間:うーんそうですね〜。
志村:はい、本当に、世界中の飲食店の皆様が今は大変だと思うんだけれども、でもお客様とともにその場を守っていただけたらいいなって思います。
間:そうですね。
志村:はい。あのう最後にね、いつもお招きしたゲストの皆さんにお聞きしてるんです、明日元気でいられるためになにかお言葉をくださいってお願いしてるんですけれども、もしよかったら・・・。
間:明日、元気になるためにですね。
志村:はい。
間:うん、僕は若い料理人たちにも言ってるんですけども、ちっちゃなことで喜べるような、そういうメンタルといいますかね、そういう気持ちでぜひ居て欲しいなと思ってるんですね。ちっちゃなことでいいんです。今日は1分間で10個のものが、なにか皮を剥いたりとかですね、それができた。でも明日は11個できた、そしたらその1個を思い切って喜ぶような、そういう心持ちで居て欲しいなと思うんですね。目の前の小さなことに喜べる自分で居て欲しいなと思いますね。あとは、まあ食いしん坊ですから僕なんかは。明日の朝何食べようかな〜?お昼何食べようかな〜?って、食べることを考えるってやっぱり楽しいことかなと思うので、晩ご飯はワインを一杯飲んであれを食べようか、そんなことを少し思い浮かべて、明日1日を元気に過ごしていただきたいなと思いますね。
志村:いいですね〜。
間:食べることが生きることですから〜〜(笑)
志村:いやぁ、今日はありがとうございました。
間:こちらこそ。
関連記事
-
 101交流・体験
101交流・体験DIALOGUE RADIO
-IN THE DARK -第34回のゲストはコロンえりかさん
-
 104交流・体験
104交流・体験DIALOGUE RADIO
-IN THE DARK -第35回のゲストは小島慶子さん
-
 110交流・体験
110交流・体験DIALOGUE RADIO
-IN THE DARK -第37回のゲストは海音さん(モデル)
-
 112交流・体験
112交流・体験DIALOGUE RADIO
-IN THE DARK -第38回のゲストは菅原聡さん(NPO法人「GLOBE PROJECT」代表)
-
 114交流・体験
114交流・体験DIALOGUE RADIO
-IN THE DARK -第39回のゲストは石橋素さん(Rhizomatiks Research)、森永邦彦さん(ファッションブランド「ANREALAGE」デザイナー)