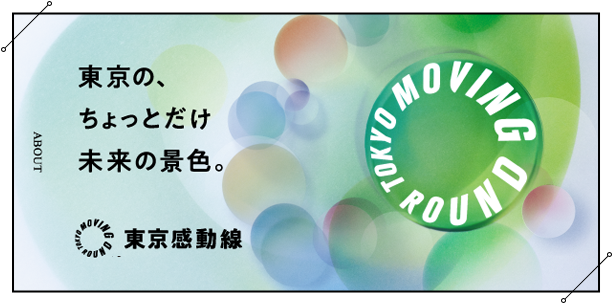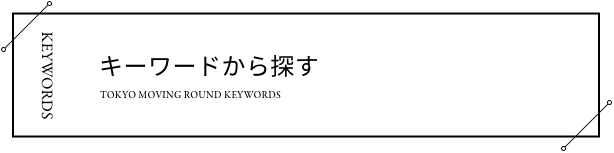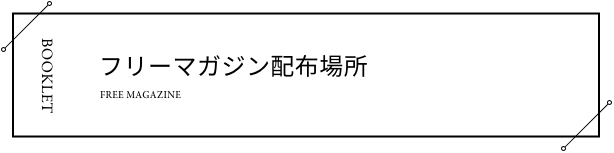- カテゴリ
- 交流・体験
毎月第二日曜日25:00〜26:00 ONAIR
真っ暗闇の中で、心と対話する時間を。
日曜の深夜。全てのしがらみから離れて本当に「独り」になっている特別な時間。人は誰もが不安や悩みを持っているはず。この番組は、自分の心と対話することの大切さを伝え、明日への活力を求める人への応援メッセージを発信するラジオ番組です。
志村:えりかさん、オラ!
コロン:オラ〜!季世恵さん!
志村:明るい挨拶な気持ちになります。
コロン:ふふふふ〜。
志村:先日ですよね、ホワイトハンドコーラスの皆さんがいらしていただいて・・・!
コロン:そうなんですよ〜!ほんっとにもう子供たちからも参加した皆さんからももう感想の嵐で、普段全然お話をしない人も無口な人も、せきを切ったように私にその興奮を伝えてくれました(笑)
志村:嬉しいです。見えないお子さんたちと聞こえないお子さんたちがコーラスをされていらっしゃるんですよね、ご一緒に。
コロン:はい、でその中に目も見えるとか、聞こえない子の兄弟とか、発達障害がある子とか、いろんな子が一緒に何か繋がれる方法はないかなあーということで、ホワイトハンドコーラスでは音楽を使って子供たちがインクルーシブに関わる場所を作っているので、ここにみんなで遠足に、それも対話の森へ遠足に来るのをもうほんっとに行く前から楽しみにしていたし、終わった後も、ものすごいまだ熱が冷めてません・・・!(笑)
志村:それは私達も同じです!ダークのアテンドもサイエンスのアテンドもみんなパワーをいただいてテンション高く今まだ・・・!
コロン:いやー嬉しいですね。コンサートの時に、私ベネズエラでハンドコーラスのコンサートをやったときに、観客の3分の1ぐらいが耳の聞こえない方で、元々その町は耳の聞こえない方がとても多くって、まあ公害の影響があって、その方たちとどういう風に関わっていけるかっていうことでホワイトハンドコーラスが生まれたんですけど。
志村:あーそうだったんですね。
コロン:はい。その背景もあって、観客の3分の1が耳の聞こえない方で、コンサートを見ながら見える音楽っていうか、子供たちが手で白い手袋をして、音楽を表現してるのを真似して、自分たちも一緒に楽しんでくれてるのにすごい感動した経験があったんですけれど、この前もここの対話の大森でサイレンスの私の大好きなアテンドの皆さんが一緒に手で歌ってくださってるのを見たときに、なんか涙が出てきてすっごく嬉しかったです!
志村:いや楽しかったんです。私も実は見よう見まねで手で歌を歌わせてもらったんですけど、手で歌えるんだなあっていう、体中で歌を歌ってる気持ちになって楽しかったですね〜!
コロン:ありがとうございます。あの歌は実は聞こえない子供たちが一生懸命、想像力を働かせながらこの歌詞はどういう絵にしようか?っていうのを考えて、動く絵のような感じで表現しているので、例えば「晴れた空」っていう歌詞であっても、歌う人は晴れた空っていう歌詞しか歌えないんですが、手話で手歌(しゅか)って私達は呼んでいるんですが、手歌で表現するときは、その晴れてるっていうことはその前にきっと雨が降っていた、雨が降っていた後に晴れた空だからきっと虹がかかってるだろう・・・っていうことで、虹の空っていうふうに表現するんですよ。そういうふうに一つの言葉とか一つの文化からまた別の世界にそれを訳すときに、やっぱり心と頭と感情を使わないとできない作業があって、その作業を子供たちとしていると、私元々音楽家なんですけれど、聞こえない子供から音楽についてすっごい大事なことをいっぱい教えてもらってるんですよね。
志村:あーそうなんですね・・・大人になってその能力を生かしてほしいな、いろんなところで。
コロン:そうですね〜。
志村:そんな世の中になってほしい・・・。
コロン:もうすごい子たちなんですよ!
志村:わかります!本当素敵だった〜!もう見えないお子さんと聞こえないお子さんの交流の仕方も素敵だったし、見とれました本当に〜。
コロン:私実はちょっとみんなには言わなかったんですけど、すごいことが実は中で起こっていて、曲をコンサートしたときに曲を一つずつ子供たちが説明したんですけど、「ともだちはいいもんだ」っていう曲があって、「ともだちはいいもんだ めとめでものがいえるんだ」っていう歌詞で始まるんだけど、その歌を全盲の子が解説をして、彼女が目と目で物が言えるっていうのは、私にとったら友達の声を聞いてその友達が元気かなってわかるようなものかなと思って歌ってますっていう解説をして、それを難聴の子が手話通訳というか、彼女が言ってるメッセージを手話で同時に伝えたんですけれど、声で話している子は手話が見えないし、手話で伝えている子は声がどのくらいのスピードなのかとか、いつ始まるのかとか、今何言ってるのかっていうのを全然わからなくて、お互いに全部言いたいことを覚えて、そしてLINEでメッセージを送って、まずその声で話している様子をビデオで送って、口の動きを見ながらそのテンポを耳の聞こえない子が全部学んで、学校帰りに練習して2人で何回も何回もタイミングを合わせてあの日やったんですけど、完璧に始まりも一緒に始まって終わりも一緒に終わって、なんか・・・すごいな・・・!って思いました。
志村:私あれ実はすごくびっくりしたんですよ、この息の合い方はなんなんだろう・・・?と思って・・・あーそんなことがあったんですね〜。
コロン:そうなんですよ。聞こえる人がね手話通訳すると難しいことではないんですけど、やっぱりあの2人が一生懸命伝えたいことのためにお互いが何か手探りの状態であっても、暗闇の中でしっかりお互いの手を見つけて手をぎゅっと握りながら伝えてるっていう感じがして。
志村:そっか〜。
〜コンサートの様子〜
コロン:こんにちは!
子供たち:こんにちは!
コロン:今日はダイアログの皆さん、ありがとうございました!そしてたくさんのお客さんも来て下さいました!私たちは「ホワイトハンドコーラスNIPPON」というグループです!まず子供たちにバトンを渡して、初めの曲の紹介をしてもらおうと思います!ではお願いします。
曲紹介する子供:最初の曲は、作詞 岩谷時子さん、作曲 三木たかしの「ともだちはいいもんだ」です。この曲は、ともだちがどんなに大切なものかを伝えている歌です。どう表示したらともだちが大切なものだと皆さんに伝わるかを考えながら練習しました。また詩の内容もよく考えました。例えば、私は全く目が見えないので、最初は「めとめでものがいえるんだ」というところはよくわかりませんでした。でも私はともだちの声を聞くだけで元気なことや楽しそうなことがわかるので、そのようなことかなと考えました。皆さんの心に大切なともだちのことが浮かんでくるように気持ちを込めて歌います。
志村:すごいなー・・・いや、えりかさんは歌手でもあって、そして駐日ベネズエラ大使の奥様でもいらっしゃいますよね。そしてホワイトハンドコーラスの監督もしていらっしゃる・・・。
コロン:何でも屋さんです。
志村:すごいな〜〜お忙しいですね、そして4人のお母様。
コロン:そうなんです、季世恵さんと同じ!先輩ママでいらっしゃいます。
志村:そうですね〜。いやー、私今日本当にたくさんお伺いしたいことがあって、そもそもえりかさんは、どうして歌を歌おうって思われたんですか?
コロン:私の両親が音楽家で、子供の頃からとても身近にあった音楽だったんですけれど、15歳のときに阪神淡路大震災があって、自宅も全壊になって、私は言葉が話せなくなったですよそのときに。
志村:あ、ということはえりかさんその頃は関西の方にいらしたってことなんですね。
コロン:そうなんです。それで何人かの友人たちと再会して、避難所でなんか歌を歌い始めて、もうピアノも何もないからグレゴリオ聖歌を歌ってたんですね。そしたら聞いてくださる方たちも歌ってる方もお互いになんか涙を流していて、言葉がいらないというか、もう言葉以上のものがその空間に満ちているのがなんか見えた気がして、その瞬間に音楽っていうのは目に見えないものだし触ることもできないしその瞬間瞬間で消えてしまうけれども、見えないけど確かにある力っていうのをすごく自分でも感じて、いや私はこの音楽の力に一生を捧げたい!ってその時に強く思ったっていうのが元体験としてあって、で、本当にいろんなところに出かけるのが私は好きなので、子供たちの前で歌ったり妊婦さんのところで歌ったり、それこそもう命がそんなに長くない末期の方のところで歌ったり、いろんなところで歌うときに、やっぱり言葉が通じなくても年代が違ってもお互いに抱えているものが違っても、なんか音楽があれば人と心で繋がれるんだなっていうのをすごく感じていたんですが、よく言われる「音楽は世界共通の言語」って言われたときに、えーでも耳の聞こえない人はどうなんだろう?っていう疑問がちょっと湧いてきたんですね。で、身近にろうの方もいなかったんですけれど、音楽って全く意味のないものなのかなーとか、一緒に音楽を楽しめる方法ってあるのかなーと。そこから大学で耳の聞こえない人と音楽っていうテーマで論文を書いたんですけれど、なんかね・・・・あるんですよね、いろんなレベルでエネルギーを交換できる方法もあるし、大学で論文を書いて、その後実践っていうのは中々できなかったんですけれど、1995年にベネズエラの「エルシステマ」という、全ての子供が無償で音楽教育を受けられるプログラムがあって、その中に耳の聞こえない子供たちも音楽をできるところがあって、そのプログラムを見たときに、あ、これだ!と思って、これをやりたい!と思って、3年前から日本で「ホワイトハンドコーラス」っていうのをやっています。
志村:あーそうだったんですね・・・!
コロン:はい。
志村:私今すごいと思ったのはね、ご自身が歌を歌ってる時に、「耳が聞こえない人はどうしてるんだろう?」っていうふうに、知り合いがいるわけじゃないの思いを馳せることができるっていうのが、えりかさん素敵だなって思う・・・。
コロン:いやーもう単純な質問だった・・ひねくれてるだけだと思います(笑)世界共通の言語って、本当に?本当に??って疑ってかかって、そこの疑問が出てきたんですけど。
志村:あーでもそう、そういうふうにえりかさんが活動されているその音楽、でも何かそのちょっと歌いましょうって人はいっぱいいるし、歌手になる方も当然おられるんだけれども、社会的なミッションみたいなのってのはどこから生まれてきたんですか?世の中を見ているその眼差しとか・・・どのあたりからそのベネズエラの聞こえない方のことを知ったこともあったのかもしれない、でももっともっと前からあったんじゃないかな?何故ならばCDにも「BRIDGE」ってありましたよね、タイトルが橋だった、その橋という人と人の間を架ける橋は、まあ大使夫人でもあることもあるかもしれない、でももっと前からじゃないかな?と思うんだけれども・・・?
コロン:うーんなんでしょうね、なんか・・・私実は小学4年生の時に日本に来て、ベネズエラで生まれ育ったんですけど日本人の母親がいるし、私は日本だ!日本人でもあるんだぞイェイイェイ!っていう感じでベネズエラでも生きていたので、日本に来るのすごい楽しみにしてたんですよね。で日本に来て最初学校行ったとき、まだ日本語そんなに話せなかったんですけど、周りの子たちが私を指さして走って逃げるので、あ、追いかけっこしたいのかな?と思ってその子たちを追いかけて遊び始めて、で何日か経ってからなんかちょっと違うなと思って、よくよく聞いてみたら、私は目の色が違うので「えりかの目を見たら腐る」って言ってみんな逃げていて、多分初めてその学校にハーフの子が転校してきて周りもどうしていいのかわからないし、私もなんか日本語を話せないのに私日本人イェイイェイ!って感じで入っていったので、すごいいじめがあったんですね。そのいじめが結構命の危険のラインまであって、救急車で弟も脊髄にひびが入るまで殴られたりとかで運ばれたりとか、まあ洋服に火をつけられるとかなんかそういうことがあったので、もうとにかくその場所を乗り切るためには、私にはいろいろ選択肢があっただろうけれど、私がそのときにこれしかないって思ったのは、もう完全に日本人になるしかないっていう気持ちで、みんなと同じにならなきゃいけないっていうのがすごくあって、大学時代まで本当に名前も話すことも何でも「すいません、すいません、いや、恐縮です」とか、なんかそういういろんな方法で、ラテンだった自分を消して日本人として生きるぞっていうのをすごい頑張ったんですよ。でもどんなに頑張ってもなんかちょっとどうしても到達できなかったところがあって、まあやっぱり見た目は変えられないし、どんなに中身を日本人にしたと思っていてもいやもうここまで頑張ったけど無理だったわーっていうのに22歳ぐらいで気がついて、もう開き直ることにしたんですね。
志村:そっか・・・。
コロン:そうなんですよ。でもそのときに、なんかやっぱり人の心の中で相手と違うとかっていうことに対して見えない壁が世の中にはすごくいっぱいあって、まあ今このコロナの問題はすごくみんなに困難な状況を与えてもいるんですけれども、一方でみんなが共通で持ってる問題っていうのを世界中が与えられたことによって、なんかみんなで一緒に乗り越える頼もしさとか、一緒にできるんだっていう、協力できるんだっていう、そういう喜びも経験できるすごい大きなチャンスかなと思っていて。CDの収録があったときは、まだ実はコロナのことは誰も想像していなくて、ベネズエラでも政治的な分断とか、私が日本で経験した、まだその多様性っていうことを受け入れるのがしんどいそこの分断とか、まあいろんな分断がある中で、どうやったらこの分断を乗り越えられるんだろう、向こう側に行けるんだろうって言ったときに、やっぱり私にとってそれが音楽であって、どんなに政治的に考えが合わない人でも、なんか音楽を聞いてる間は古里に、お互いの古里を思いながら浸れるとか、音楽がいろんなそういう分断を超える橋だなと思って、それを私は目指したいと思って音楽家になったので、そのCDには「BRIDGE」って願いを込めて付けました。
志村:そっか分断を・・・・ね、分断に橋を架ける・・・・。
志村:そうなんか・・私なんか涙出てきちゃった。
コロン:いやーすごい、私が初めて季世恵さんを泣かせた、いつも泣くのは私の方ばかりですが(笑)
志村:いやー今暗闇だからいいけど、大分ひどい顔になってますよ、どうしよう・・でもそうだったんだね〜・・・。
コロン:いや暗闇危険ですね、なんかいろいろ喋っちゃう・・・(笑)
志村:本当にね、暗闇ちょっと魔法がかかってますからね〜。
コロン:本当に〜。
志村:いやーでも大切なお話をしてくださってありがとうございます。きっとこのラジオを聞いてくださってる方たちの中には同じような痛みを持ってる人もいると思うんですね、分断によって傷ついてる人たちって、やっぱりいろんな分断があるから、今のお話はきっと心に染み入ってると思うなー・・・。22歳でラテンに戻ったんですねきっと。
コロン:はい、もう諦めました(笑)
志村:うーん、諦めると、受け入れちゃうと、そこからまた新しいドアが開いたりしますよね。
コロン:そうですね〜。本当諦めるのって大事ですね、そう言われれば(笑)
志村:うーんわかる気がする。私もそうだったよ。
コロン:え、どんなことがあったんですか?季世恵さんは。
志村:あ、私はね、家庭内に分断があって、母が違う兄妹と一緒に暮らしてたんだけど、お母さんが違うっていう分断がすごく大きくて、まあDV的なことがあったんですね、おでこを陥没骨折しちゃうとかね。でなんかどうしても受け入れて欲しくて、姉たちに、どうして愛してもらえないのかな?と聞いたのね、そうしたら「お母さんが違うから無理だ」って言われたときに、血縁というものがそれだけ分断の元になるのかと思ったときに、これはもしかすると民族もそうかもしれないって思ったりして、私の場合はね、結構長く時間がかかったんだけど、お姉ちゃんたちが死ぬ頃までに「季世恵と兄妹で良かった」って思うまでは、まいっかと思って諦めたというか、なんか無理して何とかしようと思わなくてもいいやって思ったら、ドアが開いた感じになったの。
コロン:あーーーそうなんですね・・・。
志村:だから私の場合は家庭内だから、もうえりかさんとは全然比べ物にならないけれども、でもそこになんかちょっと受け入れるというか、諦めと違う受け入れなのかな、なんかまいっかみたいな。
コロン:そうですよねーーー。いやこの間もテレビで歌うことがあって、普段心掛けてることは何ですか?って聞かれて「まいっかって思うことです」って言ったら「まいっかの歌姫」ってタイトルが出てちょっと焦ったんですけど(笑)
志村:素敵だ(笑)
コロン:本当にね〜、なんか「まいっか」が中々日本ってみんなすごい頑張っちゃうから、電車も時間通りにつくし〜。
志村:本当だよね〜。それはもう全てがそうですね、丁寧にきっちりと守られて、そして私たちは暮らしていけることができるんだけど、なのでベネズエラの皆さんは来なかったらまいっかと思ってお家に帰るんでしょうね。
コロン:そうですね〜、そうもう今日は無理だったーっていう感じで、なんかもちろん時間を守るとか、ね、並大抵の努力ではできないことなので頭が下がる一方なんですけど、その傍らやっぱり私達はこの自然の中で生きていて、自然の摂理から逃げることはできなくて、体の中にも時計が入ってて早く進むときもあればゆっくり心臓が波打つときもあるし、なんかそこのところで自分のあり方っていうのに心地よく居れるっていうのは決して怠けることとかではなくて、なんかその生きてる時間をちゃんと自分で味わって食べるっていう、すごい大事なことなんじゃないかなって最近なんかすごい思いますね。
志村:丁寧になるものね。感じることができて。
コロン:いやー大事なことって本当シンプルなことなんですね〜。
志村:そう思います。私ね、もう1個だけお聞きしたいことがあって、マリア様の歌を歌っていらっしゃるじゃないですか。
コロン:はい。
志村:あの歌を聞いたときに、私また涙がポロポロこぼれて、で、その歌の理由を聞いたらあーそういうことだったのか・・と思ったんですね。そのお話を教えていただいてもいいですか?
コロン:はい、ありがとうございます・・!いやその曲実は私の心の一番奥にある一番大事な曲なので、聞いてくださって嬉しいです。
「被爆のマリア像」というマリア像が長崎にあって、浦上天主堂っていう爆心地から500 mしか離れていない、当時はアジアで一番大きな天主堂で、隠れキリシタンの時代から長い歴史を経てやっと信仰の自由を得られた明治時代になってから信者さんたちが30年かけてみんな貧しい中からレンガ一つずつを持ち出して、30年かけて建てた教会に捧げられた守護聖人が「無原罪のマリア像」という、罪のないマリア様の象徴としてそのマリア像に捧げられていて、当時長崎にいたスペイン大使のウリバリ大使という方がおそらくそれをスペインから取り寄せて浦上天主堂に寄贈して、天主堂の中の一番大事なところにそのマリア像を置いたんですが、8月9日の原爆によって浦上天主堂が倒壊して、当時1200人いた信者さんたちの内の850人、だから本当に多くの方が原爆で亡くなって、その中の信者さんの1人に14歳のときに”トラピスト”って言って、もう人と完全に関わりを絶つ修道院に入った野口嘉右衛門さんという方がいて、その野口嘉右衛門さんはトラピストの修道院、北海道に行ってから兵役で徴兵されて、朝鮮半島の方に渡って終戦と同時に自分の故郷であった長崎が大変なことになってるらしいっていうことで北海道の修道院に戻る前に長崎に立ち寄ったら、その浦上天主堂の、自分が祈ってきた場所がもう瓦礫になってることにもう呆然と座り込んだんですよね。
そうしたら目の前に、自分がずーっと祈ってきたマリア像の頭の部分だけが転がっていて、マリア像がこっちを見てたっていうことで、神父が大事に北海道に持ち帰って30年経ってから浦上天主堂に戻ってきて、そして2001年に浦上天主堂を出発して、ミンスクという、チェルノブイリの事故があった町に被爆のマリア像を持って行って向こうで祈りを捧げるという、同じ放射能の苦しみを受けた方々と祈りを捧げるっていうことで出発する日に、たまたま私、バックパックで野宿しながら長崎を回っていて、そのマリア像の周りに人集りができているのを見て、え、なんだろう?って覗いて見た時に、そのマリア像が今まで私が見てきた、綺麗な白い肌で光るような宝石のような目が入っていて、綺麗な乙女のイメージのマリア像とは全く違った、もう頰は黒く焦げて目の中も空洞で、すごく痛ましいマリア像にすごくショックを受けたんですよね。
で、そのショックを受けてそれが上手く自分の中で消化できなかったんですけれど、原爆資料館にその後行って、そこに被爆したカシの木っていうのが置いてあって、カシの木の幹の部分が露わに展示されてるんですが、中にガラスの破片がいっぱい入ってるんですよ。
で、どうして木の幹の真ん中にガラスの破片が入ってるんだろう?と思って説明を見てみると、そのカシの木は原爆の爆心地の近くに生えていたまだ幼い細い木で、そこに四方八方からガラスの破片が飛んでそれが幹に刺さって、なのにその後ずっと生き続けて、1年1年年輪を重ねるごとにガラスの破片を全部包み込んで、中に抱擁していきながら成長し続けたカシの木で、そのカシの木が、まあその被爆者の方の話とかこのマリア像にすごくそこでなんかビビーっと繋がって、なんかやっぱり人間、その戦争の体験もそうだと思いますし、自然災害とか、いろんなその痛みっていうのはそのカシの木のガラスの破片のように中にあって、それを取り除くこともできない、ずーっと中にあるものだけれども、生きているっていうだけで自分の気がつかない間に人間も木のように年輪が少しずつ重なっていって、それこそがなんかすごい希望だなっていうのを感じて、この世の中から戦争も終わらないし貧困の問題もまだ解決しないし、人の痛みっていうのはもしかしたらずーっと人間は抱えていかなければいけないかもしれないけれど、まずはそれを生きてきた人たちの力強さとか希望っていうのにすごく励まされたような気がして、この被爆のマリアに捧げるアヴェマリアという形で父が作曲してくれて、その後からずっといろんなところに行っては、海外に行くときも必ずこの曲を歌って、まあ平和への祈りっていうことなんですけれども、平和っていうのは多分国同士の問題だけではなくて、自分の心の中の平和っていうこともあるし、それをなんか私は本当に被爆者の方たちからすごく教えていただいたので、せめてこの拙い歌で、またそれを次の方に伝えていけたらいいなあと思って歌い続けてます。
志村:あーそうだったんですね・・・・・とっても大切なことですね、本当に・・・・・。
コロン:そうですね。
志村:うん・・・・。
志村:いやー、大切なお話をお聞きできてよかった・・・・。
コロン:いやありがとうございます、こちらこそ。
志村:そうなんです、そのガラスを内包しながらもね、育っていくっていうのは、とてもすごいことだなと思います。何もなくて育つのもいいと思うけど、でも痛みを内包しながらね、育っていくっていうのは勇気になりますよね。
コロン:そうですね。
志村:私たちみんなの。
コロン:本当に、そうだと思います。
志村:うーん、そう・・・・本当に。あのね、もうそろそろ終わりの時間になっちゃうんだけれども、いつもここに来てくださったゲストの方々にお聞きしてるんです。今、夜中の1時、もう少しで2時になるけれども、明日、まあ本当は今日だけだね、朝、今よりも元気な気持ちで迎える、そんな言葉をいただいてるんですね。
コロン:はい、えっとじゃあ、ベネズエラでよく言うフレーズをお送りしようかな。
志村:ぜひ教えてください。
コロン:あのう、「まいっか」っていう話が出てきたんですけど、ベネズエラ人は物事を約束するときに、最後に「シ ディオス キエーラ(Si Dios quiere)」って言うんですね。
志村: シ ディオス キエーラ?
コロン:Si Dios quiere!意味は「神様がそれを望んでくれたらね」っていう感じで、例えば明日3時に駅で待ち合わせねって言ったら、神様がそう望めばねって言うんですよ(笑)
志村:へ〜!
コロン:で、なんかなんとも不安になる感じだと思うんですけど、ちゃんとそれで集まれるので大丈夫ですけど、自分のコントロールの効かない出来事?でも何かに守られていて、いつも自分だけじゃないんだって思ってるベネズエラ人のこの「Si Dios quiere」っていうのは、まいっか、もしできなかったらまあしょうがないね、まいっか。でももしできたら、あーよかったねって、神様もそれを望んでくれてたんだねっていうラテンの・・(笑)
志村:うーん素敵〜!
コロン:Si Dios quiere!言ってみてください皆さんも(笑)
志村:いいな〜!すごい素敵な魔法の言葉いただきました。私はね、いつも元気欲しい時は、えりかさんのCDの「ア・エ・ミ・バナナ」の歌を聞いてるよ!
コロン:あははは〜!ね、あのう何の意味もないけどとにかく明るい歌で、この前もね、手歌(しゅか)で指文字をつけてみんなで歌っていただいたんですけれど、あの歌は1回聞くと忘れられなくなるので。
志村:そう、もうねずっと頭の中にラテンがずっと残ってて、朝すごい元気に目が覚めます。そして、今の魔法の言葉が入れば、もう元気ですね。
コロン:いい日になりますように・・!
志村:いい日になります・・!よかった〜、ありがとうございます〜!
コロン:ありがとうございました〜!
志村:またいらしてください。
コロン:はい、ありがとうございます!
志村:ありがとうございました。
関連記事
-
 104交流・体験
104交流・体験DIALOGUE RADIO
-IN THE DARK -第35回のゲストは小島慶子さん
-
 107交流・体験
107交流・体験DIALOGUE RADIO
-IN THE DARK -第36回のゲストは間光男さん
-
 110交流・体験
110交流・体験DIALOGUE RADIO
-IN THE DARK -第37回のゲストは海音さん(モデル)
-
 112交流・体験
112交流・体験DIALOGUE RADIO
-IN THE DARK -第38回のゲストは菅原聡さん(NPO法人「GLOBE PROJECT」代表)
-
 114交流・体験
114交流・体験DIALOGUE RADIO
-IN THE DARK -第39回のゲストは石橋素さん(Rhizomatiks Research)、森永邦彦さん(ファッションブランド「ANREALAGE」デザイナー)