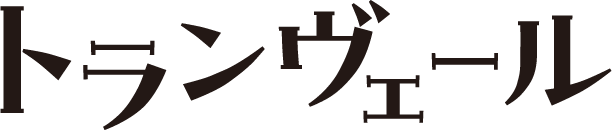2020年 12月号 特集
嘘か真か。歴史を秘めた
北陸刀剣譚の旅
鎌倉末期頃から北陸は刀剣の産地だった。その一帯で生産された刀剣は総じて「北国物(ほっこくもの)」と呼ばれる。室町時代以降には朝倉氏や前田氏によって、優れた刀工が作った刀剣がもたらされた。刀剣に秘められた数々の史実や伝説を追って、北陸を巡る旅に出る。
ご当地刀剣「北国物」
に会いに行く

時代劇研究家として役者や監督などを研究してきた春日太一さんが、日本有数の刀剣コレクションを所蔵する富山県の「秋水美術館」を探訪する。本物の刀とじっくり向き合うのは今回が初めてという春日さんを、時代劇好きという学芸員の澤田雅志さんがガイドしてくれた。日本刀は武器であると同時に、芸術的な価値も高い美術品。鎌倉時代には形がほぼ完成しており、その頃からすでに美術品として扱われていたといわれている。

秋水美術館の見どころの一つに、ご当地刀剣の展示がある。富山県・福井県・石川県で生まれた刀は総じて 「北国物(ほっこくもの)」と呼ばれているが、中でも富山の刀剣製作の歴史は古く、鎌倉時代から、則重(のりしげ)や郷義弘(ごうのよしひろ)といった優れた刀工が活躍していたといわれる。また宇多派(うだは)と呼ばれる人々が、則重や郷の作風も取り入れて、多彩な刀を生み出した。写真は則重が手掛けた一振り。

日本で三本の指に入るという伝説の刀工、郷義弘の刀を見せてもらう。春日さんは恐る恐る、まずは右手で柄(つか)を持ち、刀の形を鑑賞する。さらに、布を添えた左手で刀身を支えて横に寝かせ、光にかざしてじっくりと刀を鑑賞する。「おおっ!刃文がすごい!リズミカルに山が連なっているみたいです。光が雲みたいにもくもく動いたり、稲妻みたいにピカッと輝いたり……。光の当て方で見え方が変わっていく」。妖しい刀の美しさに、春日さんはすっかり魅せられたようだ。