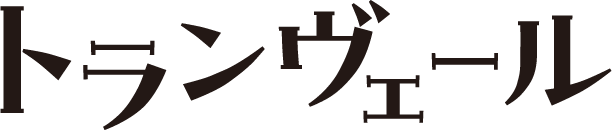遠野物語と賢治が語る、山の怪

著者の田中さんが『山怪』の原点と話す『遠野物語』は、民俗学者の柳田國男が岩手県遠野地方に暮らしていた佐々木喜善の話を聞き取って編纂し、明治43年に発表したもの。山の里に伝わる、妖怪や神様に遭遇したという奇妙な逸話の数々は評判となり、増補版『遠野物語拾遺』も出版された。その舞台を訪ねる旅を紹介する。

『遠野物語拾遺』に、旗屋の縫という人物が登場する。一つ目一本足の怪物を退治したり、青入道と知恵比べをしたりと、三面六臂の活躍を見せる伝説の猟師である。そのゆかりの地が、畑屋観音堂だ。棟札によると鉱山事故の死者の慰霊に建立されたもので、縫は実在の人物だったらしい。畑屋観音堂の傍らには山の神が祀られていた。山に潜む見えざるものを信じる心が、まだ遠野には残っているようだ。

遠野の綾織町の山中に、『遠野物語』に登場する続石という巨石がある。ある日、鳥御前という鷹匠が続石のそばで山男と山女に遭遇する。からかってやろうと挑みかかるそぶりをしたが、山男に蹴り飛ばされて意識を失う。その後、助けられるも病んで死んでしまった。これは、続石を依り代にしていた山の神の遊びを邪魔したからだという。「伝承の山の神は、顔が赤くて目が爛々と輝き、背の高い男です」と遠野市立博物館の前川さおりさんは語る。

山の不思議に触れる旅の最後に訪れたのは、岩手県花巻市の宮沢賢治記念館。代表作の一つ『注文の多い料理店』は山の不思議に彩られている。表題作の「山猫軒」はマヨイガのように山の木々の中に忽然と現れる料理店。「山男の四月」の山男は、目が金色の大男だ。『遠野物語』で話を収集した佐々木喜善と同じく、賢治も土地の伝承を聞いて育った。「ありもしない設定で、読者を異空間に引きずり込む。それが賢治の物語世界の不思議であり、魅力です」と学芸員の牛崎敏哉さんは語る。