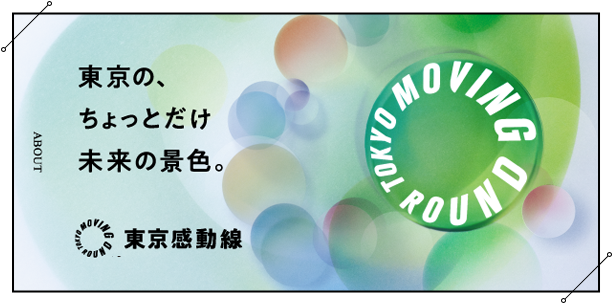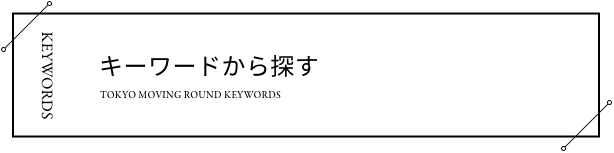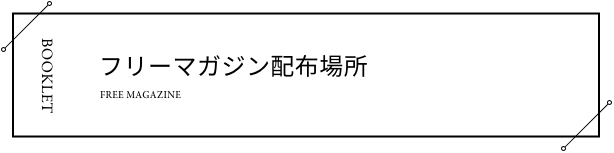- カテゴリ
- 交流・体験
「Slow Neighborhood」のプロジェクトの一環として、地方と都市が食を通じてつながり、生産者の思いまで味わう「Slow Neighborhood DINING」が行われました。2021年9月から約2か月間にわたったこの取り組みでは、JR東日本の新幹線を物流として活用し、新潟・佐渡でとれた食材を東京・新大久保にある「K,D,C,,,」(キムチ,ドリアン,カルダモン,,,)に届けて東京の料理人が調理し提供するという、新しいスタイルの地方と都市のつながり方を探りました。Slow Neighborhood DININGに携わった佐渡相田ライスファーミングの相田忠明さん、フレンチシェフのシイナケンジさんにお話をうかがいました。
佐渡から東京へ、ご近所さんにおすそわけをするように
──Slow Neighborhood DININGでは、相田さんが送った食材でシイナさんが料理をつくりました。生産者と料理人というそれぞれの立場で感じたことや気づいたことを教えてください。
相田:佐渡からSlow Neighborhood DININGに届けた食材は、市場流通にのるようなものでなく、地元の農家の方が家で食べるためにつくっていたり、自給自足で畑をやっているみなさんがつくっていたりするものでした。
佐渡の人たちが日々食べている「普段着の食材」といったらわかりやすいでしょうか。私の母もそうなのですが、自分の家で食べるだけでなく、ご近所さんにたっぷりとわけられるくらい旬の食材をつくっているんです。今回の取り組みは、佐渡と東京といったように距離は離れていても、私たちが地元で当たり前にしている物々交換のやりとりの発展形なのかなという気がしています。
シイナ:本当にそうですね。地方出身の料理人と話していたとき、「この野菜、東京では買わなくてはならないけれど、うちの地元はたくさん取れすぎて持て余すこともあるんです」と言っていてうらやましいなと思ったことがあったんですが、「今日はこの野菜がたくさんとれたから」と佐渡から届く食材を受け取るたびに、なんだか現地の暮らしを疑似体験しているような気分になりました。
東京で行われる物産展や地方の食材を使ったイベントとなると、だいたいが特級品ばかりが集まりますよね。それはそれで魅力的ですが、Slow Neighborhood DININGには相田さんがおっしゃるように「普段着の食材」ばかりで。そういった意味では、従来の地方フェアとはまったく違う印象を受けましたし、僕自身も新たなアプローチで料理に取り組めたのかなと思います。
相田:新幹線を物流として使ったことで、朝に収穫したものをその日の昼には届けることができるスピード感もすごく興味深かったです。またなによりも、シイナさんだったり、Slow Neighborhood DININGに来てくださるお客さんだったりと、私たちの食材が届くのを待ってくださっているみなさんのことを、離れていても間近に感じました。
シイナ:いつもの料理の仕事なら、来週のメニューはこれにしようと決めて、それに必要な食材を業者さんに発注し、届いたら仕込みをしてというサイクルでやっています。でも、今回は自分の手元に来るまで、どんな食材が届くのかがわからなかったんです。届いたものを見てからメニューを決めていって。はじめのうちはどうしようかと思っていたのですが、それぞれの食材のピーク時のおいしさだったり、野菜の持つ本来の味わいだったりと、そういったものを堪能できるギフトセットのように感じて、届くのがいつも楽しみでした。
【最初の画像】
上/シイナケンジさんと佐渡の生産者のみなさん。
下/佐渡に広がる田園風景。
【画像1】
相田忠明さん。佐渡相田ライスファーミングでは環境に配慮した農業を行っています。
生産地のありのままの様子を体感することで気づくこと
──佐渡から届いた食材を、シイナさんはどんなふうに感じましたか?
シイナ:Slow Neighborhood DININGは、秋にさしかかろうとする9月から始まりましたが、夏の盛りにしかできないと思っていたオクラやピーマンがたくさん届いたことがありました。食べてみると、本当に味が良いのです。
自分のもとに届いた佐渡の食材に毎日のように触れるうち、“はしり”や旬といった食の業界の一般常識はあくまでも目安であって、今まではそれに捉われすぎていたような気もして。それよりも、たった今、自分の手が触れている素材の持ち味をどうやって生かしていこうかと、そこを考えることがいちばん大切なんだと感じました。
──市場に流通させるものではなく、Slow Neighborhood DININGならではの食材のセレクトもあったのでしょうか?
相田:ニンジンやダイコンといった野菜は、通常ですと葉を切り落として出荷することがほとんどで、東京の店先で葉付きのものを見る機会はそう多くないと思います。でも本当は、葉の部分もすごくおいしいんですよ。佐渡ではお味噌汁に入れたり、漬物にしたり、炒めたりして、まるごと食べるんです。葉はすぐに傷んでしまうこともあって市場にはなかなか出せないんですが、今回は鮮度のあるうちにスピーディーに新幹線で届けられるとあって、あえて葉付きのものをお届けしました。
それから、栗ならイガが、柿は葉っぱが付いたものにしたり、お米は稲穂もお送りしたりと、ありのままの食材の様子を少しでもお伝えすることで、生産地と都市部の空気が混ざり合えばと思っていました。
──佐渡のみなさんが日常的に見たり、触れたりしているものまでシイナさんに届けたのですね。
相田:たしかにそこは意識していたところではありますが、それだけではないんです。今回の取り組みが始まるとき、協力してくれる地元のお母さんたちの畑に行ってみたら、実にたくさんの種類の野菜をつくっていたんですね。本やテレビで見て気になっためずらしい野菜の種や苗を仕入れて試しに植えてみたら育ってしまったとか、そういう何気ない感じでつくっていて。例えば、バジルやローリエをつくってパスタに入れてみたけれど一度しか使わなかったとか、「うちのお父さん、ハーブは苦手で食べないのよ」とか、つくってはみたもののうまく使いこなせなかった食材も、シイナさんのようなプロのフレンチの料理人の方に喜んでいただけて、生産者の方もすごく嬉しかったみたいです。
──シイナさんは佐渡から届いた食材から、新しいイメージやなにかを受け取った感覚はありますか?
シイナ:大いにあります。オクラだったらトゲがたくさんついていたり、ピーマンは実が厚くてツヤやハリがあったりと、どれも生き生きとしていて野菜本来の姿はこうなんだと伝わってくるかのようでした。苦みやえぐみも、それこそがその野菜が持つありのままの特性であり、だから水にさらしてアクを抜かなきゃいけないとか、そうした手間の一つひとつの意味を再発見するような感じでした。
食材がつまった箱のなかには見たことのないような山菜だったり、めずらしい葉物だったりが入っていて。扱い方を細かく書いたメモを入れてくださっていたこともありましたが、どんなメニューにしようかと、すごく想像をかきたてられました。
相田:お送りした食材について「どうやって使えばいいのか思いつかない」みたいな反応が料理人の方から返ってきたとき、地元の人たちから「佐渡ではこうやって使っているんだよ」と、佐渡ならではのレシピをおすそわけするようなことができても面白いですよね。きっと地元のお母さんたちは「東京の人がこんな料理を喜ぶのかしら」「たいしたことないものなのに」なんて恥ずかしがると思うんですけれど、料理人のみなさんの心に響く可能性もあるのかな、と。
シイナ:佐渡の日々の営みから生まれたレシピというわけですね、それはぜひ教えてほしいです。私たち料理人は仕事として毎日料理をしていますけれど、そうじゃなくて、農家の人がその日の農作業を終えたあとにつくる夕ごはんとか、漁師さんが朝、漁に出る前につくる朝ごはんとか、日常生活のなかで地元の食材をどんなふうに調理するのか、きっとそこには合理性やおいしくする秘訣が絶対にあるはずなんです。佐渡の食の実用編といいますか、そういうこともうかがいながら、送っていただいた食材でメニューをつくってみたいです。
【画像2】
Slow Neighborhood DININGでのシイナさん。
ひとつの取り組みから、未来につながっていく絆
──「Slow Neighborhood DINING」での食材や料理を通じて、人と人の交流も生まれているのではないでしょうか?
シイナ:今となっては野菜を送ってくださったみなさんを自分の親戚のように感じるんです。東京から佐渡は3時間くらいでしょうか、遠いなと思うんですけれど、でも、その距離を新幹線に乗って東京にやって来た食材を扱うたび、これをつくったみなさんに会ってみたくなる、そうした特別な気持ちになれる企画でした。佐渡の食材だけでなく、人にも触れることができたような、そんな気がしています。
Slow Neighborhood DININGがご縁でイベントが終わってからも交流は続けさせてもらっていて、僕が佐渡を訪れて地元の食材を使った料理の試食会をしたんです。佐渡に来ると、なんだか里帰りしたような心境になってしまいました。
相田:僕自身もそうですし、シイナさんの試食会に来てくれた佐渡のお母さんたちも、住んでいる集落が好きとか、自分の畑が好きとか、みんな本当に佐渡が大好きなんです。純粋に佐渡にいたいから、ずっとここで暮らしているんです。でも、世の中は広いんだし、せっかくつながるチャンスがあるのなら、それを感じてみるのもいいんじゃないかと思っているんです。例えば、試食会でもシイナさんのお料理をいただくことで、ちょっと都会の風をまとったような気持ちになれたりして。佐渡にいながら都会を旅できたような、そんな不思議な心地です。
Slow Neighborhood DININGを振り返ってみると、いい意味でのギブアンドテイクがしっかりとできているような、そうした雰囲気があるなと思いました。ないものねだりではなく、対価があってものをやりとりするのでもなく、互いが持っているものをしっかりと出し合うからこそ、これまでにないかたちで人と人がつながることができたり、生まれた価値があったのではないかと感じているんです。
【画像3】
上/Slow Neighborhood DININGで料理を振る舞うシイナさん。
下/2021年12月、佐渡で行われた試食会の様子。