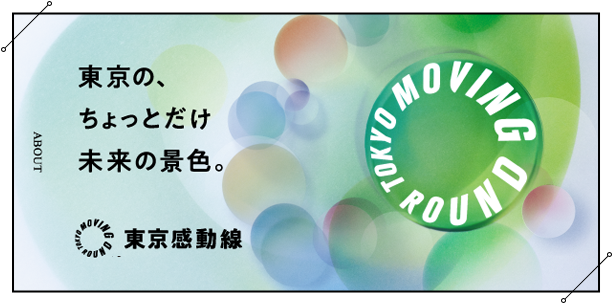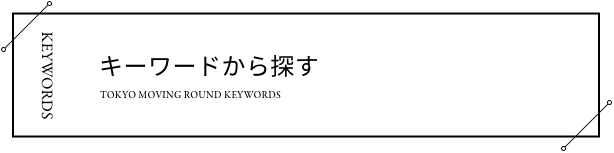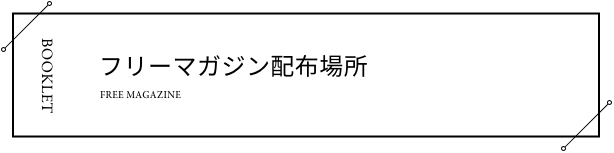- カテゴリ
- 交流・体験
2021年10月31日まで開催されたSlow Neighborhood DININGでは、食文化を通して東京と地方の暮らしがつながるさまざまなイベントが行われました。10月17日(日)、新潟県佐渡・真野地区にある老舗蔵元の尾畑酒造をゲストに招き、「佐渡島・学校蔵の出前授業」を開催。尾畑酒造が廃校となった小学校の校舎を活用して2014年に立ち上げた「学校蔵」は、お酒を軸とした交流事業や体験プログラムを行うなど、国内のみならず海外からも注目を集めてきたほか、2020年には内閣府の「日本酒特区」第1号として認定。酒造りという伝統産業によって佐渡を盛り上げています。尾畑酒造の5代目として家業を継ぎ、現在は専務取締役を務める尾畑留美子さんにお話をうかがいました。
場所や人がひらめきを与えてくれる
──学校蔵が生まれたきっかけを教えてください。
尾畑:学校蔵というのは、2010年に廃校となった旧西三川小学校を尾畑酒造のふたつめの酒蔵として再生した場所です。佐渡の西岸にある真野湾を見渡す高台に建つ木造校舎で、もともとは「日本でいちばん夕日がきれいな小学校」とうたわれるくらい地域の象徴的なスポットでした。地域のコミュニティの中心にある場所がなくなってしまうことが残念で、この景観を守りたいという思いから酒造りの場所として再生することに決めたのです。もっともその過程では、廃校を酒蔵にするという構想が無茶に思えたこともあったのですが、実際に学校が立つ高台から佐渡の海を眺めた際に迷いが消えて「やらねばならぬ」と覚悟が決まりました。
そうして2014年から、「酒造り」に加えて「環境」「交流」「学び」という4つを柱に据え、運営をスタート。具体的な活動としては、夏場に冬の環境を作ってお酒造りを行うほかに、お酒を学びたいという人を受け入れる「1週間酒造り体験プログラム」や、〈佐渡島から考える島国ニッポンの未来〉を大テーマに据えたワークショップ「学校蔵の特別授業」などを行っています。学校蔵には「幸醸心(こうじょうしん)」という校訓があり、酒造りを通して地域や人に幸せを醸していきたいと思っています。
──酒造りだけでなく、外と広く関わっていくような活動も積極的に展開しています。そういった活動からどんなものが生まれているのでしょう?
尾畑:例えば「学校蔵の特別授業」では、島の高校生から70代の方まで幅広い年齢層の方が参加してくださっています。佐渡の人だけでなく島外、県外、時には海外からの参加者もいて、混ざって学ぶのがポイントです。年代もバックグラウンドも異なる人たちが同じテーマについて授業という場で一緒に考えることで、参加者のみなさんそれぞれに“化学反応”が生まれます。化学反応で気づきを得て、発想が転換する。発想が変われば、アクションが変わります。アクションが変われば、未来が変わる。「学校蔵の特別授業」は小さな授業ですが、未来を変える授業だと位置づけています。
そんな化学反応が生まれるのも、「リアルな学校の教室」だからこそではないかと感じています。「場」の持つ力って大きいですよね。授業というスタイルも、学校という場所からヒントをもらったんです。学校蔵に限りませんが、何事も自分の頭の中から生まれたアイデアだけで決めているわけではなく、もともとそこにある資源だったり、出会う人だったり、そうしたものからインスピレーションを得て進むべき方向性に導かれるということが多いと思うのです。
だからこそ、どこかに出かけたり、誰かと出会ったりといったことはすごく大切ですし、時として人の人生を変えてしまうこともあると思っています。
──Slow Neighborhoodも、自分の知らない世界への扉を開けて新たな世界とつながることを大切にしています。
尾畑:もともと日本の社会はご近所づきあいがとても密だったけれど、核家族化が進むうちにそれも失われていきました。でも、コロナ禍を経て、誰もが人とつながることの尊さをあらためて実感しました。私たちが旧西三川小学校と出会って学校蔵が生まれたように、誰かとつながることで、新しい展開がはじまった人もいらっしゃるのではないでしょうか。お酒とお料理の組み合わせ次第で新しい味わいやおいしさが生まれるのと同じで、ヒトとヒトにもマリアージュがあると思います。幸せなマリアージュからは、幸せな展開が生まれるのです。
Slow Neighborhoodの“スロー”というコンセプトも素敵だなと感じています。お酒を醸すには長い時間がかかります。酒蔵にいると1年周期でものを考えるし、四季の変化でお酒の味わいも変化します。一方、普段の生活の中では、なんだか時間に追い立てられることが多いですよね。でも、コロナ禍によって家で過ごす時間が長くなり、スローダウンすることを余儀なくされて。社会全体がコロナ禍で一度立ち止まらざるを得なくなったことは、あらためて生活や仕事のリズムを見直すきっかけになりました。高速回転しているときには見えなかった景色や人との出会いが、これからは大事にされると思います。
【最初の画像】
上/木造校舎をそのまま活かした学校蔵。
下/「学校蔵の特別授業2019」の様子。
【画像1】
上/尾畑酒造の尾畑留美子さん。
下/新大久保K,D,C,,,で開催した「佐渡島・学校蔵の出前授業」の様子。尾畑酒造代表取締役社長の平島健さん、尾畑さんが講師を務めました。
地方から気づきを得て探る将来の日本のあり方
──都会に暮らす人からすると、地方に興味があったり、関わりを持ちたかったりしても、果たして地方の人に受け入れてもらえるのだろうかと懸念することもあると思います。尾畑さんのお話や学校蔵の取り組みを聞いていると、佐渡には誰でも受け入れてもらえそうな風土がある気がします。
尾畑:リモートワークが浸透し、いろんなライフスタイルが自由に選べるようになったので、生活の拠点を都会から地方に移すといったことも含めて、地方への関心はますます高まっています。佐渡島は少子化や高齢化など、日本の課題先進地と言われていますが、実は近年20~40代の移住者が増えているんです。
実際、弊社にもこの数年の間にIターンのスタッフが増えています。みなさん、週に3~4日弊社で働いて、ほかの時間は佐渡で実現したかったこと、カフェや民泊などに取り組んでいます。地域ならではの事業に関わりながら同時に自己実現も目指すという、まるで2台の車を操るようなオリジナルのライフスタイルを確立していて、新しい“移住ライフの形”を感じています。
地方は都会と違って小さな事業者が多いですし、それぞれが連携しながら活動しています。そして人口が少ないので、おのずと一人ひとりの役割が大きくなる。移住者の人も地域や仕事で期待されて力を発揮できる場がたくさんあります。役割って、パズルのピースみたいな「居場所」でもあるのかなと。地域の中に居場所があるって心地いいですよね。
佐渡は順徳天皇や世阿弥、日蓮といった人たちの配流や、江戸時代に佐渡金山の繁栄とともに多くの人や文化が各地から入ってきた歴史があります。もともと外のものを受け入れ、佐渡島の中で融合させていくという文化があるのかもしれません。
──尾畑酒造さんは創業から100年以上の歴史を持ちながらも学校蔵のような新しい取り組みにも積極的で、将来のことまで長いスパンで捉えていらっしゃるのかと思います。尾畑さんから見て、これからの地方のあり方をどのように考えていますか。
尾畑:100年以上も続けてこられたということは、過去の“時代の変化”も乗り越えてきたということです。決していい時代ばかりでなく、失敗や困難が立ちふさがったことも何度もありました。そうした「失敗の歴史」がDNAにあるのは宝物とも言えます。過去を振り返ってみれば、厳しい時代がずっと続くわけではない。そう信じて次に進むんです。老舗と呼ばれる企業は保守的だと思われるかもしれませんが、実際には変革の連続で事業を継続しています。そういう意味では「老舗のベンチャー」の気概を持っています。学校蔵も、そんな精神から誕生しました。
学校蔵の「酒造り体験プログラム」ではここ数年、海外からの参加者も増えています。“佐渡と世界を直接つなぐ”プログラムになってきているのです。そんな参加者に対して私たちが提供しているのは、豪華な「おもてなし」ではなく、リアルな佐渡の風土とリアルな酒蔵の日常という「おすそわけ」です。おすそわけのいいところは、お返しという継続的な関係を生むところ。実際、リピーターの方も多いです。
これからの地方は、世界とダイレクトにつながっていきながら、ほかの場所にはないここだけの宝物を「おすそわけ」していくように思います。そして、「ご近所さん」も地球規模になっていくんじゃないでしょうか。
【画像2】
新大久保K,D,C,,,で開催した「佐渡島・学校蔵の出前授業」では、日本酒のテイスティングのほか、料理とのマリアージュも。