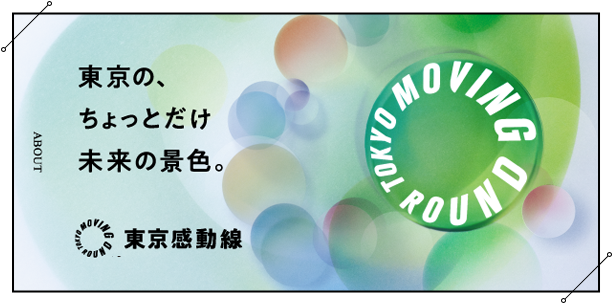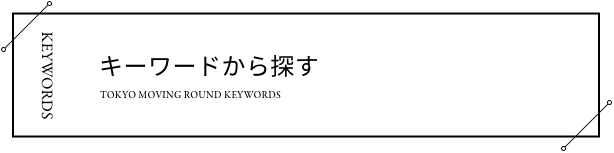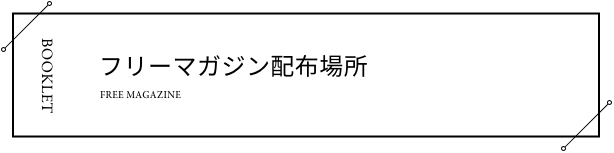誰もが「ホスト」となり、自分の好きなことを「ゲスト」に体験としてシェアできるサービス「TABICA」。そのなかで東京感動線は、山手線沿線の魅力を再発見する体験づくりのお手伝いをしてきました。
そして2020年12月、新しくスタートしたのが「地域とつながる」体験。福島県の会津地方の方々がホストとなり、野草茶や革小物づくりなどのワークショップを行いました。好評を得て、2021年5月にふたたび行われるこのコラボレーション。その背景について、西会津町の一般社団法人BOOT(ぶっと)の横山裕さんと東京感動線の古田恵美が語り合いました。
→「東京感動線×福島県西会津町 vol.02」はこちら
→「東京感動線×福島県西会津町 vol.03」はこちら
小さな一歩となった、TABICAでの取り組み
──まずは、西会津町とのコラボレーション以前から行ってきた、TABICAとの協働について教えてください。
古田:東京感動線は、山手線沿線に心が動かされる体験を増やしていく活動をしています。一方でTABICAは、ワークショップや街歩きなど、自分の得意分野や趣味を生かした体験を提供する日本全国のホストと、参加者であるゲストをつなぐプラットフォーム。TABICAとの協働を通じて、“人を起点にして街を体験する”ことを目指しています。
──その流れのなかで、地方とのコラボレーションの第1弾として組んだのが西会津町ということですね。
古田:そうです。横山さんと知り合ったのは、私が地方勤務だったとき。そのあと東京に異動し、横山さんに「今、東京感動線という活動をしています」と話したんです。そのなかで、今までは地方のことを東京に紹介するときは「旅に来てください」とか「おいしい食べ物があるから食べてみてください」という表現だったけれど、東京の暮らしと地方の暮らしを重ね合わせたら、お互いの暮らしが豊かになってくるんじゃないかという話になって。その小さな一歩として、2020年12月にTABICAを通して西日暮里駅のエキラボniriで4つのワークショップを行いました。
横山:僕は前職が観光関連の仕事だったのですが、“地方のものを東京に売り込む”ことにどうしても違和感があって。同時に、日本の経済が東京に集約されていることへの違和感も強く持っていました。本来はフラットな関係で、お互いの地域を行き来する環境を再構築することが大事なんじゃないかと思ったんです。さらにコロナの流行が、くしくも東京と地方、街と自然の関係の在り方を見直す機会になりました。
TABICAは旅行業と違ってCtoCなので、自分がいいと思っているものをほかの誰かに気軽に紹介できます。もともと会津にも似たような活動をやっている人たちがいたので、ワークショップではそこをうまく組み合わせられたらと考えました。
【画像1】
BOOTの横山裕さんと東京感動線の古田恵美。
“暮らしをつくり上げていく力”を取り戻す
──ワークショップのホストの人選は横山さんが担当したのですか?
横山:そうですね。BOOTが運営している、西会津国際芸術村に集う人たちを中心にお声がけをして、一緒に企画を練りました。東京の、特にコロナで街や家にこもる生活に欠けているのは、自然のなかで感じる空間と時間の揺らぎだったりする。そう考えて開催したのは、お箸をつくる木工教室、西会津の自生植物でお茶を淹れる野草茶レッスン、革のミニ財布づくり、西日暮里にある植物でアロマオイルをつくる講座です。たとえば野草茶レッスンは、身近な植物を使って、「夏至」や「冬至」など二十四節気に基づく季節の変化を味わうもの。どれも生活にひもづいた自然や季節を楽しむワークショップにしました。
古田:私もゲストとして参加しました。アロマオイルの講座では街にも出て、公園で葉っぱの香りを嗅いでみたら、心が穏やかになるすごくいい香りで。アロマの精油になるような香りが街なかにもあるんだと驚きました。どれもおもしろくて、いつもはネットやお店で買っているものを、自分でも作れるんだという発見がありましたね。暮らしを自分でつくっていく力は、便利な生活をしすぎるとなくなっていってしまうのかもしれません。だからこそ、一つひとつが貴重な経験でした。
横山:昔は、東京でも身近な資源でモノを作っていたと思うんですよね。今の東京は大量消費型の社会になってしまった。東京感動線が謳っている「東京の、ちょっとだけ未来の景色。」っていうのは、そういうものをもう一度取り戻すことでもあるんじゃないかなと思います。
古田:東京では自然と暮らしが切り離されているように感じるのですが、自然の恵みは、実は今でも身近なところにある。そういうことを感じながら、暮らしをつくり上げていく力……それは生きる力なのかもしれませんが、そういう力を少しずつ身につけていけると、暮らしはもっと自由で豊かになっていくのかなと思います。
【画像2】
2020年12月に開催した「街歩きでつくる国産アロマブレンドワークショップ」。
お互いの違いこそが価値になる
──前回のTABICAでのワークショップは、“小さな一歩”。これからどんなことを目指していますか?
横山:まずは「山手線を起点に、東京の暮らしの価値を拡張する」ということだと思うんですよね。拡張するというのは、東京に地方のモノを持ち込んで売るということではなく、暮らしの価値に気づくこと。閉じていると、自分の街の暮らしの価値がわからないんですよね。東京の人と地方の人がお互いの暮らしを見て「ここは自分の街とは違うな」と感じるところ、それこそが街のバリューになると思います。田舎がいいとか都会がいいとかじゃなくて、自然と都市がもつ“違い”が、価値としてどう捉えられるかが重要なんだろうなと。
──お互いを売り込むのではなく「私たちの暮らしのこういうところをおもしろがるんだ」と発見していくようなことですね。
横山:そうですね。つまり“気づき合う”ということだと思います。西会津に来て自然に触れてはじめて東京の暮らしの価値に気づいたりするので、往来することも重要ですし、なにより一人ひとりとつながり合うことがすごく大切だと思います。
──リモートが広がってきたことで、たとえば地方に住んで月に2、3回東京に通うという生活スタイルも生まれています。東京と地方の距離が縮まってきたことを、お互いの立場としてどのように見ていますか?
古田:たしかに、コロナで距離の概念がよくわからなくってきている感覚はあります。でも一方で、東京の暮らし自体は、極端に言えばマンションに閉じこもってコンビニでお弁当を買ってくるみたいな生活ですよね。地方は地方で、これまでと変わらない自然のなかでの暮らしがあるので、テレビ会議なんかはかなり普及してきているものの、暮らし自体の距離は縮まっていないのかもしれないなと。せっかくリモートが進展してきているので、もう少し暮らしが重なり合っていくようなきっかけを、今回のコラボレーションなどを通してつくっていけたらと考えています。
横山:移動手段も進化しましたしね。物理的な行動範囲は広がっているので、あとは移動した先でどういう暮らしの延長をつくれるか。そのために、誰かと話して自分の暮らしの魅力や価値に気づく時間が必要なんだろうなと思います。
それから、地方の現実的なところでいうと、やっぱり経済をつくっていかないといけないですよね。商品を東京に持ち込んで売る時代ではなくなっていくとすると、それに取って代わるのは、TABICAのような人と人のつながりから生まれる身の丈に合った経済。東京の人と話しているうちに、自分の地域のいいモノや、当たり前だと思ってやっていた暮らしの価値に少しずつ気づき始めて、それをどのように提供していけば経済として回るかが見えてくると思います。
【画像3】
西会津の風景(上)と、西会津国際芸術村(下)。廃校となった木造校舎に芸術家を招いて住居兼アトリエとして活用し、さまざまな交流を生み出している。
次回は、新しいワークショップも
──2021年5月、TABICAでふたたび会津の方たちとコラボレーションした体験を行うとのことですが、どのような内容になるのでしょうか?
横山:まずは、前回行ったワークショップを、テーマはそのままに内容をアップデートしたいと思っています。それらに加えて、東京と西会津を往来しながら創作活動を行う演劇人の方による「土地のルーツを探る言葉」についてのワークショップも。今回は、新しい技術で空間を拡張したリモートで実施することも考えています。
ふたたび実施することになったのは、前回を終えたあと、一度きりじゃもったいない、つながる人たちをもっと増やしていきたいと考えたから。それに、継続して開催することで、ホストとゲストの双方が、その体験をより日常化させることができると思ったからです。
将来的には、ワークショップにとどまらず、季節をおすそ分けするようなサービスがつくれないかと考えています。TABICAで体験したことを日常の暮らしに取り入れたいと思った人に向けて、キットのような形でお取り寄せできるようにするのもいいなと。
──今後の展開について、描いていることはありますか?
古田:いろんな地域にそれぞれの暮らしの良さがあって、横山さんの言葉を借りれば、それをみんなが“おすそ分け”し合えたら、東京感動線が目標にしている「東京の、ちょっとだけ未来の景色。」が見えてくると思います。そういう動きをもっと気軽に、たとえば駅や鉄道をきっかけにしながらハードルを下げていけるといいなと思っているので、引き続き今回のような試みを続けていきたいです。
横山:以前古田さんから、山手線は最初からリング状だったわけじゃなくて、各地方に向かって伸びている幹線がつながっていってリングになったと聞きました。そのことを知って、なるほどなと。東京の食文化なんかを見ても、いろんな地方とのつながりがあるんですよね。それにはたぶん、かつて日本に参勤交代という地方のものを東京に集める政策があったことにも関係していると思います。その後、産業政策も含めて東京から地方をむすぶ流れのなかで山手線が生まれたと考えると、単純に東京の暮らしだけが切り出されて豊かになっていくということではないんだなと感じます。
地方側の視点から見ると、東京の暮らしとつながることで地方の価値をいかにつくるかということもやはり重要です。東京には東京の暮らしがあって、会津には会津の暮らしがある。まずは認め合うことでお互いの価値を発見するベースをつくり、それを地方としてどう生かしていけるかを引き続き考えていきたいですね。
【画像4】
2020年12月に開催した「暮らしを豊かに!自分だけの革のミニ財布づくり」(上)、「暮らしを豊かに。自分だけの箸づくり木工教室」(下)。