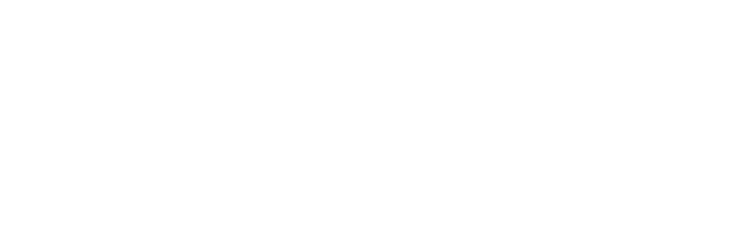出羽三山、江戸隆盛の秘密
憧れの霊山〜
江戸時代、東北・関東一円の信仰を集めた出羽三山。なぜ、中央から遠く離れた霊山へと人々は参詣したのか。隆盛の鍵となる人物を軸に、三山が再興されていった時代に光を当て、その名を広めた幕府の威光やさまざまな物語に迫る。
写真/『湯殿月山羽黒三山一枚絵図』(部分/画像提供:羽黒町観光協会)。出羽三山の参詣者のお土産として流布されたもの
講師/岩鼻 通明氏
(山形大学名誉教授)

羽黒山中興の祖・天宥と
江戸時代の出羽三山
江戸時代の初め、羽黒山第50代別当となった天宥(てんゆう)。彼が羽黒山中興の祖といわれるのは、徳川家康の宗教政策がもたらした出羽三山の危機を回避した業績に由来する。
家康の寺社法度は修験者の統括を目的とし、全国の修験道場は天台宗系の本山派と、真言宗系の当山派のどちらかに属さなければならないとされた。地方の修験の山々はそれまで独立性があり、峰入りという修行で独自に修験者の資格を与えていた。
これに対し天宥は、家康の側近・天海と結んでとある奇策を講じ、出羽三山の従来の地位と機能を守った。しかし、それは三山を天台宗派と真言宗派に二分する論争を生む。さらに、自身の失脚を招くばかりか、後の世にも軋轢を残すことになる。出羽三山は、そもそもどのような霊山なのか。古代からの変遷と天宥の策略を見ていく。
写真/「天宥法印御真像」(右/出羽三山歴史博物館蔵)。天宥が整備を行った杉並木や石段はいまも残されている(左)

出羽三山の名声を広めた
芭蕉の旅と参詣ルート
1689年(元禄2年)3(新暦5)月、松尾芭蕉は東北を巡る旅に出る。天宥の失脚から20年ほどを経たころである。芭蕉はこの旅で出羽三山に詣でて、1702年(元禄15年)に紀行文『おくのほそ道』に3句を載せた。
元禄は、庶民の間に「旅」という娯楽が広まり始めた時代。『おくのほそ道』は図らずも、出羽三山の名声を高めることに貢献した。門人をはじめとする芭蕉を慕う人々が紀行を読んで三山に詣で、それが庶民にも波及していったのである。
だが、芭蕉の出羽三山詣でには奇妙なところがある。登拝ルートが当時の慣例と異なるのだ。しかも、かなりの強行軍であり、羽黒山での滞在期間も異例に長い。そこには、何か秘められた意図や背景があったのか。同行した弟子の曾良が残した詳細な旅日記から二人の参詣ルートをたどり、天宥後の出羽三山の姿を探る。
写真/与謝蕪村『奥の細道図屏風』(部分/山形美術館蔵/長谷川コレクション)。芭蕉の『おくのほそ道』全文が墨書されている

庶民に親しまれた
お竹大日如来と湯殿山の誕生
羽黒山の門前町、手向(とうげ)の荒澤寺正善院に於竹大日堂(おたけだいにちどう)がある。江戸後期、「大日如来の化身」と庶民に信仰された女性、お竹さんが祀られている。
お竹さんは、羽黒山の麓に生まれたとも伝えられる女性。江戸の武家へ奉公に出されたが、働き者で信仰心が篤く、慈悲深い行いが評判になり、没後に奉公先の主人が大日堂に祀ったと伝わる。この物語は、歌舞伎や錦絵などの題材にもなり、江戸市中に広まった。
お竹さんが大日如来の化身とされたのは、両親が湯殿山に願掛けをして授かった子であり、湯殿山の本地仏が大日如来であったからだ。しかしこの物語は、出羽三山によって意図的に流布されていた気配がある。
東北や関東など東日本で広く信仰されていた出羽三山。その中にあって、なぜお竹物語は江戸市中で広められたのか。三山における湯殿山の異質な側面とともに、お竹さんの謎に迫る。
写真/河竹黙阿弥がお竹さんの物語を歌舞伎化した、『双蝶色成曙』の芝居絵(部分/東京都中央図書館蔵)
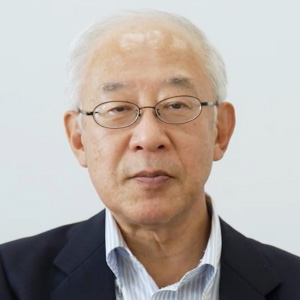
講師:岩鼻 通明氏
山形大学名誉教授。京都大学大学院文学研究科地理学修士課程修了。2003年「出羽三山信仰圏研究」で文学博士の学位を取得。2004年から2019年まで、山形大学教授を務めた。『出羽三山―山岳信仰の歴史を歩く』(岩波新書)、『出羽三山の文化と民俗』『出羽三山信仰の圏構造』(共に岩田書院)、『絵図と映像にみる山岳信仰』(海青社)など著書多数。