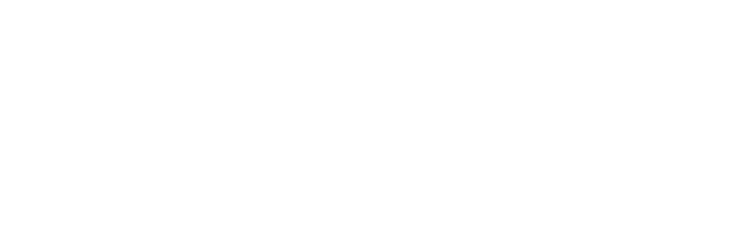縄文の
「食」をめぐる冒険
北の縄文生活〜
世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、1万年にもおよぶ縄文時代の中でも、北日本特有の文化を現代に伝える遺跡である。縄文時代の食生活を通して、北海道・北東北の縄文人の暮らしぶりを解き明かす。
写真/三内丸山遺跡で出土した縄文土器
講師/岡田 康博氏
(青森県 世界文化遺産登録専門監)

調理道具は縄文土器と黒曜石
〜縄文キッチン〜
土器は、縄文時代になって初めて登場する。縄文時代のキッチンに欠かせない調理器具である土器は、急激な環境変化に対応するため、縄文人が発明した焼き物の傑作といえる。縄文時代の初めには、このほかの調理器具も一通り整っていた。北海道・北東北の縄文遺跡群を代表する三内丸山遺跡からは、ナイフなどの材料となる黒曜石が各地から運び込まれており、さまざまな地域との交流が活発だったことを示している。
全国各地の縄文遺跡のなかで、北海道・北東北の縄文遺跡群の特徴は、規模が大きく、長く継続した集落が多いことである。遺跡や出土品の数も豊富なため、時代を追って暮らしの変遷を見てとれるところに価値がある。
日本最古といわれる土器は、青森県外ヶ浜町の大平山元遺跡から出土したが、実はこの土器には縄目模様がない。よく知られる縄文土器の優美な文様は、どのようにして生まれたのか。土器の造形・装飾などにも目を向け、縄文時代のキッチンを紹介する。
写真/ナイフなどに使われた黒曜石。三内丸山遺跡では日本各地の黒曜石が発掘されている(写真提供/三内丸山遺跡センター)

栽培する縄文人と生活環境の変化
〜縄文フード〜
近年、縄文人は狩猟採集だけではなく、栽培も行っていたことが知られてきている。その形跡を示すのは、各地の遺跡から出土するヒョウタン、ゴボウ、アサ、エゴマ、ゴマなどの種子である。北海道・北東北の遺跡からもイネ科の縄文ビエのほか、豆の野生種も出土する。だが、それらは食料の多くを占めてはいなかったようだ。
縄文フードの大半は植物性だといわれるが、北海道に限っては動物性食物の依存度が、本州よりも高い。川に回帰するサケやマス、アザラシ、オットセイなどの海獣類を得やすい環境があったからだろう。
また、北海道・北東北の縄文時代の生活を知る特徴的な食材として、「クリ」と「ハマグリ」が挙げられる。クリには管理・栽培した形跡が見られ、ハマグリは現在生息していないことから、気候変動との関係をうかがわせる。クリが津軽海峡を渡って以降、道南の集落が増加する傾向も注目されている。縄文フードから、当時の生活環境の変化を追う。
写真上/三内丸山遺跡のシンボル、大型掘立柱建物はクリの木が使われている。写真下/発掘された炭化したクリ

縄文人の食卓とニワトコの謎
〜縄文ダイニング〜
北海道・北東北の縄文人の食卓は豊かだった。そう思わせるものの一つが「ニワトコ」だ。三内丸山遺跡から、かなりの量の種子が出土している。利用目的は謎だが、興味深い指摘に「ニワトコ酒説」がある。ニワトコや木の実を配合し、発酵物らしきものを造っていた可能性が見えてきている。
また、遺跡からはスプーンやおたまなども出土している。縄文人たちは、食材を直接食べるのではなく、調理や加工をして、食器も用いていた。これも、縄文の「食」の豊かさを物語っている。
この豊かな食文化は、縄文人たちが自然と密接なつながりを持ち、人為的な生態系を保つことによってもたらされたと考えられる。海岸部にまで広がる落葉広葉樹の森に囲まれ、四季折々に多彩な有用植物や生き物を利用して暮らしていたのである。長きにわたる縄文文化の持続に果たした、縄文人にとっての食事の意味を考える。
写真/白神山地のブナ林。縄文時代、北東北では海のすぐそばまで落葉広葉樹の豊かな森が広がっていた

講師:岡田 康博氏
1957年、青森県生まれ。弘前大学卒業後、県内遺跡調査に携わり、1992年より三内丸山遺跡担当。現在、青森県 世界文化遺産登録専門監。著書に『改訂版 三内丸山遺跡』(同成社)、『遙かなる縄文の声』(NHKブックス)など。