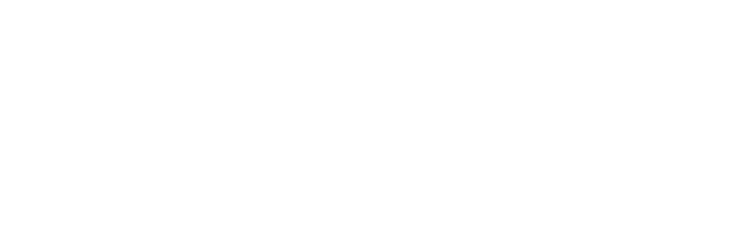不撓不屈(ふとうふくつ)の
南部魂
盛岡の幕末・維新~
戊辰戦争の敗戦で窮地に立たされた盛岡藩は、その逆境を覆して多くの逸材を世に送り出した。幕末の同藩家老・楢山佐渡(ならやまさど)と、平民宰相と呼ばれた総理大臣・原敬の足跡から、不屈の南部魂を読み解く。
写真/楢山佐渡肖像画(盛岡市先人記念館蔵)と
総理就任時の原敬肖像(原敬記念館蔵)
講師/田﨑 農巳氏(原敬記念館主任学芸員)

幕末の盛岡藩と楢山佐渡
楢山佐渡(1831~1869)は、幕末の混迷期に盛岡藩の家老を務めた人物である。藩財政が極度にひっ迫していた当時、23歳で職に就いた佐渡は、藩政改革や一揆の収束に尽力した。
眉目秀麗にして文武両道に秀でるも、人柄は謙虚で不正を嫌った。その業績と高潔さから現在、岩手県の先人の中でも、地元では原敬と並んで特に人気が高い。
戊辰戦争の当時、佐渡は家老として列藩同盟軍に与する決断を下し、結果として敗戦した盛岡藩は、新政府により「賊軍」とされてしまう。戦後、佐渡は戦争責任者として、盛岡の報恩寺で処刑された。「花は咲く 柳はもゆる 春の夜に うつらぬものは 武士の道」、「いくとせも 國安かれと祈るらん たゞひとすじに 武士の道」。佐渡は自らの死は「武士道」を貫いてのことだとする辞世2首を遺しているが、その決断の真意についてはよく分かっていない。幕末の盛岡藩の概略や、佐渡の業績と人物像を踏まえ、否応なく戊辰の戦いに巻き込まれていった過程を追う。
写真/右側に采配を振る楢山佐渡が描かれた『秋田戦争絵図』(田中堯史氏蔵)

苦境から立ち上がる
旧盛岡藩の若者たち
敗戦した盛岡藩に課せられた新政府の措置は過酷だった。軍資金7万両をはじめ、石高20万石から13万石に減封、白石への転封が命じられ、転封を免ずる条件として70万両の献金を言い渡される。
当初、藩士たちは土地や家宝を売り払ってまで、献金70万両を工面しようとした。そのため、藩士の家のことごとくが窮状に陥った。226石の上級藩士であった原家も、邸宅の5分の4を手放し、土蔵にあった家宝や調度品も売却。同家の次男・健次郎(のちの敬)は当時、まだ12歳である。
敗戦により、盛岡の人々はひどく打ちひしがれた。だが、その挽回に大きな役割を果たした存在に、藩校・作人舘(さくじんかん)がある。1870年(明治3年)に再開されたこの藩校からは、那珂通世(東洋史学者)、阿部浩(東京府知事)、菊池武夫(中央大学初代学長)、田中舘愛橘(たなかだてあいきつ/世界的な物理学者)、そして原敬など、多くの逸材が巣立つ。彼らの活躍は次の世代が飛翔する下地ともなった。作人舘に集い、苦境から立ち上がろうと奮起した旧盛岡藩士の若き子弟らの姿を追う。
写真/作人舘の後身、盛岡市立仁王小学校には藩主・南部利恭(としゆき)の書による扁額が伝わる

「賊軍」から「平民宰相」へ
明治になって再開された作人舘に集い、学んだ若者のなかから、原敬の生涯を追ってみよう。彼は15歳のときに故郷を離れて上京するが、その後も浮き沈みの激しい人生を生きた。
戊辰戦争の戦後処理で生家は困窮。上京後は私塾通いをするも、生家に泥棒が入り、学資を絶たれる。ようやく司法省法学校(現・東京大学法学部)に入学したと思えば、3年後には放校処分になる。
その後も「浮沈」を繰り返す原だが、彼はけっしてめげない。策を講じて常に立ち上がって前進している。
やがて政治家となり、活躍していた1917年(大正6年)、旧南部藩戊辰殉難者五十年祭が開かれた。会場は、楢山佐渡が処刑された報恩寺。この五十年祭で原は祭文を読み上げ、非業の死を遂げた人々の霊を慰めるとともに「賊軍」の汚名をそそいだ。
翌年、62歳の原は藩閥や公家以外で初の総理大臣に就任する。逆境に負けず、信じる道を歩み続けた「平民宰相」原敬の人間力に迫る。
写真/原敬記念館の敷地内にある、原敬が15歳まで過ごした生家は期間限定で内部を公開(写真提供:原敬記念館)

講師:田﨑 農巳(たざき あつみ)氏
原敬記念館主任学芸員。1975年、岩手県宮古市生まれ。山形大学人文学部、神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科等で、日本史・日本民俗学を学ぶ。2004年から盛岡市先人記念館、2016年から原敬記念館で学芸員を務め、幕末から昭和初期に活躍した地元の先人たちを研究、企画展や講座、原稿執筆等で普及活動を行っている。