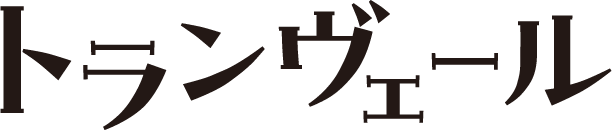2021年 1月号 特集
いつでも着物を
大正時代に大胆な色柄で一世を風靡した栃木の足利銘仙。100年もの時を経た今、再び古着着物を中心に人気を集め、地元企業が作った足利銘仙の洋服地は、欧米の高級ブランドからも注目されている。さらに、県内で出土した機織形埴輪が国の重要文化財に指定され、栃木の織物にまつわる歴史の深さや、県内で生産される結城紬にも関心が高まっている。栃木で着物の素晴らしさを再発見する旅に出た。
いつかは手元に 結城紬

「本場結城紬」を知ることで、栃木の着物をめぐる旅は一層深まる。結城紬の生産地は栃木県南部と茨城県西部にまたがる。小山市北東部の、東に鬼怒川、西は思川が流れる豊かな水に恵まれた地で古くから養蚕が行われ、結城紬が作られてきた。結城紬の製作工程は30以上に及ぶ。なかでも国の重要無形文化財に指定されている「本場結城紬」の条件は、「糸は真綿から手紡ぎ」「柄を作る絣くくり」「地機での機織り」の3点だ。写真は、蚕の繭を広げた真綿から糸を紡いでいるところ。

「絣くくり」(写真)は、何十本も束ねた紡ぎ糸を絣模様に合わせて綿糸でくくる工程だ。模様の部分だけをあらかじめ糸でくくり、染料が染みこまないようにする。こうして細かい模様が生み出されていく。重要なのは同じ強さでくくること。綿糸をきっちり巻きつけて、結んで糸を切る。作業はその繰り返しで、模様の細かさにもよるが何カ月もかかることもある。

写真は、地機で織っているところ。緯糸(よこいと)は随時模様を確かめながら、経糸(たていと)も時々チェックしては針で糸を引っ張って模様のずれを修正しつつ織っていく。精緻な模様は、絣くくりはもちろん、織りの地道な模様合わせあってのもの。作り手が心を込め、磨き抜かれた手仕事の技と気が遠くなるほどの時間を費やすことで、着物好きなら誰もが憧れる本場結城紬が出来上がる。