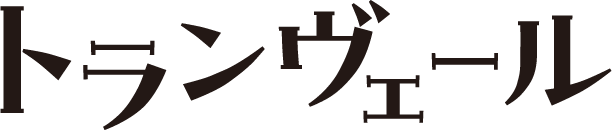2021年 1月号 特集
いつでも着物を
大正時代に大胆な色柄で一世を風靡した栃木の足利銘仙。100年もの時を経た今、再び古着着物を中心に人気を集め、地元企業が作った足利銘仙の洋服地は、欧米の高級ブランドからも注目されている。さらに、県内で出土した機織形埴輪が国の重要文化財に指定され、栃木の織物にまつわる歴史の深さや、県内で生産される結城紬にも関心が高まっている。栃木で着物の素晴らしさを再発見する旅に出た。