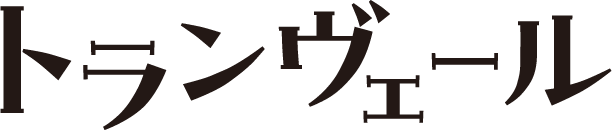栄華を誇った
いにしえの常陸国

菅原孝標は長元5(1032)年から9(1036)年にかけて、孝標女ら家族を京に残し、単身で常陸国(ひたちのくに)に赴任している。常陸国は現在の茨城県の大半を占めるエリアで、国府は石岡市の場所に置かれた。そのため、茨城にも『更級日記』の舞台といわれている場所がある。『更級日記』には、『神拝といふわざして国のうちありきしに』という記述がある。国司は赴任後に在地の神社をめぐり、参拝を行うのが慣習だった。常陸国で一番格式の高い鹿島神宮には、孝標も訪れた可能性がある。

孝標が赴任する数百年前から、常陸国は山海の美味に恵まれた豊かな国だった。茨城県内に数千基も残る古墳がその事実を物語る。6世紀初頭に築かれた富士見塚古墳はとくに巨大で、墳丘の全長は約80メートル、高さは約9メートルもある。当時内海だった霞ケ浦に入港した船からも前景が見渡せるほどの、圧倒的なスケールだ。常陸国は舟運を通じて他国と結び付きを強めていた。巨大な古墳には、他国からやってきた人々に、被葬者の権力を誇示する狙いがあったという。

常陸国の人々は、遥か遠く九州とも交易をしていた。その証拠の一つがひたちなか市にある虎塚古墳である。虎塚古墳は6世紀後半以降に築かれた茨城を代表する装飾古墳で、被葬者は海運に関わった人と考えられている。その石室に描かれた幾何学的な図形は、九州の古墳に多く見られる特徴だという。写真は、ひたちなか市埋蔵文化財調査センターにある原寸大の石室レプリカ。装飾古墳は、広範囲にわたる文化圏を築いていた常陸国の栄華を、雄弁に語ってくれる存在だ。