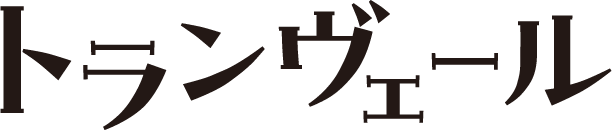名句誕生の地で
新訳に挑む

夏草や兵どもが夢の跡
I dream of heroes,
deeds, then awake ―the grass sways
in the summer breeze
Arthur Binard
芭蕉が名句を生んだ地をビナードさんが訪れ、新訳を作る。まず訪れたのは源義経終焉の地、岩手県の平泉。ここで詠まれた「夏草や」の句は多くの人に訳されてきた。ここでいう夢は「兵士たちが栄光を夢見た」と解釈されることが多い。しかし深沢さんは「芭蕉の夢に兵が現れたことを詠んでいるという説があるんです。芭蕉の時代、『夢』という言葉は眠っている時の『夢』だけで、将来の希望という意味はなかったと分かっています。」と解説する。ビナードさんは、芭蕉が夢を見ているので I dream と始め、grass sways in the summer breezeと、芭蕉が兵の気配を夏草のそよぎに感じているように訳した。

閑かさや岩にしみ入る蟬の声
Up here, a stillness――
the sound of the cicadas
seeps into the crags
Arthur Binard
次の行き先は、山形県山形市にある天台宗の名刹・立石寺。山門から800段を超える石段を登り、奥の院へと向かう。芭蕉がこの山寺で詠んだ句について、ビナードさんは「閑かさや」がキーワードだという。深沢さんも「『しずか』を『閑か』と書く場合には、安定した穏やかな状態、禅の悟りにも通じる精神的な境地を指します」とうなずく。それを踏まえ、静寂だけでなく動かない状態も指す、stillness という言葉をビナードさんは選んだ。山頂へと続く険しい道を上りきれば、山々を渡る風に汗も引き、不思議と心が浄化される。「閑か」という言葉がしみ入る心地がした。

象潟や雨に西施がねぶの花
Extreme beauty is ominous――
these Kisakata Isles, silk trees in the rain
blooming like tragic heroines
Arthur Binard
芭蕉が訪れた時、秋田県の象潟は、鳥海山を背景に多くの小島が潟に浮かぶ景勝地だった。芭蕉は象潟の句に、中国四大美人の一人、西施を登場させている。西施といえば、美しさ故に政治の道具として利用された悲劇のヒロイン。そのイメージから「ominousは、不吉な前触れや兆しという意味。Extreme beautyを置いて、美しすぎるものは滅びを感じせる......といった訳になるね」とビナードさん。象潟は芭蕉が訪れた100年以上後に、大規模な地震によって隆起。景色も様変わりしてしまった。芭蕉は、象潟に何か予感を感じていたのだろうか。