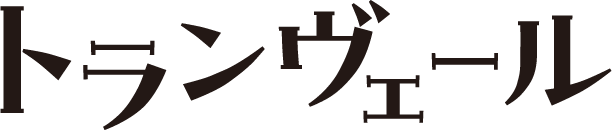交易の民、アイヌ。
その足跡を訪ねて。

「二風谷アイヌ文化博物館」には、日常生活や祭祀などでアイヌが使った道具がずらりと並び、圧巻だ。和人との関係性が色濃く表れた道具も多く、例えば、女性用の“タマサイ”という首飾りは、修験者の装飾品に似ている。アイヌは本州で盛んだった修験道の影響を受けたのかもしれない。数々のアイヌの道具を通して、日本の失われた文化や風習を見つめ直すこともできる。
(二風谷アイヌ文化博物館蔵)

渡島半島の南西にある上ノ国町は、1470(文明2)年ごろに築かれた山城「勝山館(かつやまだて)」を中心としたアイヌと和人の交易都市だった。これまでは市街地に流れる「天の川」を境に北側がアイヌ、南側の勝山館周辺が和人の居住地と考えられていた。しかし近年、城跡からアイヌの墓が見つかり、城内でのアイヌと和人の共存が明らかになったという。写真は勝山館から約2キロ南東にある「花沢館(はなざわだて)」での発掘の様子。ここからも古いアイヌの品が発掘されていて、勝山館より先に共存が進んでいた可能性もある。

13世紀ごろに青森県の十三湖の畔に開かれ、上ノ国以前の北方交易を担っていた港が「十三湊(とさみなと)」である。十三湊からは、アイヌ関連の遺物とされる蝦夷拵えの刀装具とガラス玉が出土している。アイヌは津軽海峡を越え、本州まで足を延ばしていたのだろうか。青森や秋田にはアイヌ語由来とされる地名が多い。「アイヌの言葉を話し、伝統的な文化を享受する人々がいたことは間違いありません」と五所川原市教育委員会の榊原滋高さんは語る。
中世の北海道・青森には、“交易の民”アイヌと和人の交流が生んだ豊かな社会と文化が存在したのだ。