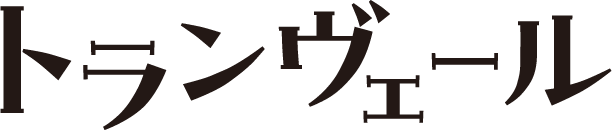アラマタ的
新七不思議の旅

昔から庶民の旅のスタイルとして人気がある、七不思議を訪ねる旅。博物学者・荒俣宏が、東日本の新しい夏の楽しみ方として、令和版の新七不思議を提案。ここでは七不思議の旅の中から3つを紹介する。

まずは、秋田県男鹿半島にある「なまはげ館」。ここには男鹿半島に伝わる150ものナマハゲ面が展示されている。ナマハゲは、大晦日の夜、荒々しく咆哮しながら里の家を回る来訪神だ。日本の東北地方の大晦日の行事と思いきや、ヨーロッパのクリスマスやハロウィンとつながる原始的な信仰だった。その共通点に、不思議を感じる。

江戸時代、現在の山形県鶴岡市の吉蔵が臨死体験をする。それだけならよくある話だが、吉蔵の場合、その体験を画僧が聞き取り、『念仏吉蔵蘇生物語絵巻』が作られたことで貴重な史料が残ることになった。登場人物は実在する人々で、息絶えてから蘇生まで10時間余りなど、物語が良く整っていて詳細、大変珍しいものだと、探偵団も感心。

江戸時代後期から明治時代にかけて活躍した庄内藩士、松森胤保(まつもりたねやす)が遺した生物図鑑や発明品を訪ねて鶴岡へ。胤保は、鳥船と呼ばれる飛行船の図を残し、生涯で328冊もの著作を残した人物だ。藩の政治を背負って立つほどのエリートが、なぜ図鑑の製作や発明に没頭したのか。謎多き人物像に迫る。