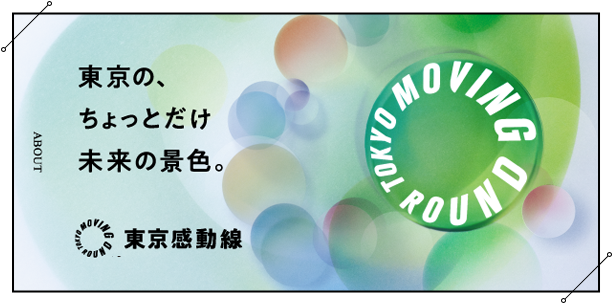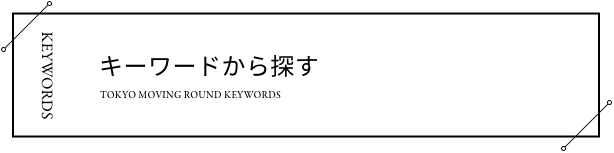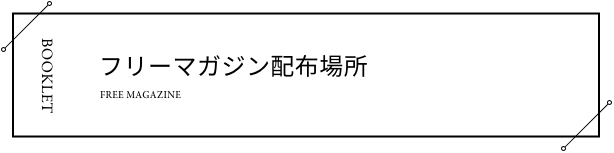渋谷駅直結・直上の大規模複合施設「渋谷スクランブルスクエア」の15階に位置する「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」は、年齢も職業もさまざまな人々が集う場所。彼らをつないでいるのは、“問い”です。自分のなかにある問いを見つけて磨き、チームをつくり、形にして世に放つ。そのプロセスを丁寧にたどり、これまでにない価値を秘めたたくさんのプロジェクトが生まれているといいます。コミュニティを活性化させる仕掛けや“問い”の深め方について、ディレクターの出川久美子さんとプログラムマネージャーの渡邉博之さんに伺いました。
大空間で生まれる自由なコミュニケーション
──SHIBUYA QWSのコンセプトについて教えてください。
出川:SHIBUYA QWSは、個人やグループが持つ“問い”や課題に対し、プロジェクトとして取り組むための会員制の拠点です。昨今では“イノベーション”というと、起こすこと自体が目的化してしまっていて、結果的にあまりいいものが生まれづらくなっているのが課題になっていると感じています。私たちはそうではなく、ここに集う人たちが自分自身の問いや課題を見つけて対話を通して深めていき、その結果としてイノベーションが生まれたり社会課題が解決されることを目指しているんです。
渡邉:渋谷スクランブルスクエアの15階フロアをまるごと占める約2,600㎡の空間は、間仕切りをなるべく少なくした開放的な雰囲気。メインの活動の場となる実験場のような「PROJECT BASE」、人々が行き交い交流するリビングルームのような「CROSS PARK」、平常時は200名規模のイベントが開催できる「SCRAMBLE HALL」など、多様なスペースがあります。さらに、3DプリンターやレーザーカッターなどのFab機器も用意していて、使い方をレクチャーする講座を定期的に開いています。
──問いを共有してチームをつくり、プロジェクト化につなげてもらうために心がけていることはありますか?
出川:まず大切なのは、会員同士が気軽にコミュニケーションをとれるようにすること。そのためにいろいろな工夫をしています。たとえばPROJECT BASEでは、各テーブルで、プラカードに個人やチームの問いを書いた“問い立て”を立ててもらうようにしています。“自分たちはこういう問いを持って活動しています”とほかの人に伝えることで、「私も同じようなことを考えてるんです」とか、「この問いのこと、詳しく聞かせてください」というふうに話しかけるきっかけになる。話しかけられたほうは快く応じるルールになっているので、会話が生まれやすい環境なんです。
【画像1】
“問い立て”に書く問いは、日によって変わってもOK。コミュニケーションを通じてプロジェクトチームがつくられたり、プロジェクト活動が活性化していく。
問いを見つけることから始まるトライアル
──会員にはどんな方が多いのでしょうか?
出川:多様な人が集うことで、今まで想像していなかったものが生まれると考えているので、ターゲットはあえて絞っていないんです。「問い」をもって活動されているという点が会員のみなさまの共通項となっています。
渡邉:中高生や大学生、大学教授、会社の仕事以外に自分の活動もしたいという会社員、スタートアップを立ち上げて間もない方、アーティスト活動をされている方など、属性はさまざま。今までご活動されてきた方々の年齢も、下は14歳、上は91歳とすごく幅広いです。もしも渋谷のスクランブル交差点を歩いている人たちをシャベルですくいあげたら、きっとこんな感じの構成になるんだろうなというくらいの多様性があります。
出川:昨年開催したQWS開業1周年のトークイベントで、QWSのメンバーでもある起業家の麻生要一さんが“問いの前ではみんな平等”とおっしゃっていて、本当にその通りだなと。属性や年齢に関係なく、みんながそれぞれの問いに向き合っていますし、これまでに交わらなかったたくさんの人とつながれる場になっていると思います。
渡邉:特徴的なのが、最初からイノベーションや起業を求めている人ばかりではないということです。プロジェクト化のスタート地点になるのは、あくまでも問いを見つけること。だからこそ、いわゆる“意識が高い”人だけじゃない、いろいろな人が集まっています。
出川:まだ自分の問いがなにかわからないけれど、なにかしたいという方に向けては、「QWSカルティベーション」というプログラムを用意していて。全9回で、「出会う」「磨く」「放つ」の3つのフェーズがあります。
自分の問いを見つけて深堀し、チームビルディングができる状態にするのが「出会う」。次の「磨く」では、チームで立てた問いをより深めるリサーチ方法などを学びます。そうして磨いた問いを世に出していくために必要なことを学ぶのが「放つ」。問いを形にしたプロトタイプを作って、みなさんにお披露目していただきます。
──一連の流れを体験することで、どういう道筋で問いを立て、プロジェクト化していくのかがわかるようになっているんですね。
出川:はい、プロジェクト化までのプロセスが体系的に学べるようになっています。QWSカルティベーションは会員でない方も参加することができるので、入会前にトライアルとして体験していただくのにもぴったりです。
【画像2】
過去の「QWSカルティベーション」の様子。現在はリモートを中心に開催している。
活動をもっとアクティブにする仕掛け
──自分のなかにある問いを見つけたり、プロジェクトを活性化するための工夫には、ほかにどのようなものがありますか?
出川:大学や企業パートナーと連携したさまざまなプログラムを用意しています。2020年に開催した、プロダクトデザインやプロトタイピングについて体系的に学ぶ2カ月の「QWS PRODUCT BOOTCAMP」もそのひとつ。
渡邉:プロダクトデザインについてまったく学んだことのない初心者の方もチャレンジしやすい内容で、デザインの基礎から始まり、最終的にプロトタイプを作ってプレゼンテーションをしていただくところまでやりました。
出川:それから、月1回の「スクランブルミーティング」も特徴的なプログラムです。「QWSコモンズ」としてQWSをご活用いただいている起業家や投資家の方、大学の連携パートナーの方などにメンターを務めていただいて、プロジェクトチーム単位でメンタリングを受けられるものです。プロジェクトを進めるうえでの悩みを相談し、アドバイスをもらいながらブラッシュアップしていくことができます。
──知見の深い方に直接相談できるんですね。
渡邉:さらに、施設のなかにもいろんな工夫をしていて、たとえばひとつのクエスチョンに対して、みんなが自由に答えを書いて貼っていく掲示板「Question Board(クエスチョンボード)」があったりします。このあいだは「生きてるってどんなときに感じる?」という質問に「温泉入ってるとき」「ペットと戯れてるとき」「おいしいものを食べてるとき」といった答えが集まっていました。何気ないことですが、多様な価値観を眺めることがアイデアのきっかけや視野を広げてくれることもあると思います。
出川:質問を貼り出している“コミュニケーター”と呼ばれるスタッフは、それ以外にも、親和性の高そうなプロジェクトのメンバーを紹介したりと、会員同士のつながりをつくってコミュニティを活性化させるはたらきをしています。日々のコミュケーションを促進させつつ、プログラムを通して体系的に学んでいただく。その両方にしっかり取り組むことが、みなさんの活動がうまく進んでいくことにつながるんじゃないかなと思っています。
【画像3】
イベント開催時以外には作業スペースとして活用できる「SCRAMBLE HALL」。広い窓の外に渋谷の風景が広がる。
問いから生まれた、バラエティ豊かなプロジェクト
──これまでにどのようなプロジェクトが生まれたのでしょうか?
渡邉:現在は約40のプロジェクトが進行中なのですが、そのなかだけでも音楽、アート、ヘルスケア、SDGsなど、ジャンルはすごく幅広くて。たとえば「都市空間に暮らす人とペットの健全な共生の在り方とは?」という問いのもと進んでいるプロジェクト「変幻自在」では、原材料から製法、会計情報、未調査の部分も含めてすべての情報を公開して、人間側のメリットを追求するのではなく、犬に本当に必要な栄養素を提供するドッグフードを開発しています。
出川:渋谷の街から出た生ごみを再利用して肥料をつくる「渋谷肥料」プロジェクトは、さまざまなメディアに注目されています。このプロジェクトは渋谷のごみ問題に着目したことから始まり、「渋谷を『消費の終着点』から『新しい循環の出発点』にシフトできないか?」という問いを立てました。渋谷の生ごみからつくった肥料でさつまいもを育ててスイーツにしたり、渋谷の商業ビルとつくった肥料で育てたハーブをコスメにして販売することを目指しています。
それから、元音大生が中心になって進めている「ミュジキャリ」も面白いプロジェクトです。発案者の方は、音大を出て実際に音楽を職にできる方の割合が非常に低い一方、何年も毎日楽器の練習をするようにすごく努力家気質な音大生は、実は社会で活躍できる場がたくさんあるのでは?と問いを立てたんです。自身のキャリアも生かし、プロジェクトを通して音大生の就活支援サービス「ミュジキャリ」を立ち上げました。今は会社も立ち上げ、順調に運営しています。
──すごくバラエティに富んでいますね。プロジェクト化に至るまでにいろんな過程があったのだろうと想像しました。
渡邉:これらのプロジェクトの入り口はやはり“問い”で、手探りで少しずつ進めてきたものもたくさんあると思います。「変幻自在」は、最初はペットが好きな人たちが集まり、ペットのヘルスケアでなにかできないかというところから始まりました。「渋谷肥料」も、最初からSDGsでなにかやろうとしていたわけではなく、渋谷の街でポジティブな取り組みになることがなにかできないかと1年ぐらい考えて、少しずつ形にしてきたプロジェクトです。
──「なにかやりたいけれど、なにをしたらいいかわからない」「SHIBUYA QWSが気になるけどハードルが高そう」、そう感じている方に伝えたいことはありますか?
渡邉:きっと、問いは誰しもの身近なところに落ちていて、それを突き詰めていくことで大きなものに育っていくんじゃないかなと思っています。そういう意味で、SHIBUYA QWSはみんながチャレンジできる場所です。 “人生100年時代”と言われ、働くことの定義や人生設計の考え方が変化してきている今、自分が本当にやりたいことを見つけるためにQWSに来てみるのはとてもいい選択肢だと思うんです。ぜひいろんな方に来ていただきたいですね。
出川:問いは誰しもが持っているものですが、自分がそれに気づけるかどうか、だと思います。そのきっかけを掴んでいただくのがSHIBUYA QWSの役割のひとつかなと。「私って、実はこういう問いを持っていたんだ」と気づいて、それを深めていった結果、イノベーションが生まれるのが理想だと思っているので、まずは「QWSカルティベーション」などで、「問い」に触れ合う体験をしていただけたらうれしいです。
【画像4】
「渋谷肥料」で開発したスイーツの試食会の様子。
アクセス
SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)
所在地/東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア(東棟)15F
営業時間/9:00~22:00(最終入館21:30)
※今後の状況により変更となる可能性があります。
https://shibuya-qws.com/