感染対策指針
1 院内感染対策に関する基本的な考え方
JR東京総合病院は、地域社会における豊かな生活の実現を担うJR東日本の企業立病院として信頼とやすらぎ、そして安心な医療を提供することを理念として掲げている。そこから、私たちは医療を必要とする患者とその家族、それを担うスタッフを院内感染から防護する責務がある。
そのため、効果的な感染管理組織を整備し、サーベイランスや感染に関する諸問題解決を核にした感染対策チーム、抗菌薬適正使用支援チームを編成し実行する。
また、全スタッフは感染対策マニュアルを遵守し、常に標準予防策と状況によっては適切な感染経路別予防策を医療行為において実践する。また、抗菌薬の適正使用を推進し、薬剤耐性(AMR)微生物の抑制に努める。さらに、院内外の感染情報を全スタッフが共有し、異常を速やかに察知し迅速な対応を目指す。病院感染発生時にはそれを分析・評価し、感染対策の改善に活かす。
こうした感染対策に関する基本姿勢をスタッフへ周知し、医療の安全性を確保し患者とその家族に信頼される医療サービスを提供する。
2 委員会組織に関する基本的事項
2-1) JR東京総合病院院内感染対策委員会規程
目的
第1条 JR東京総合病院における院内感染対策を目的として、JR東京総合病院に院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
審議事項
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査・審議する。
- (1)院内感染対策に関し、予算、施設、設備など重要な事項
- (2)院内感染対策に対するマニュアルの作成などに関する事項
- (3)院内感染対策についての周知徹底や啓発に関する事項
- (4)院内感染が判明した場合の報告とその対応に関する事項
- (5)その他、院内感染対策に関する事項
組織
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
委員長 院長が指名した者
副委員長 委員長が指名した者
委員 院長
インフェクションコントロールドクター(ICD)
インフェクションコントロールナース(ICN)
委員長が指定する医師若干名
看護部長
薬剤部長等の薬剤部門の責任者
臨床検査技師細菌検査担当者
事務部長等の事務部門の責任者
栄養管理士
その他委員長が必要と認めた者
2 委員長は、実務を行わせるために、上記委員若干名により構成される部会等を設けることができる。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、必要があるときは任期の途中で変更を行うことができる。
運営
第4条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
3 委員は、委員長の命を受け会務を掌理する。
開催
第5条 委員会は、毎月1回を定例会として招集するほか、必要に応じて委員長が招集する。
関係者の出席
第6条 委員長が必要と認めたときは、関係者の出席を求めることができる。
報告と指導
第7条 委員会は、審議した事項を院長に報告するものとする。また、審議結果を院内各部署に報告し対策について指導する。
庶務
第8条 委員会の庶務は、事務部企画総務ユニットで行う。
雑則
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
2-2) JR東京総合病院院内感染対策委員会細則
JR東京総合病院院内感染対策委員会規程第9条の規定により、JR東京総合病院院内感染対策委員会細則を定める。
- (1)院内感染対策委員会目的
- 1)医療機関全体として組織的な対策を実施する。
- 2)院内スタッフが感染対策のための正しい知識をもち感染防止技術を身につける。
- 3)患者と家族(面会者含む)及び院内スタッフへの院内感染リスクを最小限にする。
- (2)院内感染対策委員会審議事項
- 1)感染対策に必要と考える施設や設備の妥当性を検証し、予算を計上する。
- 2)最新の情報に基づいた感染対策マニュアルを整備し、周知徹底をはかる。
- 3)年に2回以上の感染対策に対する講演会等の啓蒙活動を行う。
- 4)各職場での院内感染の実態把握とそれに伴う感染対策技術の指導を行う。
- 5)院内感染に関連する事故などに対する迅速かつ、適切な対応と事後処理の策定と実施。
- 6)院内スタッフの安全を確保するための対応を協議する。
- (3)付属した部会等の組織の設置
- 1)感染対策チーム(以下ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)は、院長直轄の組織である。医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・リハビリテーション技師・放射線技師・事務担当者等のメンバーから成り、アウトブレイクの対応、感染サーベイランス、感染対策マニュアル作成、院内ラウンドによる現状把握・指導を行う。
- 2)看護部長より任命されたメンバーで構成される看護部感染対策委員会および、同じく任命されたリンクナースを含めた看護部感染対策拡大委員会を設置する。
これら委員会は、各部署における感染対策の実践、周知徹底のための指導、教育、院内感染に関する情報の把握、サーベイランスなど感染対策全般に関わる。 - 3)院内感染対策委員会での決定事項や感染対策に関わる注意事項などは適宜、全体連絡会議あるいは看護師長会議、看護部感染対策委員会および看護部感染対策拡大委員会において報告し、スタッフに周知徹底を図る。
- 4)臨床検査科また、薬剤部も必要に応じて定期的に院内の感染情報をICTおよび院内感染対策委員会に報告する。
2-3) 感染対策チーム(ICT)活動要綱
JR東京総合病院院内感染対策委員会規程第9条の規定により、JR東京総合病院感染対策チーム活動要綱を定める。
- (1)趣旨
この要綱は、JR東京総合病院感染対策チーム(以下ICTという)の組織および運営に関し必要事項を定めるものとする。 - (2)組織
- 1)ICTは、感染対策の実働部隊として院長の直轄機関として設置する。
- 2)メンバー構成
- インフェクションコントロールドクター(ICD)
- インフェクションコントロールナース(ICN)
- 薬剤師
- 臨床検査技師細菌検査担当者
- リハビリテーション技師
- 放射線技師
- 事務部担当者
- 3)会議の開催は、毎週1回行う。
- 4)ICTの位置づけ
〔組織関連図〕
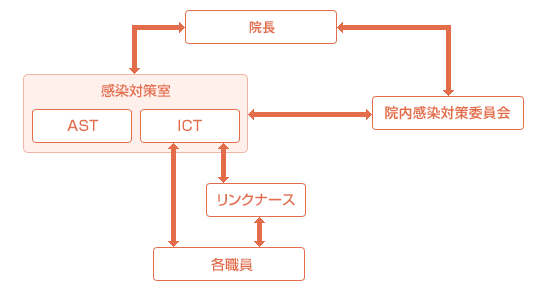
- (3)ICTの役割
- 1)感染対策に関する医療上、看護上のアドバイスを行う。
- 2)院内感染発生時に迅速な対応を行う。
- 3)感染対策に対するスタッフの教育を行う。
- 4)サーベイランスを行い、結果を現場にフィードバックし感染率の低減を図る。
- 5)院内定期ラウンドを毎週1回行い、感染対策の浸透、改善を行う。
- 6)院内感染対策マニュアルの作成、見直し、改訂を適時行いスタッフに徹底する。
- 7)環境衛生、器具導入、病院建築などの問題を検討する。
- 8)職業感染対策を行う。
- 9)抗MRSA薬の届出制、広域抗菌薬などの投与方法(投与量、投与時間など)の把握と適正化を監視する。
- (4)ICTの権限
院内における感染対策を強力かつ円滑に実行していく上で即座に活動できるチームとして、以下の一定の権限を有する。- 1)セクションの壁を取り除き、院内を横断的に動き、必要な指示・指導ができる。
- 2)感染対策において必要な場合は倫理的配慮に基づきカルテなどを閲覧でき、情報収集できる。
- 3)感染管理上の問題発生時にはICDにより招集される。
- 4)感染対策上の指導・指摘を行った部署に対して、改善事項について書面での提出を求めることができる。
- 5)ICTの活動および会議にメンバー以外の者を出席させ、必要な事項について説明を求め、または意見を聴取することができる。
- (5)各メンバー独自の役割・権限および業務
- ICD(インフェクションコントロールドクター)
- 1)役割と権限
- 感染対策の責任者である。
- 感染症の治療や抗菌薬の適正使用について主治医への指導を行うことができる。
- 病院内各部門間を横断的に動くことができ、感染対策が円滑に行われるようにする。
- 2)具体的業務
- 当院における感染対策上の問題点の把握と改善
- 病院感染発生のサーベイランス
- 感染症の治療、抗菌薬の適正使用の指導と評価
- 感染症の治療と抗菌薬使用についてのコンサルテーション
- 医師への教育実施
- 職業感染防止に関すること
- 1)役割と権限
- ICN(インフェクションコントロールナース)
- 1)役割と権限
- 病院内の各部門における感染症発生を監視し、感染防止技術などを客観的に調査、把握する。それをもとに各部門間の調整、指導を行う。
- 病棟・外来毎に配置した看護部感染対策委員会メンバーやリンクナースをまとめ、日常業務の中で発生した問題点の改善、評価をチェックし指導する。
- 病院内各部門間を横断的に動くことができ、感染対策が円滑に行われるようにする。
- 2)具体的業務
- 当院における感染対策上の問題点の把握と改善
- 病院感染発生のサーベイランス
- 感染対策に関する院内ラウンドの実施
- 感染防止教育プログラムの立案実施
- 職業感染防止に関すること
- 感染対策のための医療器材の検討、選定
- 病院環境(ファシリティマネジメント)に関すること
- 器材の洗浄や消毒、滅菌に関すること
- 感染対策マニュアルの改訂
- 院内スタッフ全員に対しコンサルテーションの実施
- 1)役割と権限
- 臨床検査技師細菌検査担当者
- 1)具体的業務
- 院内において分離された起炎菌検索・薬剤感受性成績、耐性菌の出現を把握し、ICTおよび院内感染対策委員会へ情報提供を行う。
- 注意すべき微生物、検体の取り扱いなどに関する情報をICTへ伝達する。
- 研修医をはじめとしてグラム染色などスタッフ教育を実施する。
- 1)具体的業務
- 薬剤師
- 1)具体的業務
- 抗菌薬と消毒薬の使用状況と適正使用・管理方法についてICTへ情報提供を行う。
- 感染対策上、必要とされる薬品について管理しICTへ情報提供を行う。
- 1)具体的業務
- リハビリテーション技師
- 1)具体的業務
- 当院ではリハビリテーションに対する割合が多いためICTメンバーとして加えた。ICTへ参加することでリハビリテーション科全般(対象患者、リハビリテーション技師、リハビリテーション環境など)における感染対策の中心的役割を担う。
- 1)具体的業務
- 放射線技師
- 1)具体的業務
- 当院では結核病床を2床有しており、放射線科とは密接な関係を持つこととなる。したがって、放射線科でも感染対策に対する知識を持ち、診療に活かすことは重要であるためICTメンバーとして加えた。放射線科全般(対象患者、放射線技師、検査室環境など)における感染対策の中心的役割を担う。
- 1)具体的業務
- 事務担当者
- 1)具体的業務
- ICTの庶務を行う
- 1)具体的業務
- ICD(インフェクションコントロールドクター)
2-4) 抗菌薬適正使用支援のチーム(AST)活動要綱
JR東京総合病院院内感染対策委員会規程第9条の規定により、JR東京総合病院抗菌薬適正使用支援のチーム活動要綱を定める。
- (1)趣旨
感染症治療の早期モニタリングとフィードバック、微生物検査・臨床検査の利用の適正化、抗菌薬適正使用に係る評価、抗菌薬適正使用の教育・啓発等を行うことによる抗菌薬の適正な使用の推進を行う。 - (2)組織
- 1)ASTは、抗菌薬適正使用支援の実働部隊として以下の職員による構成員を基本とする。
- 2)メンバー構成
- インフェクションコントロールドクター(ICD)
- インフェクションコントロールナース(ICN)
- 薬剤師
- 臨床検査技師細菌検査担当者
- その他感染対策に関連のある職種
- 3)会議の開催は、毎週1回行う。
- (3)ASTの役割
- 1)抗菌薬治療の最適化のため、血液培養陽性患者、耐性菌検出患者、指定抗菌薬(抗MRSA薬、カルバペネム系、ニューキノロン系、その他抗緑膿菌活性を有する特定の注射薬)長期使用患者に対し、抗菌薬ラウンドを行い、用法・用量・治療期間などが適切かモニタリングし,必要時,抗菌薬ラウンドまたは主治医へフィードバックを行う。
- 2)起因菌を特定するために、患者検体の適切な採取方法・培養検査の提出(血液培養の複数セット採取など)の推進。
- 3)施設内のアンチバイオグラムの作成し、その活用法について啓発。
- 4)指定抗菌薬の使用状況を会議にて報告。
- 5)抗菌薬の適正な使用を目的とした職員の研修を年2回程度実施。
- 6)抗菌薬適正使用マニュアルの定期的な見直しと院内採用抗菌薬の検討。
- 7)必要に応じ、連携をしている医療機関から、抗菌薬適正使用の推進に関する相談への対応。
- (4)抗菌薬適正使用支援のための権利
院内における抗菌薬適正使用支援を行うにあたり- 1)必要な場合は倫理的配慮に基づきカルテなどを閲覧でき、情報収集できる。
- 2)ASTの活動メンバー以外の者に必要な事項について説明を求め、または意見を聴取することができる。
3 スタッフ研修の基本方針
1) 院内感染対策に関するスタッフ研修の基本方針
- (1)研修の目的
院内感染対策の基本的な考え方および標準予防策、感染経路別予防策、職業感染対策など院内感染対策の具体策を全スタッフに周知し、スタッフ個々の院内感染対策に関する知識と意識の向上を図ることを目的に実施する。 - (2)研修の種類および方法
- 1)採用時研修
採用時には対象者へICTにより感染対策の基礎に関する研修を行う。 - 2)感染管理組織に所属するスタッフの研修
院内感染対策委員会、ICT、看護部感染対策委員会およびリンクナースの各メンバーは、外部研修会、研究会、学会などへ積極的に参加し、感染管理の最新知識と技術習得に努める。また、習得した知識・技術は院内へフィードバックする。 - 3)全スタッフを対象とする定期的な研修の実施
ICTが企画し、全スタッフ対象の院内感染対策研修を年間2回以上定期的に開催する。また、上記以外にも必要に応じて感染対策に関する各種研修を開催する。 - 4)部署ごとの研修の実施
ICTによる部署ごとの研修を必要に応じ実施する。
(ICTメンバーが病棟や外来などに出向き、出張講義をする等) - 5)受講機会の拡充
院内講師による研修の場合、同じ内容の研修を複数回行うなど受講機会の拡大に努める。 - 6)委託業者への教育の実施
当院に勤務する委託業者へ院内感染対策に関する教育を実施する。 - 7)結果の記録と保存
ICTは感染対策に関し実施した各種研修の実施内容(開催日時、出席者人数、研修項目、研修評価など)を記録し、保存する。
- 1)採用時研修
4 感染症発生状況の監視と報告に関する基本方針
- 1)ICTはサーベイランスデータ、院内ラウンド等からリスク事例を把握し、対策の指導を行う。
- 2)ASTは、感染症例報告、血液培養陽性例、指定抗菌薬届出報告、抗菌薬長期使用症例、抗菌薬処方状況の把握等を検討し、診療支援を行う。
- 3)サーベイランスを積極的に実施し、感染対策の改善に活用する。
- (1)院内における微生物検出状況のサーベイランス(MRSAなどの耐性菌のサーベイランス)や、薬剤感受性パターンなどの解析を行い、疫学情報を院内感染対策委員会へ報告すると共に、現場へフィードバックする。
- (2)手術部位感染、カテーテル関連血流感染、カテーテル関連尿路感染、人工呼吸器関連肺炎など対象限定サーベイランスを可能な範囲で実施する。
- (3)検査部門(医療機関における主要菌種、主要な薬剤耐性菌の分離状況を明らかにする)サーベイランス、耐性菌サーベイランスを実施する。
- (4)外来、入院病棟におけるインフルエンザ迅速検査者数、および陽性者数のサーベイランスを実施する。
- 4)感染症法に基づいて感染症を診断した場合には、診断した医師は速やかに届出を行う。
5 アウトブレイクあるいは異常発生時の対応に関する基本方針
アウトブレイクあるいは異常発生時の対応は、患者への健康被害を最小限にとどめ、病院を社会的信用の失墜から守る重要な項目である。それらの状況に速やかに対応するためには、日常的なサーベイランス、感染症報告体制を充実させ、早期にICTが介入し感染症の拡大を制御することが第一である。
- 1)各種サーベイランスをもとに、院内感染のアウトブレイクあるいは異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。
- 2)臨床検査科細菌検査室では、業務として検体からの検出菌の薬剤耐性パターンなどの解析を行って、疫学情報を日常的にICTおよび臨床側へフィードバックする。
- 3)アウトブレイクあるいは異常発生時には、その状況および患者への対応などを院長に報告する。院内感染対策委員会を開催し、速やかに発生の原因を究明する。そして、改善策を立案し実施するために全スタッフへの周知徹底を図る。
- 4)報告の義務付けられている感染症が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。
- 5)患者へ不利益なことが発生した場合の患者、家族への説明方法
- (1)患者、家族には時期を失せず誠意を持って説明を行う。
- (2)説明には、説明担当者のほか上席医師などが同席する。また、相手方にも複数の方に来ていただくよう求める。
- (3)説明は、カルテなどの記録に基づき分かりやすく行う。
- (4)原因が明らかな場合は分かりやすく説明を行う。
- (5)説明者、説明を受けた側、日時、説明内容、回答などをカルテに記載する。
※アウトブレイクあるいは異常発生時の対応チャートを参照
5-1) アウトブレイクあるいは異常発生時の対応チャート
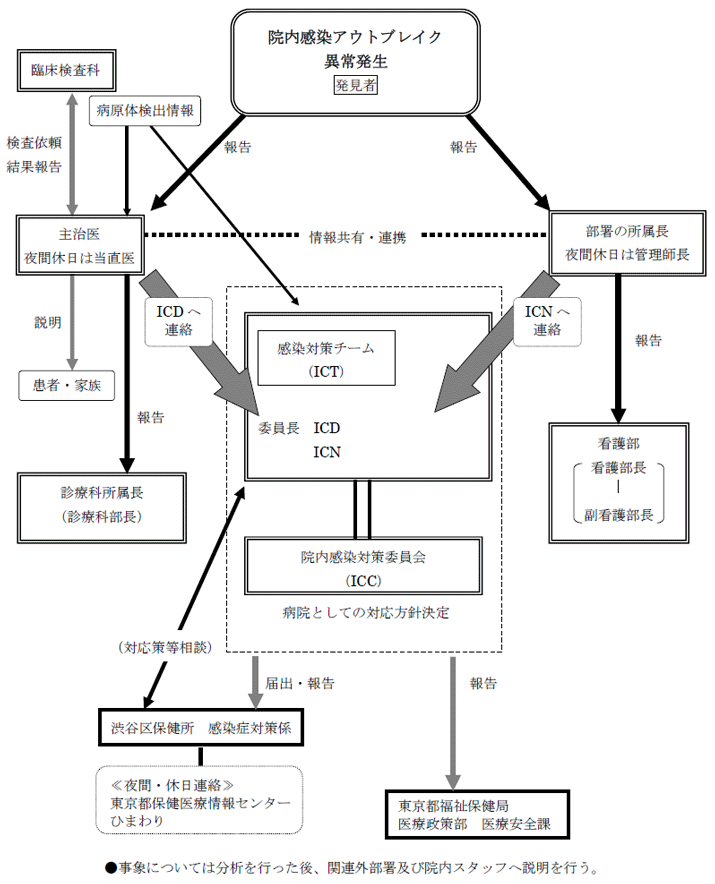
6 患者などに対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- 1)本指針は、JR東京総合病院ホームページへ一般に公開することにより患者または家族の閲覧が出来るようにする。
- 2)院内スタッフは感染対策マニュアル、JR東京総合病院ポータルサイトより閲覧することができる。
7 院内感染対策推進のために必要な基本方針
1) 感染対策マニュアルの遵守
院内スタッフは、JR東京総合病院感染対策マニュアルに記載された感染対策を実施し、感染予防策の遵守に努める。
感染対策への疑義については、院内感染対策委員会または、ICTと十分に協議する。
2) ICT・ASTとの協働
院内スタッフは、自部署の感染対策上の問題発見に努め、ICT・ASTと協働しその問題点を改善する。
3) 自己の健康管理
院内スタッフは、職種に関わらず医療従事者としての自覚に基づき、自らが感染源とならないよう定期健康診断等を年1回以上受診し、健康管理に留意するとともに、日頃から自己の健康管理を十分に行う。しかし、感染症罹患時またはその疑いのある場合は速やかに院内報告体制に基づき報告し対応する。
4) 各種抗体価の確認とワクチン接種
院内スタッフは、病院が勧奨する各種抗体価の確認、およびワクチン接種(B型肝炎、ウイルス性疾患の抗体価検査およびワクチン接種、インフルエンザワクチン接種、T-SPOT検査)に積極的に参加する。検査後の情報については各自で収集、スタッフ手帳へ記入して各種感染症に関する情報を自己管理すること。なお、ワクチン接種に対して疑問や不安などがある場合はICDまたはICNへ連絡しコンサルテーションを受けることができる。その後に接種を行うか行わないかについての自己決定をする。
令和4年10月改訂