TCFD・TNFD提言に基づく情報開示
気候変動に関する情報開示の取組みとして、2020年よりTCFD提言に基づく将来の気候変動による運輸事業における財務的影響の定量評価・開示に取り組んできましたが、この度、分析対象を運輸事業だけでなく生活ソリューション事業へ拡充しました。また、自然関連課題に関する情報開示の取組みとして、2024年度にTNFD提言に基づき、信濃川発電所を優先地域として選定し、その自然資本への依存・影響、リスク・機会について初めて情報開示を行いましたが、リスクの詳細な分析を経て、この度、リスクを低減するための指標と目標の設定を行いました。
横にスワイプできます
| 開示項目 | TCFD提言に基づく気候関連開示 | TNFD提言に基づく自然関連開示 |
|---|---|---|
| ガバナンス | マネジメント体制として、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ戦略委員会」を設置、気候変動・自然関連課題等に関する目標の設定や進捗、リスク・機会等に関する監督と意思決定を行っています。同委員会の委員は副社長・常務取締役等で構成され、社外取締役も出席し、年2回程度開催しています。また、「JR東日本グループ人権方針」のもと、事業活動の影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント活動の状況等について監督しています。 |
|
| 戦略 | グループ経営ビジョン「勇翔2034」のもと、持続可能で豊かな地球環境の実現をめざします。そのため、各種事業について、気候変動が事業活動に及ぼす重要なリスク・機会を特定、評価し、事業戦略の妥当性を検証しています。 |
複数の事業・拠点を抱える当社グループにおいて、LEAPアプローチ※1に基づき、優先度の高い事業及び地域を選定し自然関連課題の分析・評価を行っています。さらに、TNFDが提唱するシナリオを用いて自然関連のリスクと機会に対する組織の戦略のレジリエンスについて分析しています。 |
| リスク管理 | 各部門において把握した気候変動の影響を受けるリスクについて具体的な回避・低減策を講じています。気候変動の緩和に関しては、半年に1回以上、各事業に係るエネルギー使用量、CO2排出量、フロン漏洩量等を取りまとめ、法令改正等の重要な外部環境の変化を踏まえて、リスクの洗い出し・特定・評価を行っています。気候変動への適応に関しては、急性・慢性の気象災害について、主要事業における物理的リスクの低減に向けた取組みを推進しています。自然関連リスクに関しては自然・生態系に影響を与えうるリスクの特定、具体的な低減策を講じています。LEAPアプローチに基づいた分析・評価を通じて、自然関連のリスク・機会の優先順位を明確化し、気候変動の緩和策とともに、資源循環、化学物質管理、鉄道沿線環境保全等の施策を推進しています。 |
|
| 指標と目標 | 気候変動に対しては「ゼロカーボン・チャレンジ2050」を当社グループ全体の目標に掲げ、2030年度までにCO2排出量50%削減(2013年度比)、2050年度「実質ゼロ」を目標に設定。これらの進捗状況を定期的に管理するとともに、脱炭素社会の実現に向けた取組みをグループ全体で推進しています。自然関連については廃棄物排出量や植樹本数に関して目標を設定しています。さらに、LEAPアプローチに則り分析を進めネイチャーポジティブに向けた指標・目標(後述)を新たに設定しました。 |
|
- ※1TNFDが提唱する、自然関連のリスク・機会を体系的に評価するためのプロセス(LEAP: Locate, Evaluate, Assess, Prepareの略)
TCFD提言に基づく情報開示※2
気候変動に伴うリスク・機会には、地球温暖化により生じる気象災害の激甚化等の「物理的」なものと、気候変動の緩和を目的とした規制の強化や技術の進展といった社会環境の「移行」に起因するものがあります。主要事業に関する主な気候変動リスク・機会を特定するとともに、重要と認識されたリスク・機会に関するシナリオ分析を進めています。
- ※2TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)とは、企業の気候変動に関連するリスクと機会の開示を促進する国際的な枠組み。気候変動が企業の財務に与える影響を開示し、投資判断に役立てることを目的とする
リスク・機会の特定
不動産・ホテル事業(不動産・ホテル・ショッピングセンター運営事業)の主なリスク・機会(抜粋)
横にスワイプできます
| 要因 | 事業影響 | 財務的影響 | 発現・実現時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 移行リスク | 炭素価格等のGHG排出規制強化 |
操業に関わる排出量に応じた対応コストの増加 |
大 |
中期 |
ZEB規制や省エネ規制の導入 |
建物のZEB化や省エネ化に関する規制の導入強化による建設・改修コストの増加 |
中 |
短期~中期 |
|
環境性能の高い不動産の普及 |
環境性能の高い不動産の買取価格上昇による調達コストの増加 |
大 |
短期~中期 |
|
| 物理的リスク | 風水災等の気象災害の増加・激甚化 |
施設の被災に伴う復旧コストの増加、及び営業停止に伴う売上の減少 |
中 |
短期 |
平均気温の上昇 |
施設における夏季冷房コストの増加 |
中 |
短期 |
|
| 機会 | エネルギー効率の向上 |
既存設備のエネルギー効率向上や高効率化ビルへの移転、建て替えによる操業コストの減少 |
大 |
中期 |
再エネ・省エネ技術の進展 |
再エネや省エネに関する技術革新による導入コスト及び操業コストの減少 |
大 |
中期 |
|
環境意識の高いテナント企業の増加 |
環境性能の高い不動産や環境認証を取得した不動産、環境価値を購入した不動産の賃貸収入の増加 |
中 |
中期 |
|
財務への影響度及び発現・実現時期の定義は以下のとおりです。
| 財務への影響度※3 | 売上高 小:10億円未満、中:10~100億円、大:100億円以上 |
|---|---|
| 発現・実現時期 | 短期:~5年以内、中期:5年超10年以内、長期:10年超 |
- ※3財務への影響度について、移行リスク・機会については2030年前後、物理的リスクについては2050年前後における財務的影響額の推計に基づき評価しています。
シナリオ分析
脱炭素社会への移行に伴い、建物の省エネ規制が強化され、また環境意識の高いテナント企業が増加していきます。これにより、環境性能の高い不動産(グリーンビルディング)の需要が高まります。こうした社会的な要請に対応できなければ、操業コストの増加や賃貸収入の減少などの財務的影響を受ける可能性があります。
本分析では、グリーンビルディングの普及・規制導入による財務的影響を、2つのシナリオに基づき、建設・改修コスト、エネルギーコスト、賃貸収入の観点から試算しました。

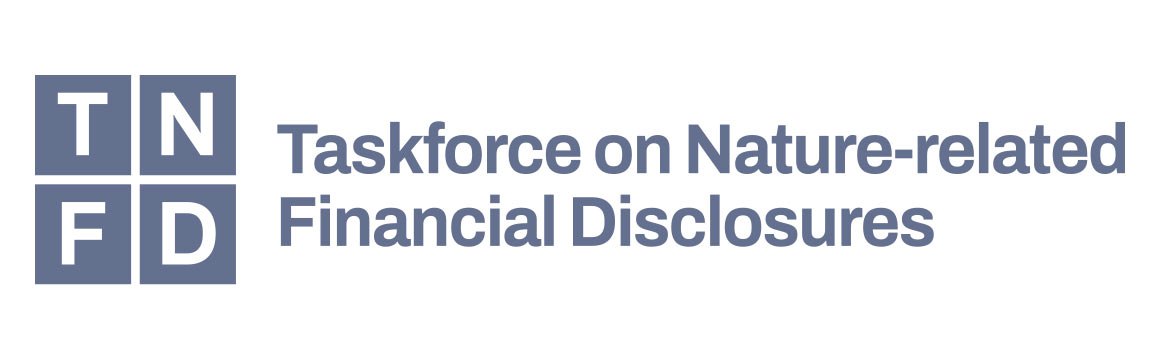

分析の対象と評価時点
不動産事業、ホテル事業、ショッピングセンター運営事業の主な施設はそれぞれ、(株)JR東日本ビルディング等が運営する物件、日本ホテル(株)等が運営する建物、(株)アトレ、(株)ルミネ等が運営する建物とする。評価時点は2030年とする。
分析を行ったシナリオとその世界観
横にスワイプできます
| グリーンビルディング導入等の取組み | シナリオの世界観 | 使用する 外部シナリオ |
||
|---|---|---|---|---|
| 実施 | 未実施 | |||
| 1.5℃ シナリオ |
シナリオ① |
シナリオ② |
2050年までにネットゼロ排出を達成するためのシナリオで、2100年時点での世界気温上昇が約1.5℃にとどまることが見込まれる。環境規制や顧客からの要請により、建物のエネルギー高効率化のための改修工事、環境性能の高い建物の建設が進み、グリーンビルディングや環境認証の取得が進む。 |
IEA,NZE |
シナリオ分析結果
横にスワイプできます
| 気候変動による2030年時点での財務的影響(億円) | ||
|---|---|---|
| シナリオ① 1.5℃シナリオ(取組み実施) | シナリオ② 1.5℃シナリオ(取組み未実施) | |
| 改修コスト・建設コストの増加 | △30.6 |
△7.7 |
| エネルギーコストの削減 | 19.8 |
3.7 |
| 賃貸収入の増加 | 182.5 |
△165.7 |
試算の結果、1.5℃シナリオで環境対応を実施した場合、既存物件の改修コストとグリーンビルディングの建設コストは増加するものの、エネルギー効率改善によるコスト削減と環境意識の高い顧客からの賃貸収入増加により、追加コストを大きく上回る効果が見込まれます。一方、同シナリオで環境対応を実施しない場合、改修・建設コストは抑えられるものの、エネルギーコストの削減効果は限定的で、顧客要請に対応できないことによる賃貸収入の大幅減少が予想されることがわかりました。
TNFD提言に基づく情報開示※4
LEAPアプローチに基づいて自然関連課題の分析に着手し、詳細な検討を進めるべき優先地域として信濃川発電所(以下、信発)を選定し、これまで分析を進めてきました。
- ※4TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)とは、企業の自然資本(生物多様性、土地、水など)に関連するリスクと機会の開示を促進する国際的な枠組み。企業が自然資本との関係性(依存・影響)を理解し、自然に関連するリスクと機会を財務的に評価・開示できるようにすることを目的とする。
Prepare:戦略と目標の設定
これまでの取組みにて抽出した、信発事業における自然関連のリスクと機会について、既存の取組みや財務的影響、TNFDが提唱する自然関連シナリオを参考に、「移行リスクが顕著となる社会」と「物理的リスクが顕著となる社会」の2つのシナリオを設定し、事業に及ぼす影響を整理しました。
設定シナリオの概要
横にスワイプできます
| 移行リスクが顕著となる社会 | 物理的リスクが顕著となる社会 | |
|---|---|---|
| 社会の様相 | 自然関連の政策・規制の強化、自然関連技術の進展、自然保護活動を求める社会的な圧力の高まりが人々の生活や企業の活動に影響を及ぼすものの、資源の供給、気候の調節や災害の緩和といった生態系サービスの劣化は一定程度に抑えられている。 |
自然関連の政策・規制の一貫性の欠如、自然関連技術開発の遅延、自然保護活動への社会的な無関心により、資源の供給、気候の調節や災害の緩和といった生態系サービスが著しく劣化し、人々の生活や企業の活動に影響を及ぼしている。 |
「移行リスクが顕著となる社会」における主要なリスク・機会を下表に示します。この社会では、関連法令の規制強化、ステークホルダーの信頼低下や要請の高まりが事業に影響を及ぼす一方で、一部の事業機会については重要性が増すと予想されました。
「移行リスクが顕著となる社会」における主要なリスクと機会
横にスワイプできます
| 自然との接点 | リスク | 機会 | 既存の取組み | |
|---|---|---|---|---|
| 影響ドライバー | 水利用 |
水利用による生態系等への影響に起因する、関係法令の規制強化 |
- |
国、自治体、有識者との水環境改善に関する協議会や、各種学会への参加生態系 |
| 生態系サービス | 生息・生育環境の維持 |
生息・生育環境の劣化による、ステークホルダーからの信頼低下 |
|
|
指標と目標の設定
| 指標 | 目標 |
|---|---|
信濃川中流域の環境調査の継続的な実施 |
年1回以上 |
ステークホルダー(地元自治体、有識者等)との対話の場である検討会の継続的な開催 |
年1回以上 |
LEAPアプローチに基づく評価、シナリオ分析等の結果を踏まえて、当社グループでは、生息・生育環境が劣化して生態系保全が危ぶまれ、ステークホルダーからの信頼が低下するリスクが特に重要であると考えています。このリスクを低減するため、「信濃川中流域の環境調査の継続的な実施」、及び「地元自治体や有識者等を集めたステークホルダーとの対話の場である検討会の継続的な開催」を管理指標として設定しました。
指標と目標に関連する信発事業における具体的な取組み
河川環境を保全するための取組み
JR東日本グループでは、信濃川に生息する魚の遡上等を妨げないよう、宮中取水ダムの脇に整備した魚道のメンテナンスを行うと共に、魚道の改善に向けた研究とモニタリングを重ねています。毎年春には地元の漁協や小学生らとともに、信濃川にサケの稚魚を放流する活動を行っています。また、ダム上流から発電所下流にかけての水温調査、魚類の捕獲調査、環境DNAによる魚種の把握、サケの遡上状況調査等を実施しています。こうした取組みは、生態系へ影響をおよぼすというリスクを低減するだけでなく、自然と事業の双方にとってプラスになる機会にもなり得ると考えており、今後も継続して取り組んでいきます。
地域コミュニティとの対話
JR東日本グループは長年にわたり取水が流域に与える影響を観測・評価し結果を公表してきました。また「信濃川中流域水環境改善検討協議会」をはじめとした会議に参加し、事業活動と信濃川中流域の自然との調和について地域コミュニティとの対話を続けています。
また2024年には、地域住民、漁協、有識者(魚類、河川環境、生態学等の専門家)とともに信濃川中流域の河川環境や生物多様性の保全を検討する場として、当社グループが事務局となり「JR信濃川発電所に係る河川環境検討会」を新たに発足しました。2025年6月に第2回検討会を開催し、これまでの河川環境に係る当社の取り組み、宮中取水ダムからの河川環境に配慮した放流方法についての検討報告、信濃川発電所に係る生物多様性の保全に向けた魚類の生息及び遡上・降下に関すること等について関係の皆さまからご意見をいただきました。
引き続きTNFD提言に基づいた自然関連リスク・機会の評価及び指標と目標の管理を継続するとともに、信濃川中流域における発電事業と自然との調和活動を推進し、地域コミュニティや河川管理者等のステークホルダーと協力しながら、ネイチャーポジティブの実現に向けてグループ全体で取り組んでいきます。