血液・腫瘍内科
特色
血液・腫瘍内科では、白血球、赤血球、血小板などの血球数の異常に対する診療と白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの血液細胞由来の悪性腫瘍の診断・治療を二本柱としています。
血球数の異常には、鉄やビタミンなどの欠乏による貧血、本来は病原微生物を攻撃するために存在する免疫系が血球細胞を標的とするために起こる自己免疫性の溶血や血小板減少、血球産生の場である骨髄の細胞成分が消失して脂肪に置き換わってしまう再生不良性貧血などがあります。これらの病気の多くは、外来での補充療法や免疫抑制療法によって治療することが可能です。
血液・腫瘍内科の診療においてより大きな部分を占める病気が血液腫瘍です。その多くは外来で診断を確定した後に入院となり、治療を開始する場合が多いですが、治療の継続は外来、または外来と入院を組み合わせた形で行っています。以前の血液腫瘍に対する治療はいわゆる抗がん剤を何種類か組み合わせたものでしたが、がん化の仕組みが明らかになって原因となる異常分子を標的にした治療や、特定の細胞だけを選択的に攻撃する抗体療法、さらには腫瘍に対する免疫反応を活発にする薬剤など種々の作用を持つ薬の組み合わせで治療が行えるようになりました。このため以前ほどの長期入院を必要としなくなっています。
日々の診療において最も重視している点は、患者さんの治療を安全に行うこととご自身の病気を理解して頂いて納得・安心の上で治療を行うことです。病気の状態に関してわかっていることをできる限り平易な言葉で説明し、病気に関して十分に理解し安心して治療に臨んで頂けますよう最善を尽くします。急性白血病や悪性リンパ腫など入院での治療が必要な病気に関しては、毎週水曜日に部長回診を行って十分な討議を行い正確な診断を確定した上で栄養状態なども把握し最新の情報に基づいて最も安全かつ有効と考えられる治療を選択しています。もちらん社会的背景も考慮し、それぞれの患者さまに適した治療方針を立てています。
治療にあたっては、他科との連携を緊密にして、種々の合併症・副作用に対して的確に対処できる体制をとっています。また栄養状態の改善を目的としたNSTチームからの助言、積極的な治療が困難な末期の患者さまにおける緩和ケアチームとの協力等により医療の質を高め、快適な療養生活が送れる環境を整備しています。外来の化学療法は、当科もその運営に関与している化学療法室で専門的に行っていますので、より安全に高いアメニティーのもとで行うことが可能です。
得意とする疾患と治療
急性白血病
多くの場合、診断が疑われてすぐに検査、入院での治療の開始が必要な病気です。急激に白血病細胞が増殖するために、骨髄の働きが抑制されて貧血、正常白血球の減少による感染・発熱、血小板減少による紫斑、出血などがみられます。
これらの症状をコントロールしながら、先ずは比較的大量の抗がん剤を用いて体の中からほとんど白血病細胞がなくなる寛解状態を目指した寛解導入療法を行います。治療開始前の検査によりあらかじめ白血病の性質を見極め、高齢の方の場合は体力・栄養状態なども考慮して寛解状態に達した時点で造血幹細胞移植を行うかどうかを決めます。造血幹細胞移植が必要な場合には比較的早い段階で東京大学医学部附属病院や虎の門病院などにご紹介、転院としています。移植を行わない場合には続けて抗がん剤を用いた地固め療法を行って体の中に残っている白血病細胞を根絶します。近年は血液学の進歩により白血病も細かく分類されており、どのタイプの白血病であるかによって治りやすさ、有効な治療法が異なりますので、当科では初診の時点で分子生物学的手法なども併用することによって正確な診断を確定することを重視しています。また、病気に対して理解し大変な治療を受け入れて頂くために心理面も含めてできる限りの支援をさせて頂きます。
近年は造血幹細胞移植の適応とならない高齢者の急性骨髄性白血病が増加していますが、これに対して比較的マイルドな治療法であるベネクレクスタとビダーザの併用療法が行えるようになり多くの患者さんで生存期間の延長などの効果を挙げています。
慢性骨髄性白血病
急性白血病とは対照的に検査から治療まですべて外来で行える疾患です。これは血液学の進歩によって慢性骨髄性白血病の本体が解明され、この病気に特徴的な染色体転座の結果つくりだされるbcr-ablチロシンキナーゼに対して非常に特異性の高い分子標的療法剤が開発されたことによります。
実際の現場では、血液検査の結果から慢性骨髄性白血病が疑われた場合に骨髄検査が行われ、分子生物学的な検査法によって確実に診断されます。診断が確定した時点でbcr-ablチロシンキナーゼ阻害剤の内服を開始し、その後のコントロールも通常は外来通院のみで行えます。副作用に注意しながらbcr-ablチロシンキナーゼ阻害剤の内服を継続しますが、一部の患者さんでは薬を中止しても再発しない状態まで腫瘍量が減らせる場合もあります。
慢性リンパ性白血病
欧米では発症頻度の高い病気ですが我が国では白血病の数パーセントを占めるのみです。高齢者に多く、また現時点の抗がん剤治療では完全には治癒しないので、赤血球、血小板数がある程度保たれている状況であれば経過観察する場合が多いです。また我が国の慢性リンパ性白血病は欧米に比較して病気の進行速度も遅くゆるやかではないかと思われます。白血病自体よりは病気の進行に伴う免疫力の低下から感染症が起こって命取りとなることが多いので、ガンマグロブリンの投与、細菌およびウイルス感染症の早期発見・早期治療に主眼をおきます。
悪性リンパ腫
悪性リンパ腫は主にリンパ節において白血病の構成成分であるリンパ球が悪性腫瘍化したものです。悪性リンパ腫は様々な病型に分類され、病型により病気の進み方や治療法が異なります。そのため、悪性リンパ腫が疑われる場合、正確に診断をすることが大切です。当院では悪性リンパ腫を疑った場合、担当部位の科に依頼して手術で病変を採取します。診断は悪性リンパ腫を専門とする病理医に直接依頼して遅延なく正確な診断が行われます。
治療に関しては悪性リンパ腫の病型に基づき決定します。当院では70歳以上の患者様を治療することも多く、治療法に関してはガイドラインなどを参照するとともに、患者様やご家族の希望を伺い、患者様の全身状態、通院のしやすさなどを考慮に入れた総合的な医学的判断に基づいて決定します。年齢や全身状態により標準量での治療が難しい場合でも、薬剤を減量するなどして標準的な治療を行えるよう調整しています。基本的には外来で治療を行いますが、全身状態に応じて診断前から入院する場合や、入退院を繰り返して治療する場合もあります。悪性リンパ腫は一般的に、一定期間に集中して治療し、治療終了後は外来で経過を観察します。治療で燃え尽きることなく、治療終了後は速やかに自分の生活が取り戻せるよう、工夫して治療しております。
多発性骨髄腫
多発性骨髄腫は形質細胞という抗体産生細胞の悪性腫瘍です。多発性骨髄腫は正常の体の機能に様々な障害を加えます。そのため貧血や骨折、腎障害、感染にかかりやすくなるなどの障害が出ます。近年治療薬の進歩が著しく、症状の改善や生存期間の延長を認めますが、継続する治療法が大半を占めることから、治療とうまく付き合っていかなければなりません。治療法に関してはガイドラインなどを参照し、その時点で適切な治療法を選択しますが、多発性骨髄腫は初回の一連の治療で病気の勢いを最大限に抑えることが大切であり、治療法を工夫しながらより良い状態に到達することを目指します。治療が継続できるように、一人一人の状態にあった治療法を選択し、副作用対策をしっかり行います。当院では70歳以上の患者様を治療することが多く、抗体薬を含めた標準治療を行いますが、ご高齢、全身状態が悪い患者様でも、病勢改善により全身状態が改善することがありますので、治療を希望される場合、当院では積極的に治療します。また、当院は自家末梢血幹細胞移植を行っており、その時点の治療方針に基づき、該当者には移植しております。
貧血
主に外来で種々の貧血の原因検索を行い、それぞれの原因に即した治療を行っています。最も多いのは鉄欠乏性貧血ですが、便検査および女性の場合には産婦人科への紹介によって原因を明らかにし食事指導も含めて鉄剤の投与を行います。妊娠可能年齢の女性の場合、一旦よくなった後も完全に鉄剤をやめてしまうと再び貧血となることが多いので数日に1錠でも鉄剤の内服を続ける必要があります。そのほかの原因としてビタミンB12または葉酸の欠乏、赤血球が破壊される溶血性貧血、骨髄自体が赤血球をはじめとする血球細胞を産生しなくなる再生不良性貧血、前白血病状態と考えられる骨髄異形成症候群などがあり、それぞれの原因に即した治療を行います。
骨髄異形成症候群は特に高齢の患者さまでは貧血の原因として多い疾患ですが、ビダーザの皮下注によって改善し、輸血が必要なくなる患者さまが多数いらっしゃいます。貧血を指摘された場合にはぜひ一度当科をご受診ください。
血小板減少
血小板の減少を起こす病気では特発性血小板減少性紫斑病の頻度が最も高いです。原因となる可能性のあるピロリ菌感染の有無を調べて、もしあれば積極的に除菌療法を行います。血小板数が少なめでも慢性的であって低下傾向がなく臨床症状もない場合には無治療で経過観察をしていることも多いです。この他に血小板減少の原因として播種性血管内凝固などの重大な病気が隠れている可能性がありますので治療は行わない場合でもできる限り原因を確定し定期的に経過を観察しています。
骨髄増殖性腫瘍
貧血や血小板減少とともに赤血球や血小板数が増加する骨髄増殖性腫瘍も比較的よく見られる病気です。診断を確定した上で年齢が若く高脂血症などの合併症がない場合には経過観察、65歳以上であれば細胞増殖の阻害剤であるハイドレアの内服で血球数をコントロールします。若年者で主に赤血球が多い場合には瀉血を行っています。通常は1-2ヶ月に1回の受診でコントロールが可能です。
リンパ節腫脹
全身のリンパ節は骨髄とともに血液内科が担当する臓器であり、原因がはっきりしないリンパ節腫脹の診療を担当しています。リンパ節腫脹の原因の決定にあたっては触診を含めた診察、超音波やCTなどの画像診断、種々の血液検査などを総合して診断を進めます。これらの検査で診断がつかないもののリンパ節の大きさが増大傾向であって悪性腫瘍その他の重篤な疾患が疑われる場合には、腫脹しているリンパ節の一部を手術的に採ってくるリンパ節生検を行って最終的に診断を確定します。
出血傾向・凝固異常
出血傾向・凝固異常の診療においても、どこに異常があって病気が起こっているのかを明らかにするために、丁寧に問診・診察した上で臨床経過を把握し、必要十分な検査を行っています。検査のみに頼ると検査の誤差や非特異的な変動に振り回されることになりますので特にこの領域ではこれまでの経過や使用薬剤の十分な把握を重視して効率のよい診療を心掛けています。比較的稀な疾患とされる後天性血友病なども数年で2例を経験しており、いずれも入院治療で寛解となりました。
スタッフ紹介

- 役職・医師名
- 副院長 杉本 耕一
- 得意な分野
- 悪性リンパ腫、慢性リンパ性白血病
貧血およびリンパ節腫脹の鑑別診断
骨髄増殖性腫瘍 - 認定等
- 日本内科学会認定総合内科専門医
日本血液学会認定血液専門医・指導医、評議員
日本がん治療認定医機構がん治療認定医・暫定教育医
日本東洋医学会認定漢方専門医
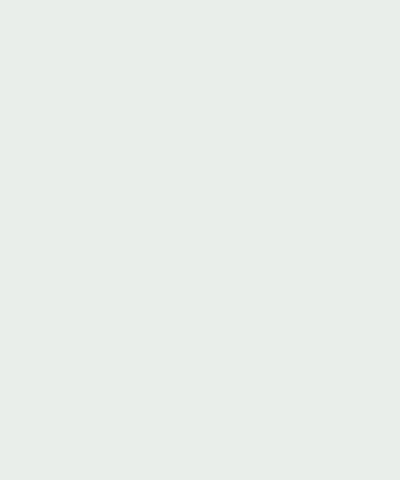
- 役職・医師名
- 医長 奥田 慎也
- 認定等
- 日本内科学会認定総合内科専門医
日本血液学会認定血液専門医
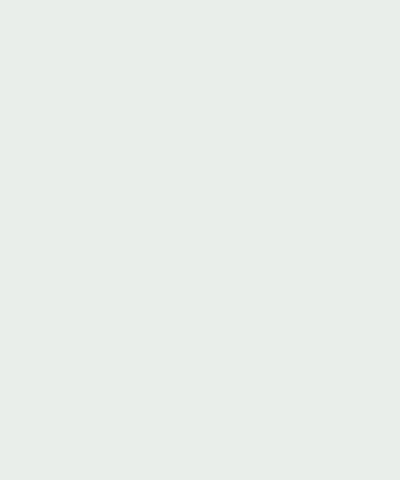
- 役職・医師名
- 医長 安永 愛
- 認定等
- 日本内科学会認定総合内科専門医
日本血液学会認定血液専門医
日本医師会認定産業医
日本造血・免疫細胞療法学会造血細胞移植認定医
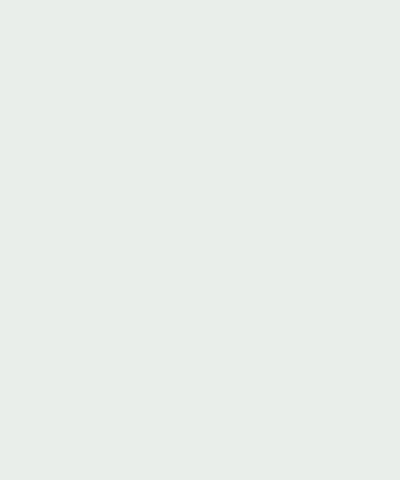
- 役職・医師名
- 非常勤医師 竹林 ちあき
- 認定等
- 日本内科学会認定総合内科専門医
日本血液学会認定血液専門医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医・暫定教育医
日本化学療法学会認定抗菌化学療法認定医
スタッフによる著書
1.杉本耕一:25急性白血病.宮園浩平、石川冬木、間野博行 監訳、デヴィータ がんの分子生物学 第2版:474-499、メディカル・サイエンス・インターナショナル、2017(翻訳)
2.杉本耕一:26慢性白血病.宮園浩平、石川冬木、間野博行 監訳、デヴィータ がんの分子生物学 第2版:500-515、メディカル・サイエンス・インターナショナル、2017(翻訳)
3.杉本耕一:Part12 クリティカルケア Section4 腫瘍に関連する救急疾患 331章 腫瘍に関連する救急疾患.福井次矢、黒川清 日本語版監修、ハリソン内科学 第5版:1836-1847、メディカル・サイエンス・インターナショナル、2017(翻訳)
4.杉本耕一:Part VI 二次性貧血 3 ACDと鉄欠乏性貧血との鑑別.貧血学:535-539、日本臨牀社、2017
5.杉本耕一:23悪性腫瘍 リンパ性白血病.横田千津子、池田宇一、大越教夫監修、病気と薬 パーフェクトBOOK:1466-1473、南山堂、2012
6.杉本耕一:造血器悪性腫瘍.高橋和久編、講義録 腫瘍学:162-168、メディカルビュー社、2009
7.杉本耕一:真性赤血球増加症、本態性血小板血症、慢性特発性骨髄線維症.山口徹、北原光夫、福井次矢編、今日の治療指針2009版:491-493、医学書院、2009
8.杉本耕一:第IV編 臓器・患者別腫瘍学 25造血器腫瘍学.樋野興夫、木南英紀編、がん医療入門:144-148、朝倉書店、2008
9.杉本耕一:第10章 血液腫瘍 4 MALTリンパ腫の治療.中川和彦、勝俣範之、西尾和人、畠清彦、朴成和編、Cancer Treatment Navigator:200-201、メディカルレビュー社、2008
10.杉本耕一:第2章 血液・造血器系の疾患 10血友病.富野康日己、望月正隆編、疾患と薬物治療:47-49、医師薬出版株式会社、2008
11.杉本耕一:第2章 血液・造血器系の疾患 9 播種性血管内凝固(DIC)、富野康日己、望月正隆編、疾患と薬物治療:44-46、医師薬出版株式会社、2008
12.杉本耕一:82.G-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)フィルグラスチム、レノグラスチム、ナルトグラスチム、富野康日己編、基本治療薬115 使い方と禁忌:304-306、中外医学社、2007
13.杉本耕一:81.分子標的治療薬 リツキシマブ. 富野康日己編、基本治療薬115 使い方と禁忌:304-306、中外医学社、2007
14.杉本耕一:第3章 血液・造血器疾患 7 骨髄異形成症候群.矢崎義雄、乾賢一編、薬剤師・薬学生のための臨床医学:242-244、文光堂、2005