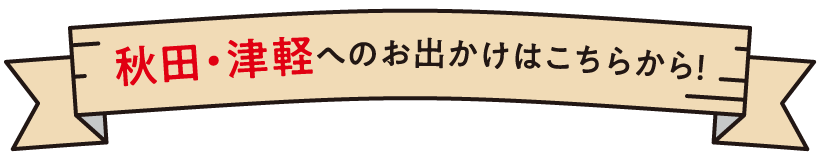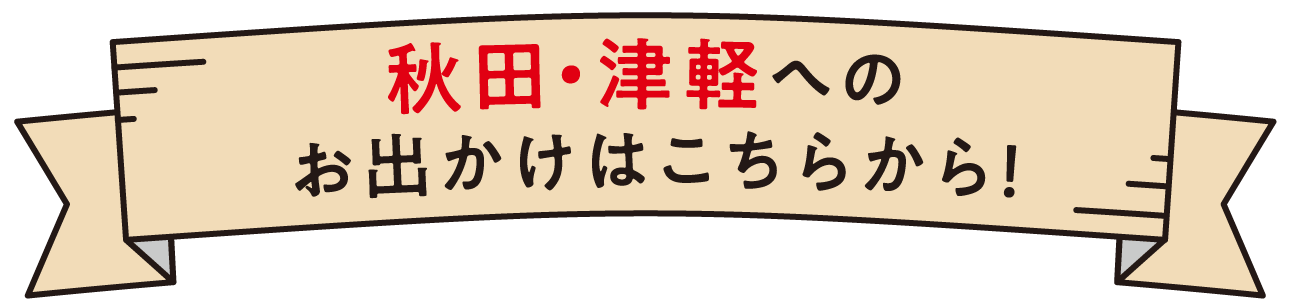弘前公園からほど近くにある「藤田記念庭園」。大正10年、弘前出身の事業家・藤田謙一が別邸を構える際、東京から庭師を招いて江戸風な景趣の庭園をつくらせました。みちのく銀行の管理所有を経て、市制施行100周年事業として弘前市が整備を進め、平成3年7月に一般へ向けて開園。園内は崖地をはさんで高台部と低地部に分かれ、登録有形文化財に指定された貴重な建築物も。四季折々に表情を変える美しい庭園をひと目眺めようと、国内外から多くの観光客が訪れています。

津軽のいろいろ 「弘前市」
青森県の最高峰・岩木山の麓に広がる青森県弘前市。桜まつりで有名な弘前公園の弘前城を囲むように神社や仏閣が建てられ、今も重要な文化財が残る城下町です。文明開化の波に乗って建てられた洋館も多く、当時の面影を残すレトロな建築物からロマンを感じます。美しい古都の文化に触れながら、街をのんびり散策しませんか。
四季折々の風景が迎える 異なる趣の2つの庭園





- 藤田記念庭園
- 住所:青森県弘前市大字上白銀町8-1(藤田記念庭園管理事務所)
- TEL:0172-37-5525
- 営業時間:9:00〜17:00(最終入園16:30)
- 定休日:無休
- 料金:大人320円、小・中学生100円
大正時代の情趣に富んだ洋館 庭園を眺めてくつろぐひととき





藤田記念庭園敷地内の、赤いとんがり屋根の洋館内にある「大正浪漫喫茶」。弘前市における代表的な近代建築の担い手・堀江佐吉の子孫が設計・施工にあたった同建築物は、国の登録有形文化財に指定され、館内には施主である藤田謙一資料室を備えています。陽の光を通して輝くステンドグラス、暖炉やランプなど、大正時代を彷彿とさせるインテリアの数々を眺めていると、なんだか懐かしい気持ちがこみあげてきます。
喫茶では、ガレットやシードルなど県産食材を使ったメニューを提供し、とりわけ人気を集めているのがアップルパイ。市内の協力店が毎朝配達してくれる作りたてのアップルパイを常時6種類以上ラインアップし、これを目当てに訪れる観光客でにぎわっています。窓際の特等席で高台部の庭園を眺めながら、ホッと一息ついてみませんか。
- 大正浪漫喫茶室
- 住所:青森県弘前市大字上白銀町8-1(藤田記念庭園 洋館内)
- TEL:0172-37-5690
- 営業時間:9:30〜16:30(LO16:00) ※席利用は60分制
- 定休日:無休
- 料金:入館無料
手仕事のぬくもりが息づく メイド・イン・津軽に溢れた喫茶



当別邸建築と同時に現在地に建てられた、岩木山麓開発事業の事務所倉庫。かつては「考古館」として弘前市内から出土した旧石器〜江戸時代までの遺物などを展示していましたが、平成29年に〈和〉をテーマにしたカフェとしてリニューアルしました。こぎん刺しや津軽塗などの工芸品が一同に揃う展示・販売スペースを備え、津軽で古くから紡がれてきたものづくりに関わる情報発信の拠点にもなっています。
地場で採れた野菜や果物をふんだんに取り入れ、仕入れによって献立が変わる「おばんざい定食」を提供。甘味に使うみつやシロップ、白玉まで自家製にこだわり、素材を生かしたやさしい甘さと素朴な味わいが話題を呼んでいます。また、テーブルやチェア、使用する食器のほとんどが手工芸品のため、手仕事のぬくもりが随所に感じられます。
- クラフト&和カフェ 匠館
- 住所:青森県弘前市大字上白銀町8-1(藤田記念庭園 旧考古館内)
- TEL:0172-36-6505
- 営業時間:9:30〜16:30
- 定休日:無休 ※年末年始は休み
- 料金:入館無料
例大祭の前夜に心が弾む 津軽ならでは夏の風物詩

「弘前天満宮」で2024年6月24日に開かれた宵宮の様子。薄暮が迫る風景の中に約30軒の露店の明かりが灯り、例大祭の前夜を彩った。

どこか幻想的なムードが漂う夕暮れの社殿。老若男女が参拝のために列を作った。
短い夏の訪れとともに各地の神社や寺院で催される宵宮(よみや)。明治頃から続くこの風習は津軽地方ならではの文化です。本来、神社仏閣で行われる例大祭に参列できるのは氏子などに限られますが、前夜祭である宵宮は誰もが楽しめるもの。開催当日に打ち上げられる花火の音が聞こえると人々の心は浮き立ち、自ずとその日行われる宵宮へと足を向けます。日が暮れる頃に神社や寺院周辺の沿道に出店がずらりと並び、境内では催しが行われることも。ひっきりなしに参拝客が訪れ、夜遅くまでにぎわいを見せます。
- 開催:弘前周辺の市町村は毎年5月〜10月 ※神社仏閣により異なる
きもの専門店で粋な装いを 浴衣で愉しむ宵宮のすゝめ







創業40年を迎えた「きもの専門店 夢や」。これまで1,000名以上の採寸、5,000枚以上の仕立てを行った実績が裏打ちする技術と経験で、一人ひとりの要望に寄り添った仕立てやお直し、コーディネートを行う呉服店です。店主の小林さんは、「一人でも多くの人に、一度でも笑顔で着物を着てほしい」と創業から変わらぬ想いで店舗を運営。誰でも気軽に和服に親しめるようにと、8年前にレンタルサービスを開始しました。
観光や冠婚葬祭のための着物はもちろんのこと、花火やまつりが続くシーズンには浴衣を提供(6月中旬〜8月末まで)※「期間以外のレンタルはご利用いただけません」と店主。日本人が和服に袖を通す機会が減ってきたと言われる中で、「せっかくの機会に浴衣が着たい」と訪れる人々の願いを叶えてきました。100着以上を揃える浴衣の中からチョイスした自分好みの1枚に、小物を合わせてトータルコーディネート。「花火やまつりの会場で着崩れることがないように」と心配りが行き届いた着付けで送り出してくれる、店主夫妻のあたたかな人柄も同店の魅力のひとつです。
- きもの専門店 夢や
- 住所:青森県弘前市元大工町1-1
- TEL:0172-32-8111
- 営業時間:10:00〜18:00 ※まつり期間は返却対応のため〜21:00頃
- 定休日:日曜 ※ほか不定休あり
- 料金::浴衣レンタル 5,000円〜(料金はサイズにより異なる) ※夏季(6月中旬〜8月末まで)限定。着付け、一式(浴衣・帯・飾り紐・下駄・巾着)を含む。ヘアメイク要望の場合は提携美容院にて別途
着物レンタル 15,000円〜 ※通年(夏季を除く)。着付け、一式(着物、襦袢、帯、帯揚げ、帯締め、足袋、草履、和鞄)を含む。ヘアメイク要望の場合は提携美容院にて別途
岩木山を臨む景勝地 〈学問の神〉を祀る地元民の拠り所





青森県の最高峰・岩木山を臨む景勝地に鎮座する「弘前天満宮」。この場所には、かつて領内修験の蝕頭(ふれがしら)を勤めてきた大行院がありましたが、明治4年の修験道の廃止によって「神道天満宮」に。移建や合祀を経て、現在は茂森町一帯の鎮守「弘前天満宮」となり地域に根付いています。岩木山と対峙するような高台の境内には社殿や社務所のほか、津軽ダム建設の際に合祀した稲荷神社、推定樹齢500年を超える県天然記念物のシダレザクラや天満宮児童公園があり、地元民の拠り所として親しまれています。
守り本尊は文殊菩薩、そして御祭神は菅原道真朝臣命(すがわらのみちざねあそみのみこと)。平安時代前期に学者・政治家として活躍し〈学問の神〉として崇められていることから、「学業成就や合格祈願のために訪れる方が多い」と15代目宮司の宇庭(うにわ)さんが教えてくれました。受験シーズンや新学期を迎える季節には、御神徳をいただきたいと多くの参拝者でにぎわうそうです。
- 弘前天満宮
- 住所:青森県弘前市大字西茂森1-1-34
- TEL:0172-32-5796
- 開所時間:社務所8:30〜16:30
- 定休日:無休
※営業時間や定休日などは、2024年7月末時点の情報です。紹介施設の都合により、変更になる場合があります。
記事作成:あきたタウン情報