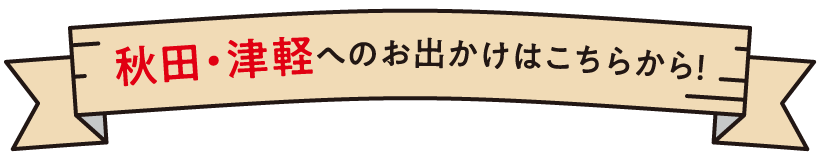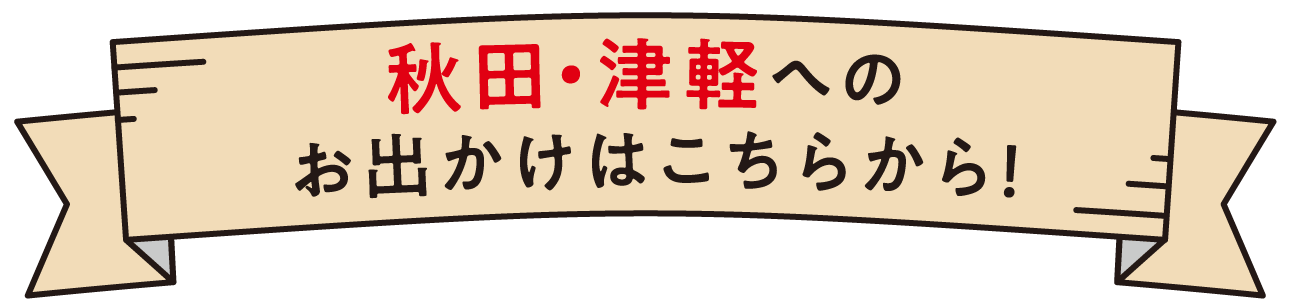弘前公園(弘前城)は、「日本三大桜名所」のひとつに数えられ、国内外から例年約200万人が訪れます。
弘前公園の桜の歴史は古く、江戸時代までさかのぼります。1715年に、津軽藩士が京都から持ち帰った桜を城内に植えたのが始まりと言われているそうです。時代が明治に移ると、廃藩によって荒れ果てた城内を見かねた旧藩士が自費で桜を植樹しました。当時は明治維新後の動乱期で、「城を行楽地にするとは何事か」と苗木が引き抜かれるなど、一部では反対の声もあったようです。反対の動きがありながらも、植樹は続けられました。大正時代になると明治期に植えた桜が見事に咲き誇るようになり、1918年には弘前商工会が主催となって現在の「弘前さくらまつり」の前身である「第一回観桜会」が開催されました。その後、太平洋戦争などで一時中断した時期もありましたが現在まで開催されています。
公園内には多数のフォトスポットがあります。西濠に架かる春陽橋は、園内で最長の橋です。西濠を挟んで両側には多くの桜が並びます。夜間になると、ライトアップによって桜の花と橋が水面に反射し、幻想的な景色が現れます。

桜の名所に出かけよう!
津軽の桜は4月中旬からゴールデンウィークにかけて見頃を迎えます。桜の名所と言えば弘前公園を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、それだけではありません。この春は津軽エリアで咲き誇る各地の桜を見に行きましょう。
まずは大定番 弘前公園




昨今SNSで「桜のハート」と話題となっているのは、2本の桜の枝が重なって空にハートを描いたように見える隠れたスポットです。管理する弘前市によると、場所は非公開。園内を散策しながらぜひ探してみてください。

桜が満開となってから散ってしまうまでは、わずか1週間程度と言われています。弘前公園ではお濠端の桜が見頃を終えて散っていくと、徐々に花びらが水面を埋めていき、美しい花筏へと変わります。ピンク色の絨毯とも形容される、散ってもなお美しい風景が楽しめます。
- 弘前公園(弘前市役所 公園緑地課)
- 住所:青森県弘前市下白銀町1
- TEL:0172-33-8739(弘前市役所 公園緑地課)
- URL:https://www.hirosakipark.jp/
岩木山と桜



古くから信仰の対象として地域から愛されてきた津軽富士「岩木山」。津軽の桜の名所といえば先にご紹介した弘前公園が有名ですが、岩木山麓の山桜も必見です。 山麓に続く桜並木は、「世界一の桜並木をつくろう」と地元の人たちの手によって1985年から植えられたもので、1995年まで10年間かけて約6500本のオオヤマザクラが植えられました。 総延長約20kmにわたる濃紅色の桜並木。晴れた日には残雪の岩木山を背景に桜を眺めながら、鯵ヶ沢町へと続くドライブコースをお楽しみください。 開花時期は例年4月下旬から5月上旬で、標高の低い場所から高い方へ10日以上咲き続けます。
- 岩木山観光協会
- 住所:青森県弘前市大字百沢裾野124
- TEL:0172-83-3000
- URL:http://www.iwakisan.com/
列車と桜

「芦野公園」は、作家・太宰治生誕の地、旧金木町(現在の五所川原市)にあります。太宰も幼少の頃よく遊んでいたと言われているこの公園は、「日本のさくら名所100選」にも選ばれています。約80万平方メートルの広大な園内では、春になると約1500本の桜が咲き誇ります。また、公園内には津軽鉄道「芦野公園駅」があるので、アクセスは津軽鉄道がおすすめ。線路を覆う桜のトンネルの中を列車が走る様子は幻想的で、沿線ではカメラを構える観光客が多く見られます。
- 五所川原観光協会
- 住所:青森県五所川原市字大町38
- TEL:0173-38-1515
- URL:http://www.go-kankou.jp/
猿賀公園



平川市の猿賀神社は、坂上田村麻呂が蝦夷平定の際に建立したとされる由緒ある神社で、見晴ヶ池と鏡ヶ池の2つの池を含む広い境内や隣接する猿賀公園は桜の名所として地域の人々に愛されています。園内にはシダレザクラや、ソメイヨシノ、八重桜など約330本が咲き乱れ、例年4月下旬から5月上旬にかけて、平川さくらまつりが開催されます。鏡ヶ池の中心に鎮座する真っ赤な社(猿賀神社の末社で「胸肩神社」)は、桜とのコントラストが何とも美しい、写真映えスポットです。
この他、夏には蓮の花が咲き誇り、秋には紅葉、冬には真っ白な雪に公園全体が包まれ、四季折々の美しい景色を堪能できます。
- 平川市観光協会
- 住所:青森県平川市猿賀石林94 平川市ふるさとセンター1階
- TEL:0172-40-2231
- URL:https://hirakawa-kankou.com/
今年2023年は、桜が見頃を迎える4月から6月までの3カ月間、津軽エリアでは津軽観光キャンペーン「ツガル ツナガル」を開催します。この後も津軽の情報をたっぷり紹介していきますよ! この春は是非、津軽へお出かけください♪皆さんのお越しをお待ちしています!!
記事作成:JR東日本秋田支社