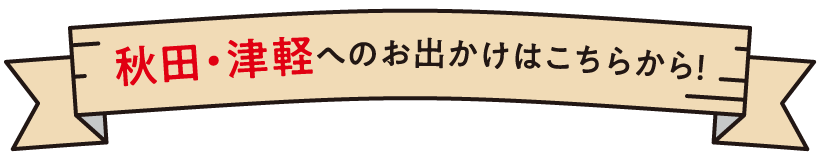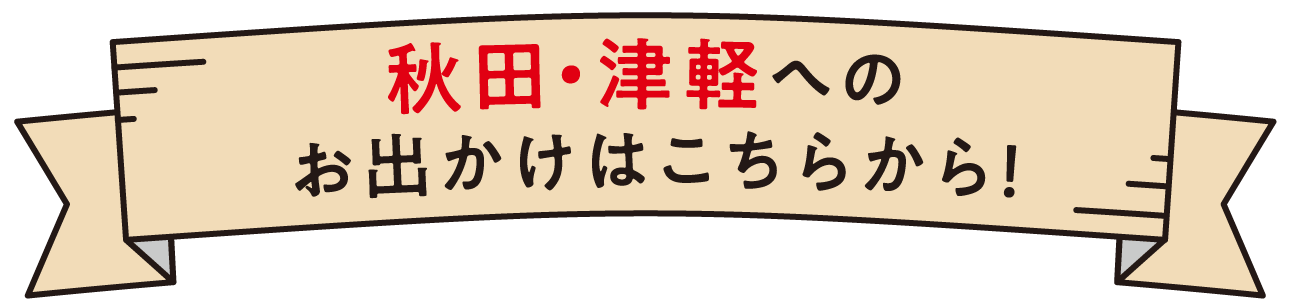石孫本店の醤油・味噌は、すべて秋田県産の米・大豆・麦を使用した天然醸造。創業からほとんど変わらない製法を継承し、当時の道具が今も現役で使用されていることに、同業者からも驚かれているのだとか。そんな全国でも稀有な存在である石孫本店では、「醸造蔵の内部見学・作業見学」(1,000円、お土産付き・要予約)を行っており、仕込みの工程に沿って蔵の中を見学することができるんです。今回は、蔵の作業の様子を見学し、石孫本店が人々に愛される秘密を知りました。
醤油と味噌の醸造で最も重要とされる「麹づくり」において、石孫本店のこだわりは顕著に見られます。現代は、機械制御によって生産の安定化を図る製法が一般的となっていますが、石孫本店では、昔ながらの「麹蓋」を使用。「麹蓋」とは、木製の四角いお盆のような形の容器で、これに材料となる種麹を混ぜた蒸米、または種麹を混ぜた炒り麦と蒸し大豆を入れ、醤油麴室では木炭と稲わらで温度調整しながら世話をし、麹を成長させます。一度の仕込みで数百枚、蔵人が一枚ずつ仕込んでいるというから驚きです。

今も昔も変わらぬ製法を守る老舗蔵の心意気
古くから酒造をはじめとする醸造業が盛んだった、秋田県湯沢市岩崎地区。少し歩くだけでも内蔵や古民家など至るところに歴史が垣間見え、風情ある町並みに出会えます。この地で安政2年に創業し、160年以上の時を経ても今なお醤油・味噌を醸し続ける「石孫本店」。国の登録有形文化財に指定されている5つの土蔵を構え、敢えて昔ながらの手造りを貫き、発酵食文化を伝え続ける石孫本店へ伺いました。
「麹蓋」が現役!? 正真正銘の手造り






麹蓋もさることながら醤油造りでは、さらに珍しい機械が稼働中! 大正期に作られ、国内で現存しているのは唯一という「麦炒り機」です。今や入手困難とされる石炭を燃料に、醤油麹作りに欠かせない麦を炒っています。
造り出すのは、”生き物”。


醤油・味噌の仕込みに使う蔵はそれぞれ独立していて、麹室から取り出された麹と原料を木桶に運び入れる作業、木桶から移す作業も、なんとすべて人力!天然秋田杉を使った30石(5.4キロリットル)もの巨大な桶がいっぱいになるまで、蔵人が担ぎ何度も往復して運び入れ、醤油のもろみは何度も撹拌しながら、味噌は発酵度合いを確かめつつ、蔵付き酵母「いしまご恵比寿酵母」によって熟成するのを待ちます。




一見効率の悪そうな作業ですが、そこには、『造り出す製品は「生き物」である』という石孫本店の考えが背景に。絶え間なく変化する「生き物」は、最先端の機械を使ったとしても制御できないことがあります。だからこそ、米や大豆、小麦の状態を常に肌で感じながら、蔵人が五感を研ぎ澄ませて作業を進めることが必要であり、伝統の製法を守ることにも繋がっているのです。
受け継がれる”本物”の手づくり〜天然醸造の味噌・醤油〜



守り続ける製法と原料にこだわった、まさに〈本物〉の手づくりである石孫本店の醤油・味噌。地域に根付く蔵元だからこそできる、親しみやすい味わいが一番の魅力です。
味噌は、風味豊かな甘みのある「五号蔵」や昔ながらの純正田舎味噌「特上石孫味噌」など、個性際立つ商品が揃い、サイズ展開もさまざま。醤油は、定番の「百寿」のほか、味噌の上澄み液を使った「みそたまり」も人気が高いです。日常使いしやすいものを中心に、プレゼントや贈り物にもぴったりな商品も展開し、蔵内の販売コーナーやWEBサイトからも購入できるので、ぜひチェックしてみてください。
発酵文化を伝える新たな挑戦!





2020年6月、「あきた発酵ツーリズム」の観光拠点としてリニューアルオープンを果たした石孫本店。以前、母屋だった場所に開放的なイベントスペースを設け、「みそボール作り」(1,500円)や「なま醤油絞り体験」(2,000円)など、楽しい体験ができるように(各要予約)。焼きたての煎餅に醤油などで味付けする「せんべい手焼き体験」(500円)は、予約なしでも参加できる気軽さが好評です。感染症拡大の影響で、体験を開催できない時期もありましたが、今年に入り再開。毎週土曜には、限定の「石孫らーめん」が味わえることもあって、多くの人が訪れにぎわう姿が戻ってきています。
郷土に根付く味を絶やさず後世に

伝統の味を継承しつつも、老舗の暖簾にあぐらをかくことなく、多くの人に訪れてもらえる企画を考え続ける石孫本店。長く醸造文化の継承活動を行ってきた石川社長は、「醤油や味噌は、多くの人が特別に意識をせず購入されていると思います。そうした方たちにも普段から関心を持ってもらえるように、常に新しいことに挑戦していきたい」と話し、発酵食を伝える拠点となった今、「県内外の方々が、街歩きや近隣の観光地に来た時の立ち寄りスポットとして、気軽に利用できる場所でありたい」とこの先のあり方にも目を向けます。20代〜60代まで幅広い年齢層の職人・従業員が揃い、近年では、社長自らが行ってきた業務も後進に任せることも多くなったとか。製法を守り続ける職人たち=発酵文化の担い手によって、”いつまでもここにあって欲しい”大切な味はこれからも受け継がれていきます。
- 石孫本店
- 住所:秋田県湯沢市岩崎字岩崎162
- TEL:0183-73-2901
- 営業時間:10:00〜16:00
- 定休日:第2土曜日
- 駐車場:あり
- https://ishimago.jp/
「手間を惜しまない」とはまさにこのこと。「食卓の基礎を作る醤油・味噌から、お客さまに健康をお届けしたい」という創業当時から変わらぬ思いで作り続ける蔵人たちの仕事への誇りと姿勢に、驚くとともに感心しっぱなしでした。私たちにずっと変わらぬ味を届けてくれることに感謝しつつ、改めて地域に根付く味を大切にしていきたいですね。ぜひ蔵見学に参加して、蔵と、働く蔵人たちの姿を見てみてください。発酵文化を知ることに留まらない、生き続ける歴史の香りと気質に心動かされますよ。
記事作成:あきたタウン情報